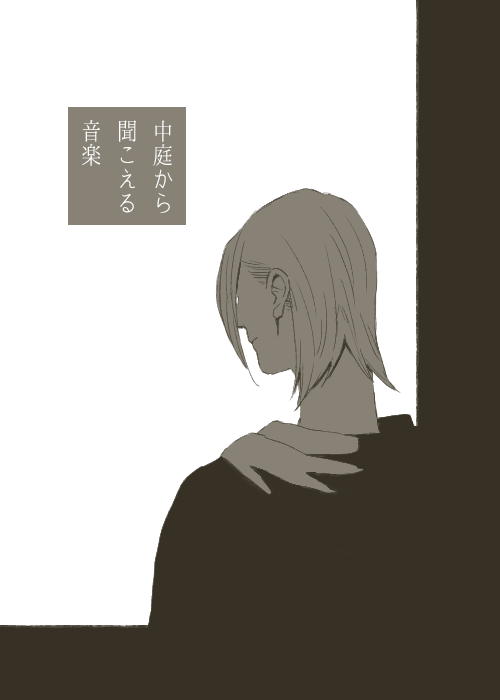1.阿万門ナユラ
吉良が辺境から三番隊舎に戻ったとき、隊士たちの集まる休憩室から聞こえてきたのは耳慣れない音だった。不思議に思い広い室内を覗き込むと、その中央の卓に着く鳳橋の周りに三番隊隊士たちの人だかりができている。こちらに背を向けている鳳橋は何か聴き慣れぬ楽器を演奏しているようだった。
「イヅル、おかえり」
霊圧で気づいていたのだろう、演奏を途中でやめた鳳橋は肩越しに振り返り、吉良に微笑みかける。
「――鳳橋隊長、ただいま戻りました」
「副隊長! おかえりなさいませ」
「お疲れ様ですー」
「吉良イヅル!」
隊士たちから掛けられたねぎらいの声を押しのけて、快活で威厳のある少女の声が飛んできた。ギョッとした吉良の視界に、鳳橋の隣に坐っていたらしい阿万門ナユラの立ち上がる姿が映る。
「久しいな、息災か」
「なぜここにいるんだい……」
「時間ができたからな。一度ここには来てみたいと思っていたのだ。聞いていたとおり、音楽は鳴っているし、隊長はゆるふわだし、お前は遅刻してくるし……」
「え……ボクがゆるふわって誰に聞いたの……」
「平子真子だ」
あー……と項垂れる鳳橋。そもそもこの少女が“ゆるふわ”という概念を知っているのか……と吉良もまたげんなりする。
一息に面倒になってナユラを無視することにした吉良は、鳳橋に目を向けて「それは新しい楽器ですか?」と訊ねた。途端に元気になって身体を起こした鳳橋が「そうっ」と明るく返事をする。その様子を見た吉良は小さく口の端を上げた。
「キーボードっていうんだ。この白鍵と黒鍵を使ってこんなふうに音を出す」
歩み寄った吉良が卓の上に見たのは、白と黒の打鍵が並ぶ横長の箱形をした機械だった。鳳橋は指先で打鍵を叩くと音階を奏で、「ここで調整していろんな音が出せるんだよ」と鍵盤上部に並んだ機構をいじくってさまざまな音を出した。
「でもボクはこの楽器はそこまで上手に扱えないから……基礎くらいなら教えられるけど、誰か興味のある子に使ってもらいたいなって。隅に置いておくからさ、誰でも使っていいものにしようよ」
「それは私でもか?」
吉良の隣でナユラが声を上げる。鳳橋が「もちろん」と答えるのに吉良は驚き慌てて口を挟んだ。
「隊長、彼女は部外者です」
「どこのどんな誰でもいてもいい場所があってもいいと思わない? 三番隊にとっての柿の木の下みたいなさ」
「…………そう、ですかね」
「この部屋には隊外秘なんてないんだし。そうだ、瀞霊廷通信に広告出そうかな」
傍らに置いていたらしい数冊の楽譜集らしき冊子を整えてキーボードに添えると鳳橋は立ち上がり、「ちょっと出てくるね」と吉良の肩を軽く叩いて休憩室の外に出たが、すぐに「忘れ物」と言って廊下から吉良を手招いた。
「何でしょうか?」
「ふふ」
鳳橋は吉良の手を取り引いて彼をも休憩室の外にいざなうと、その頭をそっと抱えて額に口づけを落とす。
「おかえり」
「…………はい、戻りました」
「じゃっ、ボクは行ってきます」
「行ってらっしゃいませ。早めに戻ってきて仕事してくださいね」
「ははは」
「はははじゃなくて」
軽やかに自身から離れ、ひらりと手を振って隊舎を出ていく鳳橋の背をじいと見送っていた吉良は、腰の下から聞こえた「見ていたぞ」の声で再びげんなりしながらそちらを見た。
「上官との関係は良好のようだな。何よりだ」
「どうも。じゃあ、僕は執務室にいるから」
前半をナユラへ、後半を休憩室内の隊士たちへ向けて声を掛けてから吉良は歩き出す。後ろをナユラの足音がついてきたが、彼は振り返らなかった。
「身体はずいぶん馴染んだのか。放熱処理に課題があったと聞いているが」
「…………」
「吉良イヅル、答えねばこのままついて行くぞ?」
「そう。茶菓子くらいは出すよ」
「ほう?」
「君に処理してもらわないと腐らせてしまう」
「私は残飯処理か」
呵呵とナユラは笑って、辿り着いた副官室に吉良に続いて入室する。促される前に応接用であろうソファに腰を下ろすと、ぐるりと室内を見回した。
戸が閉ざされると、あれだけ賑やかだった隊舎内とは隔絶された、ずいぶん静かな空間のように彼女は思った。だが、吉良が窓を開けた途端に中庭から室内に流れ込んでくる旋律とも言えないような音がある。先ほどの鍵盤楽器だろうか? それとも別の? 窓際に立つ吉良の後頭部は、ナユラからはその表情は見えないが、音のするほうを見下ろしているような気がした。
「何か飲むかい」
吉良が不意にそう言って振り返った。逆光のなかに僅かに光る彼の右眼に映ったナユラは思わず背筋を伸ばし、「何とは」と返す。
「いろいろあるんだ。鳳橋隊長が現世からの伝手で仕入れたものとかね。君が口にしたことのないものもあると思うよ」
「見せてくれ」
戸棚からたくさんの紙袋が出され、卓のうえに並べられる。「こっちのまとまりがコーヒー、こっちが紅茶。いくつも色の違う袋があるのは種類で味が違うから。緑茶……はいいか。こっちは焙じ茶。ココアというのもあったんだけど今は切らしている。甘いから好き嫌いは分かれるだろうね」色とりどりの紙袋をひとつひとつ示していく吉良の指先は黒い。
「どれも美味しいは美味しいよ。好みだけだ。選んでいる間に湯を沸かしてくるから」
吉良がさっさと出て行きシンとなった執務室には、遠くから、先程と変わらない楽器が奏でる旋律にもならないような音ひとつぶひとつぶが届く。ナユラが触れるたび紙袋もまたカサカサと音を立てた。
――どれも良さそうに見える。
どれも理解できなくて良くない、よりはマシな感情を持てた。ナユラはそのことにほっとする。吉良自身はナユラのそのような情動にかけらも興味を示さないだろう。ただナユラが、気にしたいだけなのだ。
程なく吉良は湯の入った茶瓶を片手に戻ってきた。
「決まったかい」
「難しいな。どれも美味いのだろう」
「そうだね」
薄く吉良の口の端が上がる。ナユラはそれを見て、「お前の勧めるものを」と口にしていた。
「…………隊長はコーヒーや紅茶を嗜むけど」
「それらは次に取っておこう。お前は?」
「次……」
吉良は億劫さを隠しもせず、焙じ茶の茶葉が入った紙袋を手に取った。「……これかな」根負けしたふうのその様子を見てナユラはぱっと笑った。
“腐らせてしまう”はずだった茶菓子と焙じ茶を堪能するナユラを放って、吉良は執務机に着いて仕事を始める。吉良は驚くほど作業に音を立てず、そちらに目を向けていなければ彼がそこにいないかもしれないとすらナユラは感じた。自身の立てる音と、窓の向こうから流れ込んでくる旋律にもならない音がこの部屋に満ちるすべてのような、そんな心地さえする。
だがそのとき、不意に吉良が顔を上げた。
「――イヅル、入ってもいいかな?」
「どうぞ」
直後に廊下から聞こえてきたのは鳳橋の声であった。あっさりとしたやり取りを交わして彼が入室し、それに合わせて吉良も立ち上がる。
「何か飲まれますか」
「ああ、いいよ、自分でやる。広告載せてくれるってさ」
鳳橋曰く“ピースサイン”を見せた彼は、慣れた足取りでソファのナユラの隣に腰掛けると卓上の紙袋群を吟味し始めた。
「それはいいのですが、広告料はどうなさったのですか?」
「ご心配なく。ボクのポケットマネーさ」
「ぽ……?」
「真似?」
ほとんど同時に訝しげな声を上げる吉良とナユラに鳳橋は笑った。
「ごめん。ボクのお金で出したよってこと」
「なるほど、私費ですか」
「それも現世の言葉か? いずれ現世で使われる用語をまとめた辞書の編纂をせねばなるまいな」
ごく真剣にそう口にするナユラを見つつ、吉良は改めて椅子に腰を下ろす。
「檜佐木くんから伝言。『どこに行っててもいいが締め切りは守れ』だってさ」
「隊長も音楽談話の寄稿、始められたじゃないですか。大丈夫なんですか?」
「もう提出したよ」
「こちらの書類はまだなのに?」
「うわあ、引っ掛けだ」
ひどいな、などと思ってもいないようなやわらかな表情で、鳳橋は勝手知ったるとばかりに戸棚から湯呑みを出して湯を注ぎ、紅茶のティーバッグを浸す。ナユラはその動きをつぶさに見ながら、交わされる二人の会話に黙って耳を傾けた。
小気味良い。
「……そろそろお暇しよう。馳走になった」
「ああ。こちらこそありがとう。送るよ」
「いや、構わない」
「そうはいかないよね。イヅル、ボクも一緒に行こう」
ナユラがソファから立つと、吉良と鳳橋も揃って立ち上がる。ナユラは急に意固地な気持ちになって眉根を寄せた。
「ここまで一人で来たのだ。一人で戻る」
「そうじゃないよ、隊舎の玄関まで」
“君は客人だから”。
言外に吉良のそんな言葉が聞こえたような気がして、不意を突かれてしまったナユラは切なく頷いていた。
受け容れられたかったのだろうか、ここに。
二人と連れ立って近く遠く音楽の響く隊舎の廊下を行くと、すれ違う隊士たちが挨拶の声を掛けてくる。皆、表情に暗さは見られない。こうした朗らかさはいつも、どこにもあったのだろうか。いつも――あの多くの人々が傷ついた、たくさんの戦いを経る以前にも。
そうなら、それを知らないことこそが死神と“我々”の断絶なのかもしれないとナユラは思う。
何もすべてを分かち合いたいわけではない。相手のすべてを理解したいなどと烏滸がましいことを口にしたくはない。そんなことで廻るようなシステムに世界はなっていない。
ただ、つい先ほど目にしたような、鳳橋から吉良に渡されたあの口づけのような、いたわりの存在を実感したい。
隊舎の玄関に着き、土間に立って振り返ったナユラを、上り框で二人が見送る。
「またいつでもおいで」
鳳橋がさも当たり前のように軽やかに両手を振ってそう言うので、ナユラは彼の高いところにある面を見返して神妙に頷き、それから吉良を見た。僅かに鳳橋の後ろに立っている吉良はナユラを見返し、目を眇める。ため息をつけない代わりの表情のようにも見えた。
「……息抜きになるだろうし……キーボードはいつでもそこにあるから」
「――お前は?」
ナユラは、自分の声が震えていないことを願った。
「僕がいようといまいと、君はここに来ればいい」
――ぱちん、と。
目の前で光がまたたいた。
「柿のシーズンには干し柿作るからね、楽しみにおいでよ」
「はあー……」
にこにこと機嫌のいい鳳橋の言葉に吉良は今度こそわかりやすく嘆息し、そういうことだから、とナユラに向けて言った。ナユラは頷いた――二人の表情の眩しさに、目を細めながら。
「では、またな」
「気をつけてお帰り」
「…………いろいろと無理せずにね」
二人に見送られ、手を振ってナユラは三番隊舎を出る。
“君はここに来ればいい”。
“またいつでもおいで”。
その言葉が、どれほどナユラの心をぬくめたか、きっと二人は知らないだろう。吉良の温度のない、無感動な声がどれほど他意なく響いたか。腐らせる前にと振る舞われた茶菓子がどれほど美味かったか。鳳橋の衒いのない、満遍のない言葉がどれほど気遣いに満ちていたか。
いたわりがいたわりの形をしていないとき、ナユラはそこに無為を見た。大霊書回廊に納められた膨大な蔵書にすら綴じられていないその質感が、ナユラを緩やかさで以て拒絶し、受容する。人と人との関係性とは、時にこのようなものではなかったか。
そうだ。時に人は意図せず勝手に救われる。
吉良イヅル、お前もいつかそうだったのだろう?
少しばかり歩を進めてから、ナユラは今一度、音楽の聴こえてくる三番隊舎を振り返り、また前を向いた。明日にでも再び足を運びたい騒ついた気持ちをどうにか宥めて、彼女は一人、帰路を行く。目を逸らすことのできない自身の為すべき責務、その繁忙と、それをこなした先にきっと聴こえてくるであろう、窓の向こうから流れてくる旋律にもならないような音を、思い浮かべながら。
2.檜佐木修兵
「オラァ! いるか吉良ァ!」
「あ、檜佐木さん。ちょうど今電書送りましたので。確認してください」
蹴破らんばかりの勢いで三番隊舎副官室の戸を開け放った檜佐木は、ちょうどその瞬間に都合が良いと言うように部屋の主人から掛けられた言葉でたたらを踏んだ。すぐに檜佐木が腰に提げた伝令神機が通知音を鳴らす。
「何……」
「それでいいか、お手隙の際に確認お願いします」
「いや……今見る」
応接用の長椅子にどかりと腰を下ろし、檜佐木はじっと食い入るように伝令神機の画面を見た。部屋の主人――吉良はぱちりと瞬く。そんな態度を取られるとは思ってもいなかったが、特に咎めることもない。檜佐木が微動だにせずに提出した原稿に目を通している間、吉良は変わらず事務作業を進めることにした。
しばらく経ってから、ふうと檜佐木はひとつ嘆息して顔を上げた。
「大丈夫でしたか?」
吉良としては原稿として体裁が整っているかを確認したい意図があったが、檜佐木は神妙な顔つきで、
「正直に言うぞ。すごくいい文章だ」
とのたまった。
「えっ、あ、ああ。ありがとうございます」
「文章量がいつもの連載より多いが、実は今号は他との兼ね合いであと二頁増やしたかったんだ。ちょうどいい。内容は申し分ない。明快でわかりやすいし随筆として優れていると思う。九番に戻ってから精査はするが特に校閲も必要ないだろう」
ここまで檜佐木が吉良の“文章”を褒めることがないため、かえって吉良は気恥ずかしく感じてしまう。
「すごい。ベタ褒めですね、珍しい」
「一点、気になるのが」
「はい?」
「書き出しの一文がこうだとすると、署名がないのは意図的か? これは匿名として載せたほうがいいのか」
「ああ……」
檜佐木の問い掛けに吉良は逡巡する。
【これは護廷十三隊某隊に所属する無名の一死神の手による拙文である。】
という一文から始まるこの随筆は、筆者の遠方への旅路と折々の思索、日常への内省が交錯して描かれている掌編だ。全体として――筆者の気質をそのまま反映したように――陰鬱な雰囲気を基調としてはいるが、使用されている単語に難しいものはなく、文章そのものは簡潔で明快、檜佐木としては「読みやすい」という評を下したいところである。
「匿名でもいいだろうが、俺にはすぐにお前の文章だってわかるから何とも言いづらい」
「檜佐木さんは編集兼任だしそれはそうでしょう。僕の連載なんか真面目に読んでいる人いませんよ」
「たまに手紙来てるの渡してるだろ」
「ええ、句評回で引用させてもらっています」
吉良の連載への反応として送られてくる手紙の内容は事実、送り手が詠んだ句作の講評を求められていることがほとんどだった。そのどれもが瀞霊廷に存在する句会に所属している者の手によるものではないことは特筆すべき点であり、吉良としては連載の内容に困らないので助かっている節はあるが、檜佐木は不満げな様子である。
「一旦誰かに読ませてバレたら記名にするか……? 雛森以外」
「なんでそこで雛森くんなんですか」
「あいつはお前の連載ちゃんと読んでるから」
「…………」
言葉を返せなくて、吉良はただため息だけを吐いた。彼の様子を顧みることもなく、檜佐木は一人「でもなあ……」と頭を捻らせて悩んでいる。
「あーまあでも……んあー」
「ずいぶん悩みますね。僕としては、この手の内容を副官級が書いて発表したところで白々しさが残るので、匿名でお願いしたいですが」
「一理あるがバレたときの反動もデカいんじゃねえか? それに階級の別なく共感できるところもあると思うぜ」
「うーん」
今度は吉良が檜佐木の言うことに得心する番だった。
これまで連載に執筆していた内容とは明確に違う文章をしたためたのは、内奥から湧いてきたからというのがひとつあった。だからこそごくごく個人的で内省的な文章になったことは吉良自身も十分に理解している。だが同時に「これが自分である」と声高にのたまうことも吉良にはどうしても憚られた。それゆえ無名の死神の随想という形でこの文章を著したのだ。
「……いえ、すみません。やはり匿名でお願いします」
申し訳なさそうな吉良の言葉に、檜佐木は両膝をぱしんと打って立ち上がる。
「わーかったよ。別に無理して記名にしろとは思ってない」
「ありがとうございます」
「今回はこれで勘弁してやるが次の通常連載の原稿も締め切り忘れんなよ」
「はーい」
「最初に読めて嬉しかった」
にっと彼らしい頼りがいのある笑みを見せて、じゃあなと檜佐木は執務室を出ていく。ぽかんとしていた吉良はそのうち、はあ、と長く嘆息した。
彼に通信を送るまで、吉良が長い時間悩み迷っていたことを、檜佐木は知る由もない。
◇
瀞霊廷通信最新号の評判を、余暇を相変わらず趣味の辺境警備に充てる吉良が知るのは瀞霊廷への帰着後になるだろう。
ところで鳳橋が吉良に初めて出会ってからというもの、彼曰くインスピレーションがとどまるところを知らず、吉良が瀞霊廷通信に連載を持っていると知るやその初回が掲載されている号からすべてのバックナンバーを取り寄せたことを知っているのは、おそらくそれを依頼された檜佐木のみである。吉良が過去に出した二冊の句集については――世のなかに書籍の形で存在するほとんどのそれと同様――句友に配布するためだけに刷られた小部数の自費出版だったために檜佐木は黙っていたが、存在が突き止められるのも時間の問題なのでは? と予感してもいる。
――という思索に耽る原因となったのは、あるとき三番隊舎に出向いて帰ってきた六車が珍しく瀞霊廷通信に目を通しているのを見かけたからであった。
「隊長! もしかして!」
「ちげえよ。ローズの奴がやけに興奮してたから」
ついに編集の仕事に興味が!? と嬉々として呼びかけた檜佐木を一蹴し、六車はある頁を開いて眉をぎゅっと寄せた。
「…………俺には合わねえ」
「何スか?」
「『読むたびに涙が溢れてしまう』ってよ。申し分ねえ感想じゃねえか、よかったな」
そうして六車が檜佐木に見せたのは、“ある無名隊士の随想”の頁であった。
――もうバレたのか?
檜佐木はすぐにそう考えた。かつて瀞霊廷通信のバックナンバーを大量に取り寄せた鳳橋のことだ。吉良の文章の特徴を熟知していてもおかしくはない。
ちなみに、雛森にはすぐにバレた。瀞霊廷通信最新号の発行が吉良の外出直後だったこともあって、雛森は檜佐木と阿散井、そして伊勢に彼女の感想を共有することにしたようだった。伊勢もまた雛森の言を受けて「言われてみれば確かに」と彼女自身の洞察力で納得してみせ、程なく檜佐木は松本にまで「これ吉良でしょ? 何わざわざ秘密にしてんのよ」と言われている。吉良の意図に反して、同格で付き合いの多い相手には即座に“無名隊士”の正体は明るみに出てしまったというわけだ。
――みんなちゃんと読んでんだよ、ざまあみろ。
檜佐木は内心で悪態をつき、吉良が帰ってきたら何と言ってやろうかと得意になっていた。
しかし、鳳橋については考慮の外だった。
「……鳳橋隊長、他に何か言ってましたか?」
「あ? 『この万民には絶対にウケないような文章が本当に好き』とか言ってたぜ。誰が書いたかは知らんが、まああいつにハマるもんが俺にハマらねえのはわかってたな」
褒め言葉……なのだろう。万民に“ウケる”ような文章がこの世に存在しないことは自明である。自分が思いをかけるものを素直にそれと表明することに躊躇いも恥じらいもない鳳橋のような存在は、吉良の周囲にはこれまでいなかったな、と檜佐木は長い付き合いのなかで思う。
以前、それとなく気にして、瀞霊廷通信の特集の一環として吉良と雛森に新しい隊長たちの印象を訊ねてみたことがある。当時はまだ復職からそこまで時間が経っていないにしろどちらも悪くない様子だったが、現在はどうか。
――ああ、いつまで経っても先輩後輩の感覚が抜け切らねえな。
自身を内省しつつ、ありがとうございます、と返して檜佐木は隊首室を辞去した。
次号の編集会議のための準備に取り掛かろうと編集室に向かうと、編集部の一人から「編集長の机に手紙置いてますんで」と声を掛けられた。
「ん? 何の」
「編集長が持ってきた匿名寄稿の方宛ですよ」
「……誰から?」
「えっと、どの隊とは聞いてないけどうちではなさそうな、多分一般隊士ですね。若い子だったな」
「……ふうん。ありがとな」
席に着き、確かに卓上に置いてある一通の封書の外側を手に取って眺める。宛名もなければ送り主も書いていない、言伝がなければ開けて中身を検めてしまっていただろう。預かった隊士の在室中に戻って来れたことは幸運だった。
内容に察しなどつかない。あの随想を読んだ何者かが得る感慨に、檜佐木が勝手な想像で踏み込んでいいわけがないのだ。
伝令神機を取り出し、吉良宛てに[さっさと帰ってこい]とだけ送って卓上に置く。彼がこの程度で自分のペースを崩すとは思わないが、檜佐木の思惑を伝えることだって無駄ではないはずだ。
無名の一死神である“私”は、何も起こらない遠方への旅路に過去を追想する。学院生の時分に護廷十三隊に命を救われ、立派な死神に憧れ、入隊してからは隊務に励み、慕っていた上官を“大戦”で亡くす。
少なくない者が似たような道を辿ってきただろう。いずれの“大戦”でさえ、多くの者に多くを失わせた。だからこそこの随想は凡庸さを欠くことがなかった。“私”の、自分自身を躊躇いなく卑下する陰鬱さでさえ少なくない者が持ち得、共鳴され得たはずだ。
“私”は立ち直りつつある尸魂界で復興の一端を担いながら、しかし、時折孤独に自らを馴染ませていた。“私”は辿り着いた先の果てで独り、地べたに坐り込む。ここにいて身を包む“孤独”は、瀞霊廷で仲間に囲まれていながら感じる“孤独”とはまるで質が異なっていることに“私”は気づく。“私”は膝を抱え、茫然と世界の端を眺める。【待ち人は来ない。】“私”はついぞ立ち上がれないまま、随想はそこで終わる。
檜佐木は思う。孤独であることも、立ち上がれずにいることも否定しなかったこの随想を必要としている者は、必ずどこかにいるのだろう。胸に空いた孔を塞ぐこともできず、だからといって虚になることもできない、生きているのか死んでいるのかもわからない、境界を揺蕩うしかない“私”は、しかし、膝を抱えてここにいる。
ここにいるのだ。
ここにいるのだと、“私”が小さく発したその声が、同じような“孤独”に触れて静かに反響する。手を取り合うではない。群れるではない。お互いがそこにいて、無価値だろうと、無意味だろうと、生きているのか死んでいるのかもわからないまま、ただ、在る。そのことに気づく。
【私が待っていたのはあなたではない。】
【あなたが待っていたのも私ではない。】
【でも、私は、あなたがそこにいてくれて嬉しいと思う。】
ぼんやりしていた檜佐木の耳に、伝令神機から通知を知らせる音が響く。不意打ちに驚いてガタリと椅子を鳴らしてしまったことを気恥ずかしく思いながら確認すれば、吉良からの返信だった。
[何かありましたか?]
[これから帰ります。]
簡素な一文に檜佐木はふと息を吐いた。こう返ってきたということは、言うことに違わず程なく吉良は帰着するのだろう。
「言ってみるもんだ」
伸びをして、檜佐木は呟く。
思えば、昔から何か反応をすればその分だけ返してくるやつなのだ。彼は期待されていることに気づかないまま期待に応える。そんなものは期待ではないとないがしろにする態度で、背負ってみせる。
自分に向けられた言葉ではないのにそれでも容易く響くのは、その孔の存在ゆえなのだろう。檜佐木の胸にもそれはある。
――決して埋まることのない、愛おしい虚が。
檜佐木は卓上の封書をそっと撫ぜる。
「…………」
それでいいんだと、誰も言っていないのに聞こえた気がした。
3.阿散井恋次
吉良が四番隊に務めていたころ、何かあると阿散井は彼の許を訪ねて怪我を治してもらっていた。あまりに頻回であると隊長である卯ノ花に見咎められるので次第に“こっそり”になってはいたが、恐らくだが卯ノ花はそれも把握していたのかもしれない。
吉良も吉良で、頼まれれば嫌々言いながらも断らないうえ自身の回道技術向上のために練習相手にできるのは都合がよかったらしい。持ちつ持たれつの関係だった。
そのうちに檜佐木も吉良に治療を頼るようになった。真央霊術院の先輩後輩という立場ではあったが、吉良と阿散井、もう一人の同期である雛森は、護廷十三隊入隊後も檜佐木との友人関係が続いており、互いに切磋琢磨し合う間柄になっていた。
「朽木さんとは、どう?」
その日も、腕の傷に治療を施しながら吉良が訊ねると、阿散井は口許を一層への字に曲げて「……さあ」と返した。
「話せてない?」
「……話すこともねえし」
「そっか」
次第に腕を包み込む光が小さくなっていき、「よし」と吉良が言うとそれは静かに消滅した。阿散井は目を細め、治療痕の残らない腕を見つめる。
「……うし、ありがとな」
「いーえ。だんだん治療にかかる時間、短くなってるよね? 僕」
「なってんな。お前このまま四番隊でいくの?」
ぐるりと肩を回して立ち上がった阿散井に問われ、吉良もまた「まさか」と首を振って立ち上がる。
「回道は何かあったときに役立つからね。まあ、ないとは思うけど、市丸隊長がお怪我をされたときとか……」
「ははは、なさそー」
二人は連れ立ってこっそり使用していた救護室を出、四番隊舎の休憩室に向かう。
「いつかは市丸隊長のところに異動願を出すけど、しばらくは武者修行だね」
めいめい茶を汲み、窓辺の卓に着き二人してだらだらと姿勢を崩して過ごす。吉良の言に阿散井は心底呆れたような表情で頬杖をついた。
「好きだな、ほんと」
「僕なんかより三番隊って市丸隊長大好きな方多いんだよ。時々出向とか遠征で一緒になるんだけど」
「怖……」
「だから、冬はちょっと居づらいんだ……」
「何、なんで季節限定」
「……市丸隊長、干し柿がお好きらしくて……三番の中庭に柿の木あるでしょ? あれ市丸隊長が植えられたんだって。それで、お裾分けしてくれるんだけど……うん」
阿散井は何度か足を運んだことのある三番隊舎の中庭を思い浮かべた。確かに、何か象徴のようにその中心に一本、立派な柿の木がある。柿は育つのに時間がかかるというが、あれほどの枝ぶりなのは一体いつごろからあったのだろう。
それと同時に、目の前でぐずり出した同期が腹を壊すからという理由で干し柿を避けていたことも阿散井は思い出す。
「もっと力をつけて上位席官になればアレ回避できるはずだから」
「努力が後ろ向きすぎねえか?」
「こんなくらいの努力ならいくらでもする」
顎を卓につけて己を見上げてくる吉良に阿散井は瞬く。阿散井にとってもその言葉は、腹の底に降り積もって重なっているものだったから。
「……ばかだなー」
「お互いにね」
くしゃりと目を瞑って吉良は笑い、体を起こすとぐいと茶を飲み干す。阿散井もそれに倣い、んじゃ行くわ、ありがとな、と重ねて礼を述べて四番隊舎を後にした。
◇
「俺、いっこ、覚えてることがあってさ」
檜佐木がそんな切り出しで話し始めるのを阿散井は耳にした。なんとなく、飲みに行こう、と吉良と雛森に声をかけると、松本が現れ、檜佐木も誘おうとなって集まったのである。
阿散井の隣で吉良が「ん?」と相槌を打っている。
「吉良、お前がまだ四番隊にいたころ。俺とこいつで鍛錬してたらやり過ぎてお互いちょっと血が出てさ、治してもらいに行ったじゃん」
「あー、はいはい」
「え……僕それ覚えてないです」
檜佐木の言うことに思い当たる節があるために相槌を打つ阿散井とは違い、いまいちわかっていないらしい吉良の言葉だったが、檜佐木は「本当かよ」とさほど重要そうでもなく返す。
「治療終わって駄弁ってたら、どっかの隊士が訪ねてきたんだよ。んで、花――花だよ。花束、結構きれいな。それも覚えてる理由のひとつなんだが。花束をこう、お前に差し出して『以前は君のおかげで助かった。ありがとう』つってさ」
「へー、なんだか素敵だね」
雛森が言うのに吉良は小首を傾げて苦笑している。
「まあ俺もびっくりしてさあ。結構図体のデカい男がもじもじして恥ずかしそうにしてるもんだから。んで吉良よ。お前は『いいですよ、そんなに気を遣わなくて』つって、まあでも、断りはしなかったな」
「しないでしょうね……さすがに花束は」
生花でしょうしなおさら、と続ける吉良に、「そういう問題?」と松本が呆れたように返した。
「そうだろうけどよ、まあお前に受け取ってもらえたもんだから相手は嬉しくなったんだろ、『よかったら礼をしたいから飯に行かないか』つって。今だから言うけどアレ多分本気でお前のこと口説く気だったと思うんだよ。俺とこいつもいんのに」
親指で示された阿散井がよく覚えていると言うように何度も頷き、吉良は相変わらず首を傾げている。
「さすがにそれには乗ってないですよね?」
「乗ってて忘れてたら薄情すぎるな。乗ってねえよ。てか、答える前にあいつが来たんだ」
「あいつ?」
「市丸」
吉良と松本が思わず目を合わせるのを阿散井は見た。
二人は、そう、時折と言うには頻繁に、酒を交えて二人に共通の思い出に花を咲かせることがある。一緒に墓参りに行ったり、酒を飲んで吉良が吐いたりしながら、それでも以前よりはずいぶんと楽しそうにするようになった。
「あのころはもう三番隊隊長でさ、なのにふらっと四番隊に来て、『救護室の私物化は感心せんなァ』とか言うわけ」
「修兵、今のちょっと似てたわよ」
「お、そうですか?」
軽いやり取りと起こる笑いに酩酊が深まっていることが察せられる。吉良にさり気なく目線を向けた阿散井だったが、さほど気にしたふうでもなく困ったように浮かべる笑みは変わっておらず、その内心を量ることはできない。
――あんときのこいつはあんなにわかりやすかったのに。
「でまあデカい隊士はあいつに睨まれて萎縮しちゃって『すみませんでした』とか言ってさっさと帰っちゃって……」
「ああ! 思い出しました。四番隊のころ、治療の礼に花をいただいたので両親の墓に供えようと思ったら、市丸隊長が一緒について来てくださったんです」
吉良はようやくと記憶の底からそれを掘り返したらしかった。阿散井は、当時の記憶のなかで唯一不明瞭だった問いに急に答えを出され、思わず「あ、やっぱあんとき一緒行ったのか」と口を挟む。
「うん」
「へえ。あいつらしくない……らしい? らしかったのかしら」
「どうだったんですかね」
松本と吉良の些細なやり取りは多分に皮肉を含んでいるようにも阿散井には思われた。
「モテてないわけじゃあないんだよな、お前」
「ギンに邪魔されてたってわけね」
檜佐木と松本の言を受けて酒席に笑い声が満ち、和やかな空気が流れる。
「偶然でしょうし、救護室の私物化を咎められたんですよ。礼品だって当時の同僚たちも時折同じようにもらっていたし。もちろん大っぴらではなかったですが……僕はその一回きりじゃないかな」
「そこそこ四番にいただろ、お前」
「でももうそれきり覚えてないですね」
吉良本人は無感動な様子で小鉢をつついているが、対面で松本と雛森は「もしかしたらギンが手回してたりして」「今の流れだとありえなくないですよね」などと会話している。それを小耳に挟みながら、阿散井もまたその線が濃厚なように思った。
市丸ギンが吉良をよく引き連れていた姿を今でも思い出す。
――お前、そんなに陰気だったかよ。
市丸の後ろに静かに控える吉良を見ながら、くしゃりと笑う彼のいとけない表情をいつまでも覚えている阿散井は、ずっとそんなふうにもどかしく感じていたのだ。
「――そのとき、言われたんですよね」
「何?」
ぼそりと呟かれた言葉にまず松本が反応した。吉良は卓上の料理にぼんやりと目を落として、
「『参る墓があるキミは幸運やね』って」
と続け、そうして顔を上げると真っ直ぐに対面に坐っている松本を見た。
「なので、松本さんが市丸隊長のお墓を建ててくれて、僕は幸運でした」
「…………」
松本がおもむろに立ち上がり、その両手の指を“わきわき”させて吉良ににじり寄る。吉良も慌てて立ち上がると阿散井を挟んで隣にいた檜佐木の傍に回って抱きつくように隠れた。
「何よ、ハグくらいさせてよ!」
「嫌ですよ!」
「じゃあ乱菊さんの代わりに俺がしときます」
「何で!!」
隠れ蓑にしていたはずの檜佐木に酩酊のまま抱きしめられ、吉良は喚く。その様子を雛森と笑いながら眺めていられることに阿散井はほっとするのだった。
「そういえば朽木さんとはどう?」
宴が終わり、夜の闇が優しく落ちる道を、松本、檜佐木と別れ、久しぶりに同期三人で並んで歩いた。雛森に訊ねられ、阿散井は頭を掻いて、「……そこまで悪くはない」と返す。なんだかそう答えるだけで気恥ずかしかった。案の定、吉良と雛森は嬉しそうに笑っている。酒精で上気した頬が、そのまま夜の空気のなかで喜びの色をしているように見えた。
「おめーらはどうなんだよ、新しい隊長たち」
「……平子隊長はすごくいい人だよ。私のこと、待っててくれてる」
お仕事ちゃんとしてくれればもっといい人だけど、と雛森は眉を下げて困ったように微笑んだ。阿散井は吉良と視線を交わす。
――傷ついた人に「立ち直れ」なんて、そんな簡単に言えないよ。
自分だって傷ついたのに、吉良はそう言った。かつて互いの間にあった蟠りが解けたとはいえ、根本にある痛みがそれで寛解することはない。だが彼の場合は、しょっちゅう飲みたがる松本や、最近知り合いになったらしい阿散井は名も知らぬどこかの少女、職務中だろうと構わず楽器をとことん弾きたがる上官に囲まれて、傷があることを意識の外に置く生活を過ごしているせいか、“まだマシ”に見える。
だから、阿散井も吉良も、殊更に雛森を構ってしまう。
「でもね、私、意外と大丈夫なんだなあって思えるようになったよ」
「ふうん?」
「吉良くんから新しく俳句の本出そうか考えてるって話もらってから、練習しなくちゃって思って久しぶりに絵を描くようになったの」
「ああ」
「へえ、そうなのか」
阿散井が吉良に声をかけると彼はどこか照れくさそうに頷いた。
「まだ先だけどね……話は通しておこうと思って」
「ありがとう、吉良くん」
「ううん。こちらこそいつもありがとう」
「私も、自分の絵をまとめた本を出したいなって思い始めて。自分用にだけど……」
「えっと……僕も買いたいな、それ」
「あ、俺も」
「ほ、ほんと?」
今度は酒精のためだけでなく顔を赤くした雛森が慌てたように両手を中空で“わさわさ”動かしている。それが可笑しくて笑っているうちに、五番隊舎に到着していた。
「じゃあ、おやすみ、二人とも」
去っていく雛森に手を振って、二人は再び歩き出す。程なく、阿散井はずっと気になっていたことを口にした。
「……お前、雛森のこともういいの?」
「ん? ……うーん」
狼狽えるかと思いきや、吉良は存外冷めた表情で、僅かに目線を逸らすのみだった。
「……好きだよ。けど、同じ好きを阿散井くんにも感じてるって、最近は思う」
「…………ほーん?」
吉良が立ち止まるのに合わせて阿散井も立ち止まる。隊舎と隊舎の間にある共用の広場にはちらほらと人気があったが、通路脇に設られた長椅子に人影はなく、二人はどちらともなく腰を下ろした。
「雛森くんも、阿散井くんも……檜佐木さんも、松本さんも……市丸隊長も、僕を振り返ることはないから……僕にはそれがよかったのかも。あ、でも、気を悪くさせたいわけじゃなくて」
「わかってるよ。あんま寂しいこと言うな」
肩を竦めるとほっとしたように吉良は微笑む。懐に入れた相手に対しては無防備なくらいあけすけな態度になる吉良のことを、阿散井だって心配していないわけではない。
「つーかお前、市丸のことまだ“隊長”って呼んでんのか」
「あ、うん。鳳橋隊長が……『呼んでもいいんじゃない?』って言ってくれたんだ。『キミにとっての隊長が何人いてもいいじゃない』って」
吉良は体を屈め、両手で顔の下半分を軽く覆うようにした。その仕草、横顔に兆す照れに阿散井は意外性を見る。
「だから……えっとね」
「?」
「なんていうのか。勘違いかもしれないから……それに、そういう意味じゃないんだろうし……」
「何、どうしたよ」
突然、吉良は整理されていない言葉を口にしては一人、おろおろし始めた。彼のそんな様子を不意に目の当たりにし、可笑しくなった阿散井も前屈みになって膝に頬杖をつき、吉良が――恐らく何か相談したいことがあるのだろうと踏んで、待つ。
「うあー……」
それはずいぶん言いにくいことのようで阿散井は少し焦れるが、夜は長いし幸い二人とも明日は休暇だ。久しぶりにゆっくりするのも悪くはないだろうと思っていた。
だが。
「イヅル!」
低く、しかし明るい声が夜の間を二人に向かって飛んできた。同時に顔を上げた彼らの視界に、三番隊舎の方角から歩いてきたらしい鳳橋が駆け寄ってくる姿が映る。
「阿散井くんもこんばんは。イヅル、何してるんだい?」
「こんばんはっス」
「あ、隊長、いえ、二人で話していました」
「そうか。お邪魔して悪いね」
「いいえ」
ぴゃっと跳ねるように立ち上がり、吉良は襟足を掻きながらもごもごと言う。普段の職務中に見られるような――気ままな鳳橋と厳しい吉良のような――姿ではなくて、それが阿散井には不思議に思えた。
「隊長はこんな時間まで残っていたんですか?」
「あはは、実は作曲が捗って集中し過ぎてね。さっき夜番の子たちに『まだいたんですか、そろそろ帰ってください』って言われてしまったんだ」
鳳橋の笑顔は夜の闇のなかでも朗らかで、初めて会ったときには吉良に似て辛気くさそうだという印象を抱いていた阿散井は内心で謝罪する。
そのとき、鳳橋の隠れていない左目がすい、と細められ、吉良の後ろでおもむろに立ち上がる阿散井を見た。
――あれ?
「あー……俺も帰るわ、吉良」
「え?」
ぱっと振り返った吉良が驚いたように見上げてくるので、阿散井は「また今度、話聞いてやる」と続ける。
一歩下がり、片手をひょいと上げると吉良はコクコクと二度頷いて、「おやすみ」と笑って同じように片手をひらりと上げた。
「おやすみ、阿散井くん」
「っス。鳳橋隊長もお疲れ様です」
ぺこりと頭を下げて六番隊舎に向けて歩き出す。少し離れてからそうっと振り返ると、先ほどまでいた場所にはまだ吉良と鳳橋の影があって、何か話しているように見えた。
鳳橋の手がゆっくりと吉良の側頭部に伸び、慣れた様子で夜の光を反射する彼の金色の髪を梳く。
阿散井は慌てて視線を戻し、少しだけ足を速めた。
――なんか俺、あんときのあいつと一緒じゃねえ?
4.吉良イヅル
句境、俳趣味といったごく個人的で他者に説明し難い感覚は、吉良にとって自分でも飼い慣らすことが困難だ。というよりも、表れた句を取り上げて「なぜこのような句になったのか」「何がこの句を生んだか」と問われて答えることが彼には苦痛だった。“本当の”俳人はそうしたことも含めて表明できて初めてそうと名乗れるのだろうと吉良は思う。彼は、幾分か場の空気に慣れて取り繕うことができるようになった現在でも、内心ではやはりそのような態度を苦手に感じていた。
そうなので吉良本人が句評する立場のときはあまり作者自身に問うことをしない。語りたい者は勝手に語ればよく、語りたくない者は無理に語らずともよい。表れたものが見えるすべてで、そこから吉良自身が感じたように評する。ともすれば野放図にもなり兼ねない、雑と言われても仕方のないやり方ではあったが、『無下にせず、尊重する』という一線を守ることでそれは回避されていた。意図的にというよりは自然とそうなっていた。なぜなら吉良本人が、問われることで自分が尊重されていないと感じていたから。
ただ、幸いなことに、現在彼の所属している句会は全体の雰囲気としてそのあたりに頓着することがなかった。規範はあれど規則を細かく設けることが好きではない現会長の気質により、闊達な空気が醸成されている。旧知の檜佐木、ひいては東仙前九番隊長の依頼で吉良が瀞霊廷通信に俳句を交えた連載を持つことについて相談した折にも、俳句の射程が広がることに喜びを示してくれ、好きにどうぞ、肩書きに句会の名を使っていいから、とのお墨付きを得て、吉良は自由に書くことができるようになったのである。
「イヅル、句集出してるって本当?」
書類への押印を待ちがてら鳳橋に訊ねられたとき、吉良は不意をつかれてすぐに答えることができなかった。執務机に着いて上目遣いにこちらを見てくる相手に、「えっと」と狼狽してしまう。
「な、なぜ……?」
「偶然そんな話になって、真子と。雛森ちゃんが絵を描く子で、キミの連載や句集の挿絵も担当してるんだって聞いたって」
素敵だなって、とにこにこ微笑みながら鳳橋が言うのに吉良はどうにも気恥ずかしくなってしまうが、なんとか「自費出版で、句会の皆さんに差し上げるためのもので、句友の間ではよくあることです」と答えた。事実ではあった。広く一般に発行される書籍とは違い、趣味の範疇に収められる活動の一種であるが、様々な分野で同様にそうした自費出版は行われている。
「えっ。てことは、ボクはそれ読めない……?」
悲しげに眉が寄せられて、吉良の動いていないはずの心臓がぎゅうと軋んだ気がした。読めないわけではもちろんない。吉良の手持ちの分があるからそれを貸し出せばいいだけだ。
だが。
吉良はこんな身体になってなお、自作に対する羞恥心を投げ打つことのできない自分に自分で驚いている。言わずもがな、あらゆる創作は作者の内奥があって初めて世に出される。そうでないものなどこの世にないと言っていいだろう。ましてや鳳橋は“インスピレーション”を大事にする作り手だ。他者の創作に対してもその眼差しで望むことは明らかだった。
見られることが恥ずかしい。
――この人には。
「えっと……」
句友たちや同期たち、作家仲間としての檜佐木に対しては一切抱くことのないその感情が、どうして鳳橋に対してだけは我が物顔で内心を席巻してしまうのか、吉良には疾うにわかっている。
「あ! 無理にとは言わないよ。ごめんごめん」
「いえ、こちらこそすみません。少し、その、気恥ずかしくて。隊長も分野は違えど作り手の方ですから」
「そっか。じゃあいつか、ボクに見せても平気だなって思えたら、見せてくれたら嬉しいな。ボクはイヅルの文章も好きだからね」
ぺこりと頭を下げ、吉良は隊首室を辞去する。焦っている内心が悟られていなければいいのに、と願う。
鳳橋はいつも吉良を手を振って見送ってくれる。別に戸を閉めていかなくてもいいよ、と言う鳳橋に従って、戸は開け放したままだ。開いていたいのだという。誰でも入ってきやすいように。
『防音設備もないですしね』
『そこは一切考慮に入れてないね!』
吉良の嫌味にもあっけらかんと返す度量の深さは、そのとき偶然同席していた複数名の新任の席官を狼狽えさせ、同時に呆れさせた。
吉良の室の戸はそうはいかない。誰でも入ってきやすいように開けることが、吉良にはどうしてもできない。
◇
大勢のなかの一人だ。誰にとっても。
自身が換えの効く存在であることを、吉良はさほど気に病んだことはない。護廷十三隊に死神として所属しているならむしろそうあるべきで、そうでなければ組織は立ち行かない。誰もが欠けて困る存在であってはならない。
――誰にとっても重きを置かれない。それはある意味で気楽でもあった。責任がない。立ち去っても構われない。自身の軽さに吉良は少しばかり耐性があった。
だが、創作を始めたのは、そしてそれを何らかの手段で公表しようとしたのは、本当はそうではなかったからなのかもしれない。「ここにいるのだ」と声を上げること、それが創作を公表することによって発生する事象のひとつだ。もちろん何らかの事由によって永久に失われることもあるだろう。誰にも見つけられず、誰の目にも止まらぬこともあるだろう。だが、「ここにいるのだ」という事実は消せない。
死神であること、創作して公表すること。
このふたつは吉良にとって少しも差異がない。
――“さほど”気に病まない吉良は、一度だけそのことで涙を溢したことがある。誰にとっても重きを置かれないのに、自分にとって大切な者たちに向ける自分の感情はあまりに重すぎることに気がついたとき。自分の感情が他者に伝わることで、それが他者にとっての重みとなってしまうのではないかと恐れたとき。そして、しかし結局、誰にも伝わることはないのだとわかったとき。
腰に提げた侘助が深呼吸をした気がして、吉良は目を伏せる。
吉良にとって最も“幸運”だったのは、最も憧れた市丸ギンが、彼を少しも顧みることがなかったことだ。
◇
「抱きしめてもいい?」
大戦後、十二番隊の研究所から四番隊の救護詰所に移送されていた上官の容態がようやく小康状態になったとの知らせを受けて、面会のために詰所に足を運んだ吉良に、鳳橋は切なく眉を寄せてそう言った。困ったのは吉良のほうだった。
「半身を露出しているので……体温が高くなっているので、もしかしたらご不快に感じられるかもしれません」
「そうかな。ボクはそうは思わないよ」
譲る気のない鳳橋は腕を広げて吉良の判断を待っている。自分の許可を求められることのほうが吉良には悩ましいことだった。
観念して寄り添うように寝台へ一歩踏み出すと、鳳橋はすかさず腕を回して吉良の身体を抱き寄せた。抉れた孔の引き攣れた縁、鳩尾のあたりに鳳橋の側頭部がそっと触れる。僅かにだが残っている感覚で、掻痒感を覚えた。
抱きしめ返すことが憚られて、吉良の両腕は宙ぶらりんになった。鳳橋はしばらくそうして、ゆっくりと体勢を立て直すと泣き出しそうに眉を下げ、吉良を見上げて笑った。
「キミが、ここにいてくれて、よかった」
――ズシン。
ああ、重い。吉良はそう思った。
こんなことがずっと繰り返されてきた。鳳橋が三番隊隊長に復職し、吉良と共に働き始めてから。
鳳橋は、何度も何度も、吉良を顧みた。
初めは聞き慣れない“インスピレーション”という言葉だった。それは何かと問う吉良に、鳳橋は直感だと答え、続けて、創造の源泉という表現を使った。
『キミを見ているとボクのインスピレーションが刺激されるんだ』
にこりと笑った鳳橋に困惑し、その後ところ構わず職務を放棄して楽器を演奏しだす奇行にも惑乱させられた。次第に慣れてきて、適当にあしらったり厳しい態度を見せたりすることもできるようになったころ――つまり、余裕が出てきたころ。
吉良は、鳳橋から自身に向けられている眼差しの優しさに気がついた。
『イヅル、こんな曲ができたんだけど聴いてくれる?』
『本当に仕事が早いね、頼りになるなあ』
『無理してない? 休憩しようよ、お菓子もらったから。イヅルと一緒に食べようと思って』
『ボクはイヅルのそういうところ、好きだよ』
真っ直ぐに己を見つめてくる鳳橋は、いたわりと慈愛に満ちた彼の心を表に出すことを少しも躊躇わなかった。
『ボクはイヅルが好きだよ』
あたたかさに照らされて、泣きそうになる吉良のことさえ見通して、包み込んでくれているような……。
だが同時に、鳳橋が誰に対してもそのように穏やかに接することを吉良は知っていた。“自分にばかりそうなのではない”と思い直すとき、それは常に己の愚かさや浅ましさを罰する時間でもあった。
今抱きしめられたのは己だけではない。当たり前のように、戸隠や吾里、片倉らの、吉良を構成する魂魄となった仲間たちをも彼は抱擁しただろう。そういうことのできる人だ。
「……どうか、じっくりご静養ください」
吉良は鳳橋からそっと離れて頭を下げた。
「隊長が戻ってこられるまで、隊を立て直してお待ちしております」
「…………イヅル」
鳳橋の大きな手が下げられた吉良の頭部に触れ、遠慮がちに、しかしいたわりを持って静かに髪を梳く。
愛おしいと、言われているように、勘違いしてしまいそうになる。
「無理しないで、みんなを頼ってね。ボクもすぐに帰るから」
「…………」
コクリとひとつだけ頷いて、吉良は救護室を辞去した。廊下に出ると、救護詰所も一頃の忙しなさは過ぎたようで、静かな時間が流れている。
「あ、吉良副隊長」
偶然、勇音と行き合って、吉良は会釈を返した。勇音は少し疲れた様子で吉良に歩み寄ってくる。
「お疲れ様です、虎徹隊長」
「ああ……」
困った様子の彼女は首を傾げる吉良に「まだ慣れません」とごく小さな声で言った。
「私にとっての隊長は、卯ノ花隊長だけなので……」
「……そうですね」
彼女の喪失を吉良は思う。数日前に話を聞いてからまだ彼も実感できないでいることだ。吉良自身も一度は卯ノ花の許で回道を学び、その技を会得していった。時に優しく時に厳しいその佇まいは、どうあれ――表れたものが見えるすべてだった。
お前は失ったのだと突きつけられて初めてその喪失に向き合うことができる。その機会を逸してしまえば、いつまでも不確かな存在に縛られ続けるよりない。
「……鳳橋隊長が以前、市丸隊長を呼びにくそうにしていた僕に、彼のことも隊長と呼べばいいと仰ってくださいました」
吉良が話し始めると、勇音は緩やかに一度瞬きをして、それから微笑むように目を細めた。
「そうですね」
「はい。そうなのだと思います」
「ありがとうございます、吉良副隊長」
頭を下げられ、吉良は首を振って、では、とその場を離れた。
――縛られ続けること、立ち直れないことを肯定したい。
――向き合えなくても、寄り添いたい。
いつしか、吉良に芽生えた思いはそれだった。
◇
吉良の予想に反して、鳳橋の復帰は面会から数日後と非常に早いものだった。大戦で倒壊した三番隊舎の修繕もまだ中途半端だったために、復旧作業の手を止めてもう少し休んでほしかったと嫌味たらしくそのままに伝えれば、鳳橋はふふんと得意げに笑って、「キミだけに背負わせるわけにいかないからね」と腰に手を当ててわざとらしく尊大な態度を取る。似合わなくて思わず笑ってしまった吉良に、鳳橋は今度、まるで愛おしむような笑みを浮かべて、言った。
「ボクにも、背負わせて。イヅル。そのくらいの力ならあるつもりだけど?」
含みのある言葉だった。吉良が何と返していいかわからずに困惑していると、鳳橋は一歩、吉良に歩み寄って、囁くように続けた。
「好きだよ、イヅル。キミの傍にいさせておくれ」
「…………あ、の……」
「ふふ、顔真っ赤でかわいい。珍しいイヅルが見れたな」
からかうように言われて、吉良は慌てて腕で顔を隠す。その仕草に鳳橋はまた笑みを深めた。
「せっかく命を拾ったんだもの、伝えなくちゃってずっと思っていたんだ。よかったら考えてほしい、ボクとのこと」
「……ですが、僕はもう生きていない身です。それにお立場が」
「生きていようと死んでいようと、ボクには目の前にいるキミの命がすべてだよ」
「…………」
「立場は、そうだなあ。キミが寄りかかることのできる相手になれるよう、がんばるね」
「がんばる、って、そんな」
「よし! ボクも運ぶよー!」
惑乱したままの吉良を放って、ガシャガシャと瓦礫のうえを進んで作業を続ける隊士たちの許に鳳橋は歩いていく。一人取り残された吉良が呆然と彼の動向を見つめていると、大きな瓦礫を持ち上げようとした鳳橋がうわあと叫んで振り返った。
「イヅル! これ重いから手伝ってー!」
大きく手を振って己に訴える鳳橋に、吉良は呆気に取られ、吹き出してしまう。
「無理してるのはどっちですか」
可笑しくて小さく呟いた吉良の声は彼には届かず、早く早くと呼び寄せるその手に招かれて、吉良もまた瓦礫のうえを進む。
涅マユリは言っていた。霊圧と共に膂力と頑強さも上がっているはずだと。それなら過日、再会した鳳橋から伝えられた言葉に感じた重みも、これからならば抱えていけるのかもしれない。
傍に辿り着いた吉良に、鳳橋がぱっと晴れやかな笑みを見せる。己よりも高い位置にあるその面を見上げながら、吉良もぎこちなく微笑んだ。
足が竦む。けれど、心が走り出したそうにしている。
どこかへ行ってしまいたい。けれど、この人の傍を居心地よく感じている自分も確かにいる。
――ずっと、勘違いではなかったのかもしれない。まだ、せめぎ合う自分に決着はつかないけれど。
吉良は初めて、他者に対して期待を持って見つめることを自分に許した。
そうして同時に、どれだけ遅くなってもきっとこの人なら待っていてくれるだろうと、信じることにした。
◇
卓上に差し出された二冊の書籍と、差し出してきた相手とを鳳橋は何度も交互に見やる。次第に嫌そうな表情になる相手――吉良が、要らないのなら見せませんよ、と手を引こうとすると、慌てて鳳橋はその手ごと書籍を捉えた。
「よ、読むよ! 本当に見せてくれるの?」
「…………仕方ないですから」
「ありがとう!」
二冊を抱えてふにゃりと笑う鳳橋に、口許をへの字に曲げた吉良はひとつ咳払いをする。
「僕の私物ですので読み終わったら返してくださいね」
「わかった!」
「それと…………」
言いかけて、吉良は口を噤む。鳳橋はその様子に首を傾げたが、彼は「何でもありません」と返した。
「えっ、気になるよ?」
「……まだ秘密です。では。お仕事続けてください? 鳳橋隊長」
「ええ~~、いじわる……」
口を尖らせ、頷くだけは頷いた鳳橋に吉良は口の端を上げてみせる。そのままブーイングを背に受けながら辞去し、副官室に戻る道すがら、彼は自身が小さく鼻歌を歌っていることには気づかなかった。
もうじき、後回しになっていた句集の三冊目を出版する予定のあること。
そのうちいくつかの句の主題が自身であることに鳳橋は果たして気づくだろうかということ。
気づかなかったときにはいつ秘密を明かそうか、気づいたときにはどんなふうに白を切ろうか。
そういう未来を想像するので、心が満たされていたから。