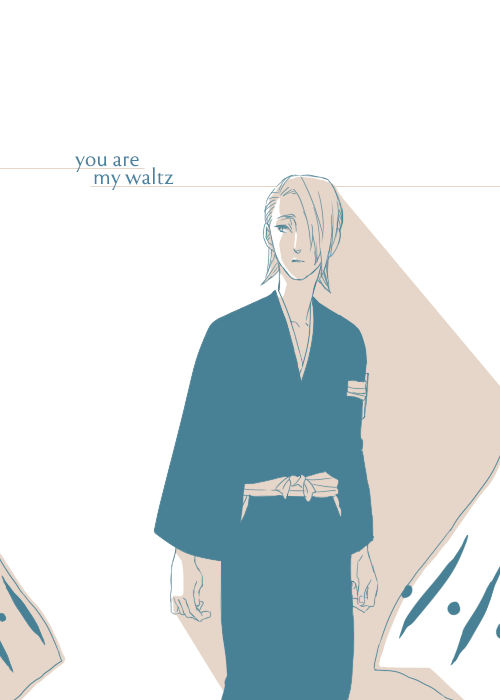「吉良隊長代行、入室のご許可をいただけますか」
低く落ち着いた声が室外から掛かり、一応の部屋の主人ではある吉良は是と答えた。からりと戸を開けたのは片倉飛鳥第六席で、瀞霊廷警邏巡回の報告のために現在は隊長代行執務室となっている副官室を訪れたのである。
室内には戸隠李空第三席の姿もあった。彼自身の執務机を持ち込んで、現在は二人体制で隊長代行業務の作業統括を行なっている形になる。最終責任は吉良が負うが、そこまでの業務はおおむね手分けすることになっていた。吉良の作業量とそれによる過労を見兼ねた戸隠からの申し出であった。
「報告ありがとう。担当隊士たちに休暇の連絡をよろしく」
「はっ、承知しました」
「あ……それと、もし見かけたら吾里五席を呼んでくれるかい」
「なぜ俺があの男を?」
「片倉」
ぴしゃりと戸隠の咎める声が飛んだ。吉良はいつものことだと苦笑するに留める。
上昇志向のあるこの席官は、特にすぐ上の席位である吾里武綱第五席にはどうにも噛みつく様子が日常的に見られていた。吾里の豪放で大らかな性格のために、また実際の作戦業務に於いての連携は恙無く遂行されるために目立った問題に発展したことはないものの、しかし礼節を疎かにすべきではないことも自明である。この点については吉良よりも戸隠のほうが重く見ていた。
「隊長代行のご命令には従うよう」
「いやっ、命令というほどのことではね……」
「もちろんです。吉良隊長代行の仰ることはすべて聞き入れます」
「その姿勢はあまりよくないよ……」
「ただ俺はあれが気に食わないだけです」
正直だなあ……。吉良はそう口には出せないまましみじみと、同期にして素直な性質の赤髪の男を思い出す。
自身の差し挟む口をとことん無視されつつ、吉良にとっての話は一旦そこで終わった――はずであった。
しかし、片倉が執務机の前から一向に去らない。書類業務に戻りかけた吉良が訝って片倉を見ると、彼はじいと吉良を見ていた。
「他に――何か」
重要事案が? 緊張した面持ちで吉良が問うと「いえ」とやや渋い表情で片倉は答え、それから「ひとつお聞き入れいただきたいことが」と続けた。
離隊――
吉良の脳裏によぎったのはそのことであった。
現状、三番隊の統率力は誰が見ても著しく低下していると判断できた。市丸ギンという稀代の統率者を失い、その大半が彼に心酔しているといっても過言ではなかった三番隊は全体として混乱の渦中にある。吉良はそのなかで――隊舎牢勾留期間や中央四十六室による裁判への出廷を経て――隊長代行として務めているために、隊士たちとの意識の乖離や自身の無力さを肌で実感していた。
いつ瓦解してもおかしくはない。いつ離散してもおかしくはない。一秒前まではそうではなかった、一秒後はそうかもしれない。無言のおそれと違和感が、常に隊舎内には漂っていた。
だから、吉良は常に覚悟していた。己のみじめさや至らなさを眼前に突きつけられる瞬間を。引き留める言葉を持たない代わりに、他隊への推薦状は誠心誠意をもってしたためることを。
無意識に彼は唾を飲んでいた。
「――何だろう」
「俺のことを名前で呼んでください」
「…………」
静寂が降りた。
「…………はっ?」
言われた言葉を遅れて理解した吉良の素っ頓狂な声が室内に小さく響く。
「飛鳥です。片倉六席じゃあなくて。今度からそうお呼びください」
さも当然のように得意な顔で片倉はのたまう。笑みを浮かべてぱさりと右目を隠す前髪を払ってみせる仕草がやけに挑発的だった。ぽかんとしている吉良と巻き込まれた戸隠のことなど視界に入っていないかのようだが、しかし彼自身はしっかりと吉良を見据えている。
「市丸隊長は吉良隊長代行のことをお名前でお呼びしていたでしょう。ずるいと思っていたんです」
「ずる……いや、えっと……いや……えっと」
「副隊長、お気持ちはわかります。落ち着いて」
横から戸隠の支援があって吉良はひとつ頷く。そう言う戸隠も吉良を“隊長代行”ではなく思わず“副隊長”と呼ばわってしまっているところに困惑ぶりが窺えた。
「その……申し出はありがたいし、君なりに隊の雰囲気を緩和させようとの考えなのだろうというのはわかるけれど……やはり礼儀は大切だと僕は思う。すまないけれど」
「隊の雰囲気は別に」
「えっ」
吉良が申し訳なさそうに――なぜ自分がこんな気持ちにならねばならないのかという疑問はあったが――断ると、片倉はしれっと建前を崩した。そもそも吉良が勝手に意図を読み違えていただけで、建前などもともとどこにもなかった。驚いた吉良が言葉を失っているのにも構わず片倉は続ける。
「俺があなたを名前で呼べない代わりに、あなたに名前で呼ばれたいだけです」
「あっ……あー……そう……」
もはや、片倉の言うことのすべてが吉良の理解の範疇になかった。
「ああ……いや、今は…………す、すまない」
「いや、構いませんよ。ですがお気が向かれましたらいつでも飛鳥とお呼びください! 俺はいつでも待っていますから」
ばちん! と音がしそうなほど鮮やかに片目を瞑ってみせた片倉が「では!」と軽やかに執務室を辞去する。
唖然としたまま吉良はしばらく戸を見つめていたが、やがて斜め前の戸隠に目を向けた。戸隠も吉良を見ていた。
「よ、よくわからなかったね……」
すっかり参っているらしい吉良が苦笑して場を取り繕うようにそう口にすると、戸隠はふと口許に手を当てて考えるような仕草をした。
「いえ、そういえば以前から、片倉六席はあなたに憧れていたような気がします」
「え?」
真剣な表情から発せられた戸隠の言に吉良はぱちりと瞬く。思ってもみない推察であった。
「まさか」
「『まさか』って、あなたが仰るんですか」
「思い当たる節がない」
「そうですか? 結構わかりやすかったですよ。理由までは聞いたことはありませんが」
「…………」
そうして戸隠は自分だけ先に書類業務に戻った。あらゆる言葉についていけないままの吉良を置いて。
「吉良副隊長、吾里です」
室外からかかったその声に吉良はハッと顔を上げた。入室を許可すると吾里武綱第五席がぬうっと戸を開けて入ってくる。すぐさま戸隠の「吉良“隊長代行”だ」と咎める声が飛んだ。
「あ、すんません」
「いや、構わないよ、そこまで厳密にしなくとも」
「隊長代行はそう仰られるでしょうから私が代わりに訂正するんです」
「……ありがとうね」
しっかり者の補佐役のありがたさが吉良の身に沁みる。
「隊長代行、片倉に何か言いました?」
悠然と執務机の前に立った吾里が唐突にそんなことを言った。吉良は首を傾げる――どちらかといえば、何も言わなかったのほうが正しい。
「や、珍しく機嫌良かったもんで」
「…………」
それは結局、まったく吉良の理解の範疇になかった。
◇
鳳橋楼十郎が三番隊隊長に復帰就任するにあたり、大規模な人事異動が行われることになるだろうという噂は隊舎のあちらこちらでまことしやかに囁かれていたが、その実、空位であった隊長の席に彼が収まったのみですべての席位は現状のまま据え置きとなった。無論、吉良は副隊長に復職し、戸隠も第三席として、副官室にしばらくあった執務机をかつての三席以下執務室に戻す日がようやく来たのであった。
隊長代行業務としての彼らの協働は、現在三番隊の席官位にある隊士たちの鳳橋への紹介が最後になる。そして、三席以下執務室への案内によってそれも完遂されるところとなった。
「うちの隊、改めて見てもやっぱりなかなかいい雰囲気じゃない。キミたちの働きがいいんだろうな」
「僕は何も。戸隠三席以下隊士たち個々の責任感と、市丸前隊長の遺恩の賜物です」
「何もしていないってことはないでしょ……ああ、キミはそういうタイプかあ」
「タイプ……?」
「んー、性質みたいなことかな」
そういう性質。吉良は言われたことを内心で反芻する。
――イヅルはそういう子ォやもんね。
以前、何度か市丸ギンにからかい混じりに言われた言葉が思い出されて、ああ、あの類いの言葉かと得心したところで、吉良のやや後ろから戸隠が声を発した。
「そうですね、そういう“タイプ”です」
「ふふふ、言われてる」
「なっ、何を……」
通じ合っているふうの二人にうろたえている間に、三席以下執務室に到着する。入室して戸隠を除く四席以下を順に紹介し、最後に吉良は片倉を示した。
「彼が片倉飛鳥第六席です」
「飛鳥クンか、よろしくね」
「…………」
「片倉六席?」
鳳橋からの呼びかけに返答をしなかった片倉を吉良は訝る。片倉本人は平然とした表情で立っているだけに、様子がおかしいことには皆が気づいた。
――なぜ。
「片倉六席、どうした」
焦る吉良に、鳳橋は鷹揚に笑う。
「まあ仕方ないか。ボクもこれからがんばるよ」
「いや、あまりに無礼で……」
「吉良副隊長」
不意に戸隠に名を呼ばれそちらを見ると、彼はじっと吉良を見つめていた。その眼差しが何か伝えようとしていることは吉良にも理解できたが、心当たりが――
――ある。あった。あれか?
「…………あ……飛鳥?」
その瞬間の片倉を見た皆が皆、後に一様にこう語る――見えない耳がピンと立ち、見えない尻尾が大きく強く左右に振られたと。
「はいっ、吉良副隊長!」
「……ええと、隊長のお声がけには即座に返答するよう」
「はっ! 無礼をお許しください、鳳橋隊長」
「あはは、許そうかな。ただ理由を訊いてもいい?」
「最初に俺の名を呼んで俺が返事をするのは吉良副隊長のみですので」
しゃあしゃあと高らかに述べる片倉、大笑いする鳳橋。絶句する吉良は、「怖ぇーなコイツ」と肩を竦める吾里に向かって「やかましいぞ唐変木が」と先ほどまでとは打って変わって低音で罵る片倉に、「……つ、次から気をつけて」と訓戒を与える以外に何を言うべきかわからなくなってしまった。
どうにかその場を収め、今後の隊長副隊長間の意思疎通と隊務確認のために鳳橋と共に三席以下執務室を辞去しようとした吉良を引き留め、戸隠は控えめに笑んで言った。
「鳳橋隊長はもちろんですが、吉良副隊長、今後は私のことも李空と気軽にお呼びください」
「…………善処するよ」
「ええ、よろしくお願いします」
一礼し、戸隠はあるべき場所に戻った自身の執務机に着く。それを見届けて、吉良は改めて鳳橋を追って室を辞去した。
「何もしていないなんてなかったじゃない」
吉良の随伴を待っていた鳳橋にからかうような声音で言われ、吉良は眉を下げる。言葉を返せず、歩みは止めない。
「キミは少し自覚的になったほうがいいかもね、あー……イヅル」
吉良は顔を上げた。前を行く鳳橋の羽織の背に大きく書かれた“三”の字が視界に映る。くるりと振り返り、翻った彼の明るい金髪に光が反射した。
「イヅルって呼んでもいい?」
細められた眼差しも、柔らかく垂れた眦も、朗らかに笑う口許も、頬にさす影も、声も、何もかもが“違う”。
“違う”日々が、始まろうとしている。
「……もう呼んだじゃないですか」
「そうだね。でも、これからも」
「……お好きなように」
「イヅルがどうしたいか聞きたいなあ」
「また呼んだ」
「ふふふ」
「……はい。呼んでください」
吉良の答えにぱあっと明るく笑った鳳橋は大きく頷き、止めていた歩みを再開した。吉良もまたそれについて歩いていく。
己の内心に渦巻くこの気持ちの正体を吉良はうまく掴むことができない。それを明らかにすることに心が怯えているような気さえする。
「――市丸は善いものを遺したね」
「なんですか?」
思索に耽りうまく聞き取れず訊ね返した吉良に、鳳橋は再度、今度はやや大きな声で朗々と繰り返した。
「キミと、キミたちと、あの柿の木。市丸は善いものを遺したと言ったんだ」
その言葉はまっすぐに吉良の心に届いた。渦の真ん中でぐるりと巡り、一体となる。
“遺した”、彼は確かにそう言った。
“置き去りにされた”、吉良ははじめ、そう思っていた。
この滲んでいる視野の先に見えるものは、これから先に我々を待っているものは、本当にこれまでと“違う”日々なのだろうか?
本当に?
◇
「なぜそんなことを知りたいんですか? 俺は俺の裡に秘めておきたいですがね」
例え自隊の隊長に対してであろうと、片倉の慇懃無礼さは損なわれることがない。吾里に対してよりはいくらか軽微だろうが、その程度だ。
「ちょっとした雑談だよ。以前はこういう時間もなかったの?」
「ありましたよ、人それぞれですが」
「じゃ、それやろうよ。惚気たくならない?」
「俺はそういう“タイプ”じゃあないんで」
「手強いなあ」
戸が開きっぱなしの隊首室から朗らかな会話が廊下まで聞こえてくる。吉良が覗き込むと、執務机に着いてギターを抱えている鳳橋と、その前に書類を片手に立っている片倉がいて、事務報告ついでに雑談に付き合わされているらしいことが察せられた。
「隊長、吉良戻りました」
「おかえり、イヅル」
「副隊長! お疲れ様です」
吉良が姿を見せると挨拶に迎えられる。すぐに片倉が不満げに鳳橋を手のひらで示した。
「吉良副隊長、この人仕事しません」
「そうみたいだね……」
「スパイだ、ひどい」
年功構わず若輩に咎められているというのに可笑しそうに笑う鳳橋に、吉良は呆れて嘆息する。そうするしか非難を表明するすべがないとも言える。
三番隊ではすっかり彼についてこの認識が定着してしまった――鳳橋新隊長はよく遅刻してくるし、就業時間でも構わず彷徨するし、満足するまで演奏しないと仕事を始めない。しかし、隊長位復職前に見せた“中庭の柿の木の下、柿を剥く吉良の隣で陰気な曲をひたすら演奏し続ける”という奇行のために、おおかたの隊士には「この人ならこんなもんだろう」と受け容れられ始めている。実力があること、それ自体は明らかなのだから。
軋轢がなかったことは吉良にとっても幸いではあった……が。
「まだご満足なさらないんですか? もう昼前ですよ」
「だって飛鳥がキミの話聞かせてくれないんだもの」
「他人のせいに……僕の話?」
小言を述べる機会も確実に増えた。どちらかといえば独断専行の気があった市丸ギンの在職時にはほとんどあり得なかったことで、吉良はその差異に辟易しかけている。
ところで、思わぬ形で己の名が出てきたことに彼は驚いた。人のいないところで人の話をしないでほしいと微妙な気持ちを抱いてしまう。
「俺がなぜあなたを気にしているかの理由を聞きたがってるんです。創作のために」
「……創作のために……」
吉良は肩を落とした。仕方ない、この人はこういう人だ。
「ご安心ください、何も話していませんから」
「安心する理由もないけど、一応礼は言うよ……」
「では、俺はこれで」
そうして片倉は隊首室を辞去する。残された吉良は鳳橋に向き直った。
「副隊長級会議にて、」
「イヅルは知ってるの? 飛鳥がどうしてキミのこと好きなのか」
「……知りませんね」
「そっか」
鳳橋はギターを爪弾き始める。“アルペジオ”と呼ばれる奏法なのだと、以前訊いてもいないのに教えられたことが吉良の脳裡に思い出された。
軽やかに弦のうえで弾けていく音色に合わせて、鳳橋は耳馴染みのない言語で囁くように歌っている。その歌声は優しく、慈しみ深ささえ感じられるのに、相変わらず彼の奏でる音は物悲しい。
「……何度も訊ねて恐縮ですが、もう少し明るい旋律にはならないんですか?」
「キミがそのほうが好きならいくらでも弾けるよ。でもなあ、インスピレーションが湧いてくるのが先だから」
「…………」
――吉良は、素直な気持ちを口にすれば、鳳橋の奏でる音に否定的な感情を抱いているわけでは決してない。ただ職務中は職務に集中してほしいと思っているだけだ。
勝手に己を理由にして、“インスピレーション”だなどとのたまって。
(「イヅルはそういう子ォやもんね」)
「……僕から得られる“インスピレーション”がいつか枯渇して、僕に何も感じなくなったらどうするんです?」
目を丸くした鳳橋が吉良を見上げる。吉良は、はたと気がついた。今、己の声音は、どこか心許なくはなかったか。
音楽を奏でる手が止まり、己自身の言葉にうろたえる吉良を見つめる鳳橋の眼差しがやわらかく緩む。
「そのときは一人の男としてイヅルの傍にいようかな」
「は?」
「『は?』って」
くすくすと口許に手を当てて笑う鳳橋に吉良は二の句が継げない。
からかわれたのだろうか?
「イヅルがボクをちゃんと見ていてくれたら、いずれどういう意味かわかるかもしれないね。キミはもう少し自覚的になったほうがいいな」
いつか言われたそれと同じような言葉が、謎かけのように繰り返される。困惑する吉良をよそに、鳳橋は「会議、どうだった?」と口にした。
「あ、はい。ええと……」
先刻の会議でまとまった逐一を報告しながら、吉良は鳳橋の打つ穏やかな相槌に耳を澄ませる。手渡した資料に落とされた伏し目がちの眼差しのうえにまつ毛の影が乗っている。ぱさり、とひとつ、瞬きをして、その二藍の瞳が上目遣いに吉良を見た。
「イヅル?」
――それは、未だ少し、吉良の理解の範疇にはない。