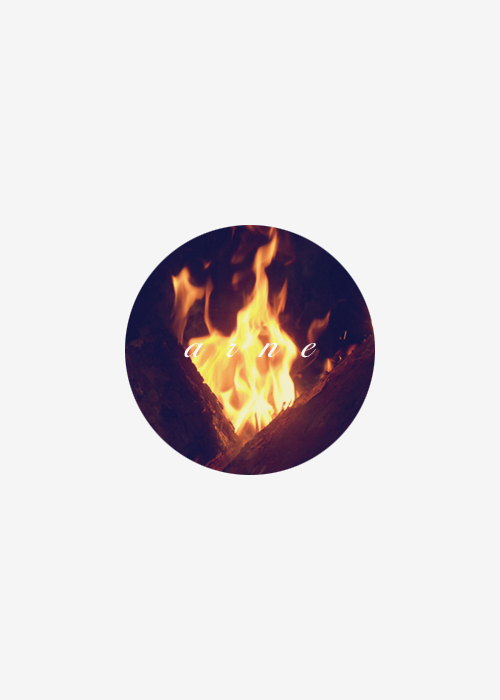激動と因縁に幕を下ろした一年の終わりは、驚くほど穏やかに暮れていった。
翌年、新年祝賀に訪れた文武百官を集めた宴は盛大に催され、主催である曹操と、いわゆる共催であるところの郭嘉もまた酒精が入って機嫌良さそうにしている。未だ冬の寒さは残るものの、程なく訪れるであろう花咲き誇る春を先取りするように、庁内は賑々しさに満ちていた。近々本格的に冀州攻略を目論むこの軍に於ける戦の前の静けさとは斯様なものであった。
「あはは、あすこの席は相変わらずの酒量だな」
隣に坐っている李典がそんなことを言うので、楽進は彼の目線の先を追った。そこには、先の大戦を経てすっかり酒友となったらしい郭嘉と荀攸の席がある。彼らの卓の上に載った酒瓶の量は他の卓と比べても明らかに多い。楽進の視界で彼らの席を横切った賈詡が――常ならば荀攸にちょっかいのひとつもかけるところを――神妙な表情になってそそくさと立ち去ろうとして、普段よりいっそう上機嫌の郭嘉に捕まったところだった。
「李典殿も……」
そこで楽進はふと、考えたことを口にする。
「あのくらいお酒を飲みたいと思うこともありますか」
「んー? 俺え?」
視線を戻して友人に向き直った李典もまたほどほどに酩酊していて大らかだ。
「まー、あんくらい飲めたらそりゃあ楽しいんだろーけど。満寵殿とかもさ」
「そうですね」
少し離れた別の席にいるもうひとりの酒豪を思い浮かべつつ楽進は頷く。
楽進は酒が得意ではなかった。
曹操の軍勢に武将として参入して以降の酒席では、気の良い同僚たちが愉快に酒を飲む様を見ながら過ごすことに楽しみを覚えたためそこまで苦ではなくなってきているが、若いころに故郷で年上に吐くまで悪い酒を飲まされた経験や、文官時代に酒席を断り上官の不興を買った記憶が、楽進の酒そのものに対する印象を良いものにはしていない。しかし、皆があれほど好きなのだから己も酒を好きにならなければならないのではないか、と楽進はこのほど思いかけてもいたのであった。
「ま、俺は楽しく飲めりゃ何でもいいかなー」
李典はあっけらかんと言う。その様子に楽進はいささか拍子抜けした。酒宴に於いても頻繁に席を共にしてくれる李典は、楽進が自身から酒が得意ではないと告白したことはないにしろ、己の酒量に合わせて彼自身も過ぎないようにしているのでは、と見えることが多々あった。
酒もろくろく飲めぬ、気の利いた話のひとつも持ち出せぬ、自分のような人物といて彼は本当に酒を楽しんでいるのだろうか?
「……そうですか……」
「うん。あ、楽進、ほら」
そうして李典は楽進の乾きかけた杯に気づいて熱い茶を注いでくれる。その気安い笑顔を見ながら、楽進の腹は雪が大地に積もるようにしんと冷えて凍えそうになっていた。
◇
いつのころからか曹操軍に連なる何名かの武将たちの間では、新年祝賀の数日後に小規模な鍛錬会を行おうというのが習慣になっていた。とはいえそれは何かと理由をつけて武器を交えたいだけの話で、日頃から行なっている手合わせとさほどの違いはない。
その場で楽進は徐晃と隣り合った。はたと楽進は、徐晃の友人がかの酒豪であり罠大好き軍師であることに思い至る。そして幸い己の友人である李典は現在、于禁と対峙して鍛錬場に立っていた。
「あの、徐晃殿。恐縮です。少々伺っても?」
「? はい、楽進殿。何でござろうか」
鋭心そのままの骨張った面立ちに柔和な笑みを乗せて徐晃は答える。楽進は己よりもいくらか高いところにあるその面を見上げて問うた。
「徐晃殿は、宴のときなどよく満寵殿と相席されていますよね」
「はあ、さようでござるな」
「その際にはどういったお話をするものでしょうか」
「?」
思いもよらない問いかけだったのだろう、徐晃は盛大に首を傾げる。そうして、ふむ、と視線をわずかに上向けながら考える素振りを見せた。
「大抵は満寵殿が、彼の考えを喋っておられるな」
「えっ」
「満寵殿は話題が泉のように湧いて来られる御仁ゆえ」
「徐晃殿は?」
「拙者は彼の話を聞いているだけでござるよ」
にこにこと徐晃は微笑んでいる。その様子に楽進は安堵と不安とが己のなかでぐるりとかき混ぜられるのを感じた。
「それは、その……徐晃殿はお話されなくてもよいのでしょうか」
問うてしまってから楽進は、いや、と慌てて手を振る。
「咎めているということではなくて」
「わかっており申す。拙者は……うーん、拙者も満寵殿も、それをできる人がやればいいと思っているゆえ、つまり、できない人が無理にそれをする必要はないというわけで」
そうして徐晃はにこりと口の端を上げてはにかんだ。
「ご参考になればよいのでござるが」
彼の表情は、言葉にされずとも楽進の不安感をわずかばかりでも把握しているのだと語った。楽進は気恥ずかしくなって、恐縮です、と返し俯く。
「お相手と面と向かってお話ししてみるのもひとつ手では」
「……それも、わかってはいるのですが……」
「ええ、難しいでござるな」
よくわかり申す、と徐晃は頷いてみせる。その答えに楽進は少しだけ安堵するが、それでもやはり徐晃には彼なりの道を見つけたがゆえの輝かしさがあった。
「がーくしん! 徐晃殿! 見てたか? 于禁殿から一戦取ったぜ、俺!」
ぱあっと明るい空気が嬉々とした声と共にその場に満ちる。軽やかに歩いてきた李典に楽進は慌てて、はい、と返事をしたが、彼は笑って、見てなかったな、と楽進の頭を小突いた。
「す、すみません……恐縮です」
「なぁに。いーっていーって」
快活な彼の笑顔は普段なら楽進をほっとさせるが、今は申し訳なさのほうが勝った。
「素晴らしい身のこなしであり申した。日々の研鑽が実を結んでいるでござるな」
「わかります? 楽進と鍛錬してると結構動けるようになってきたなーって思うんです、俺」
「なるほど」
三人の会話に于禁が入ってきた。
「何か違うなとは思っていたが……以前までの李典殿に対する戦い方では立ち行かぬか」
「そんなすぐ対策練らないでくださいね、于禁殿」
「無理な相談だな」
「おーい! 楽進、徐晃! 次は二人だぞ!」
鍛錬場から次の試合の審判役である曹休が大きく手を振りながら呼ぶ。はい、と返事をした楽進の背を、行ってこい、と李典が力強く押した。
「先ほどまでの迷いは、今は一旦忘れられよ、楽進殿」
「……はい! お相手願います、徐晃殿。楽文謙、行かせていただきます!」
「その意気でござる」
向き合う二人はそれぞれに武器を構える。きらりと徐晃の持つ大斧の背がひかめき、楽進の燃える瞳を反射した。
◇
夕暮れ、その邸の門を叩くと、裡から出てきたのは家主の荀攸本人だった。ほうと吐かれた白い息に慌てたのは訪問者たる楽進のほうである。家宰は置いているはずなのになぜ、と困惑して見つめ返すと、その意図を察したのか、あるいは視線に緊張したのか、荀攸は照れたように俯き加減になった。
「温くんには新年ですから数日ほど休暇を取らせました。寒いでしょう、どうぞ早く中へ」
その言葉を受け、楽進は荀攸の背中を軽く押して急いで中へ入る。正庁では火鉢のなかで赤く染まった木炭が軽やかな音を立てている。二人掛けの椅子に隣り合って腰掛け、すでに用意されていた軽食を促される。
「帰りがけに作っていってくれたんです。あなたが来られるからと伝えたら……」
「あ、へへ……恐縮です」
喜ばしさに楽進はいささか怪しげな笑みになってしまったが、荀攸は気に留めなかったようだ。客人の杯に熱い茶を注ぐと、次いで己のそれにも注ぐ。ほこりと湯気が立ち、その向こうにいる主人の像を滲ませた。
楽進がこうして荀攸のもとを訪れることができるようになってからひと月が経とうとしている。
二人の仲が縮まったのには官渡の戦いに於ける軍略のあれこれがあったが、楽進としてはそれより以前から荀攸に対して少なからず好意を抱いていたし、荀攸から楽進へ送られる視線もまた――“この手のこと”に鈍感であると評される楽進が確信してしまうほどには――熱っぽく心のこもったものであったから、戦の終わりにここぞとばかりに会食に誘ったのである。そのときは種々の手違いがあって結局大所帯の酒盛りと化してしまったが、以降、戦や軍務の合間合間に暇を作っては荀攸と共に過ごす時間を重ね、ここに至っているというわけだ。
そして楽進としては、そろそろ“次の段階”に進んでも良いのでは? と思い始めてもいる。互いの私室や私邸を行き来し、都合が合えば寝泊まりもする間柄になったのだ。時折、物言いたげに己の体に触れる彼の細い指は、楽進を芯から期待させてやまない。
「楽進殿? よろしければ、茶のお代わりはどうですか」
「あっ、はい! いただきます! ありがとうございます」
静かに注がれる茶の色を見ながら楽進は思う。無言は心地よいが、荀攸は酒精が入ると饒舌になるのだ。ふわふわとして口の回る彼も好ましい――と、考えがそこに至って、はたと楽進は気がついた。
「荀攸殿は……酒は飲まれないのですか?」
楽進の問いかけに荀攸は不意を突かれたようにぱちりと瞬いた。思えばそうだ。そういえば彼の杯にあるのも茶ではないか。酒豪の郭嘉に付き合ってあれほど瓶を大量に空ける彼のことだ、飲みたくないということはないはずなのに――
「ええ、酒は得意でないと伺いましたので。俺も、あなたの前では素面でいたいので……」
くしゃりとはにかむように笑って荀攸が言う。僅かに湧いた懐疑を吹き飛ばすほどの魅力的でいたいけな表情に、楽進の胸のあたりが図らずもきゅうと絞まった。
「それに、あなたに対しては素面でも雄弁なようですし」
「え?」
「だから俺を気にかけてくださったのでは」
小首をかしげる彼に楽進は、何のことだろう、と疑念を以て見つめ返す。荀攸は小さく口を開け、すぐに顔を逸らして「いえ、」とためらうように口にした。
「……俺が……あなたを思慕しているのだと、容易に推知し得るほどには」
「あっ!」
なるほどそういうことか、と楽進は得心した。そうしてすぐに言わなければならないこともわかった。
「いえ、私は……! 私もあなたのことをお慕い申し上げておりました! だからこそあなたが私を、み、見てくださっていることにも気づけたといいますか……」
膝の上でぎゅうと握られた拳が白くなる。相反して楽進の首から上はすっかり真っ赤だ。潤んだ瞳が真剣さを如実に物語っている。
楽進の拳に、荀攸の細い指先が触れた。
はっとして彼を見ると、常ならば沈着冷静なその表情は、その赤らんだ頬は、ものやわらかな微笑みは、確かに雄弁に楽進への思いを表している――彼も、己と同じ気持ちであるのだと。
添えられた手を握り返し、楽進は荀攸にぐっと体を寄せる。少し驚いたように肩をすくませた荀攸はしかし、眦を柔らかく細め、それからゆっくりと伏せた。楽進もまた、“しくじり”たくはなかったのでそれとなく“当たり”をつけてから同じように瞼を伏せた。
初めて触れた彼の唇は見た目通りに薄く、かさついてはいたが、想像を容易く超えて熱く、やわだった。
「…………」
「…………あ、あの……」
そっと顔を離し、あまりに間近にある相手の瞳の光を見て緊張に俯きかけてしまう楽進の頬に、荀攸のもう一方の手がそっと包み込むように置かれる。
「……嬉しいです」
「! わ、私もです」
「あの、今晩は……泊まっていかれます、よね」
「はい、はい!」
やや断定に近い荀攸の問いかけであったが、楽進もほとんど食い気味に答えを返す。その事実に二人は顔を見合わせて笑い合った。
晩冬の夜の帷は恋人たちの密やかな会話を隠すように、静かに静かに荀邸の上に降りるのだった。
◇
「がーくしん! おっはよーさん」
「わあ! 李典殿! おはようございます……!」
後背から力強く肩を抱かれ、楽進は飛び上がって驚いた。李典はいつものことと笑って楽進を解放する。
軽い会話を交わしていると、李典がどこか嬉しげに笑って「ところでさ」と口にした。
「あんた、なんかいいことあった?」
その問いかけに楽進はぱちりと瞬く。彼の様子に李典は自身の首許を指差した。
「勘」
「へっ、あ、ああ……」
楽進は李典を見つめて固まってしまう。言うべきだろうか。いや、李典はずっと己の荀攸に対する恋情を支援してくれていたのだ。何度か二人きりの場を作る企てをしてくれたこともある。楽進は李典に対して大恩があると言っても過言でない。
かの夜に見た荀攸の表情を思い出しながら、楽進は口を開き――そこでふと、引っかかりを覚えた。
「……李典殿、恐縮なのですが……荀攸殿に何か仰いましたか?」
「え?」
見上げると李典は首をかしげ、それから、あ、と小さく口を動かした。
「あー、いや、まあ、言った……かな」
「何と」
「……あんたは酒が苦手だろ。だから……できればあんまり勧めないでやってくれ、ってさ」
彼の言葉に楽進はぽかんとした。
――ばれていた?
冷気が吹き込む楽進の内心など露知らず、李典は悄然とした態度で視線を落とし、それから顔を上げて真っ直ぐに楽進を見つめた。
「……余計なことして、ごめん」
「あ、ああ、いえ! いえ、李典殿は何も謝るようなことをされていません! むしろ私のほうこそお気遣いいただき……それに、荀攸殿も、私の前では素面でいたいと仰ってくれて……」
焦って言葉を重ねる楽進に李典は弾かれたように明るく笑い出す。
「んはは、なんだよそれ。惚気?」
「ぅあっ、そんなつもりは」
途端に真っ赤になった楽進の頭を李典はくしゃりと軽く撫ぜる。きょとんと目を丸くした彼に、李典は今度やわらかく笑いかけた。
「お節介じゃなかったって思っていいのかな、俺」
その問いに楽進はこくりと首肯する。よかった、と李典はほっと息をついた。
「苦手なもんを無理に得意にする必要はないと思うぜ、俺。まー、みんなが好きなもののことは気になっちゃうかもしんないけどさ」
「…………はい」
ふたたび小さく頷く楽進の頭から李典は手を離し、次いで自身の癖毛を掻く。楽進は彼に問うた。
「いつから気づいて?」
「ん? あー、いつだったかな。まあ、結構最初のころだよ。あんま酒減ってねーなって思ってさ。あと一度こっそり杯いっぱいに茶を入れるのを見てから、もしかしてってな」
「ああ……」
周囲の人たちを不快にさせまいと秘密裏に行動したつもりが結局李典にはお見通しだったというわけだ。そのことを知って楽進は――心底から安堵した。そうして彼はその耳で、あんなにも不安で冷え切っていた腹の底に火鉢がぽんと置かれ、そのなかで燃えた木炭がぱちぱちと音を立て始めるのを聞いた。
「……ありがとうございます、李典殿」
「なんだよ、改まって」
楽進の言葉に、李典はやはり笑った。
「あんたの隣でさ、みんなが酒に飲まれて笑ってるのを見てるのが好きなんだよ、俺。静かで、賑やかで、ほっとする……。だから、おあいこだろ」
「……ふふ、はい。そうですね」
「またあんたの隣にいさせてくれよな」
「もちろんです! こちらこそよろしくお願いします」
ぺこりと頭を下げた楽進に、李典も笑顔のままに倣う。そうして顔を上げた二人は並び立ち、調練のために兵士たちが待つ鍛錬場へと向かって歩き出した。やがて過ぎ去りゆく冬の空に、彼らの白くあたたかい吐息がのぼり、溶けていった。