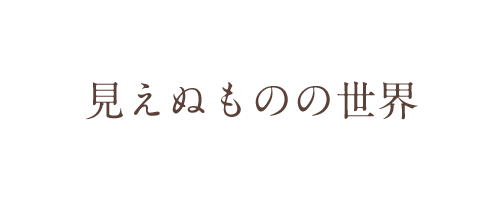「于禁殿」
快活な声が広い書庫にささやかに響く。呼ばれた于禁が振り返ると、低いところに真っ直ぐと己を見上げる楽進の顔があった。その手許に数冊の書簡があるのを于禁は見て取る。
「楽進殿。貴殿も読書か」
「はい。何かお探しでしたか?」
書棚の前での于禁の様子を見ていたのだろう、楽進は小首をかしげて訊ねた。于禁は顔に出さず逡巡したが素直に「孫子の巻二を探していた」と口にする。
そこで楽進が不思議そうな表情をした。
「先日そちらの棚にあったと思ったのですが……どなたか借りられているか、動かしてしまったのでしょうか」
「帳簿になかったゆえ、書庫内にはあるかと」
「なるほど」
過日のことである。いつまで経っても書庫から借りている本を返さないものがあるとして曹軍の文武百官に対して聞き取りが行われ、どうやら満寵の仕業であると判明したはいいものの、彼は借りていたことを忘れていたばかりか、備品の山のなかに埋もれてわからなくしてしまったという事件が発生した。軍師連中が総出で満寵の部屋を大掃除し――その際にいくつか罠や仕掛けが発動してしまい手伝っていた文官が数名軽傷を負った――結果として本は見つかったものの、また同じようなことが起こっては敵わぬと、印象に反してしっかり者の賈詡が主導して書庫に書物の貸借記録をまとめるための帳簿を置くことにした。
これはよく機能し、また人気があり借り手が後を経たない書物を優先して増やすことにも役立った。于禁が借りたがった『孫子』もそのひとつである。
「ああ、于禁殿! こちらに」
少し離れた書棚の前から楽進が声をかけた。于禁が向かうと嬉しそうにした楽進が一冊の書簡を差し出してくる。
「どなたか動かしてしまったようですね。見つかってよかった」
「かたじけない、楽進殿」
それをありがたく受け取った于禁にはふと、探すにしても楽進の行動はずいぶんと早く、手慣れていたように思われた。
「よく来られるのか」
自然と訊ねると、楽進はぱちりと瞬き、それから「その……」と口篭った。その様子に于禁は、何か差し障りがあるのか、と推測する。ならば余計なことを訊いてしまった。
「すまぬ、余計であった」
「あ、いえ! いえ、違います。そうですね、よく来ます。学ばなければいけないことが、私には多いので」
「む――そうか。貴殿は本当に勤勉だな」
「いえ、未熟ゆえです! 恐縮です」
気恥ずかしそうにはにかんで楽進は頭を下げる。その謙遜を制し、改めて礼を述べると于禁は帳簿に記録して書を片手に書庫を辞去した。そのまま廊下を進んでいると、程なく荀攸と行き合った。互いに礼を交わし、荀攸は于禁の来たほうへ向かって悠然と去っていく。
于禁は不意に、自身の目線から見る彼と楽進の上背が変わらなかったことに気がつき、なんとなく振り返った。于禁の視野、遠く廊下の突き当たりで、荀攸が書庫に入っていくのが見えた。
◇
そのことを次に于禁が思い出したのは、許昌の街で連れ立って歩いている彼らを見かけたときだった。
――意外だ。
と何よりもまず思い、それから、果たして己は彼らが並び歩いている姿を見て意外だと思えるほど彼らについて何か知っていただろうか、と考える。問うまでもなくそのようなことはなかった。軍事への関わり方に多少の違いはあれど、戦術を司ることが主である荀攸と、その戦術を遂行するために動く楽進が、その過程で相互理解を深めることを疎かにしなかったというだけのことだろう。
であれば、己も声ぐらいはかけるべきか――そのように一瞬は考えた于禁が結局そうしなかったのは、彼らがずいぶんと親密な様子で言葉を交わしていたからであった。
多少のぎこちなさは見られるが、かと言ってそれは険悪さによるものではないように于禁には見える。むしろ――己のような――人見知りをする性質の人間がそれでもなお他者と距離を縮めたいと手をこまねいているような、ある種の不器用さの発露にも感じられた。
そう思えば、于禁には身につまされることも多い。他者と交わるのが得手ではないばかりに、曹操や夏侯惇、夏侯淵らの気の良さに救われているところは大きい。
内省が深まった于禁の視野で、二人は小料理屋の前に立ち止まり、互いに二、三と言葉を交わし、そこで、楽進がそっと荀攸に寄り添うようにして何かを言った。ぱっと楽進を見た荀攸が、彼にしては珍しく表情を崩している。そうして、二人は中へ入っていった。
「…………」
于禁はその背を見送り、自身の目的であった武器屋へと歩を進める。どこか、胸にあたたかな感情が去来するのを感じながら。
翌日の調練は于禁の部隊と楽進の部隊の合同で行われた。楽進の部隊はその将軍の気質を反映してか妙に功名心に逸るものが多い印象が于禁にはあり、それは于禁の統率する部隊にはあまり見られないことである。初めのうちは他部隊とはいえ思うところあった于禁も、その自由闊達な空気を好ましく思う曹操の取りなしによって考えを改めるに至った。
「目の届く範囲すべてを自身の力で統率しようとするな、于禁よ」
あるとき、碁を打ちながら主君はそう言った。于禁は思わず彼を見返してしまう。曹操は伏し目がちに盤上を見つめていた。
「それではおぬしが参ってしまうぞ」
「そのようなつもりは……」
「ない、か。ふふ」
ぱちん、ぱちんと盤上に碁石が打たれる音がしばらく続き、やがて于禁は劣勢に追い込まれていた。
「…………」
「わしの勝ちか」
「……負けました」
「気に病むでない。良い対局であった。だが、今日はもう遅いな」
こうして軍務後に曹操の政務室での碁打ちの時間を設けられてから、于禁は碁に熱中するようになった。時折、曹軍の武将らを交えて何かの大会のような催しが開催されることもあり、この対局も近々行われるその練習のためにと場が整えられたものである。
「夏侯惇も夏侯淵も、碁の腕はいまいちだからな。その点おぬしはよく食らいついてくる」
「は、まだ未熟でございますが」
「謙遜も美徳よな」
夏侯惇が聞けば苦い顔をするであろうな、と可笑しそうに笑う曹操に一礼し、于禁は政務室を出る。ちょうど許褚が鍛錬から戻ってきたところで、李典、徐晃の二人と共に励んでいたのだと実に楽しそうに笑った。
「于禁も今度、一緒にやろうなあ」
「――ああ、無論だ。誘ってくれてありがとう」
許褚の素朴なあたたかさが心地よい。己のような付き合い難い人物にも分け隔てなく接してくれる彼にも、于禁は救われているのだ。
◇
ぱちん。ぱちん。ぱちん。
盤上に交互に打たれていく碁石を見ながら、于禁は違和感を覚えていた。対面にいるのは楽進で、彼はさほど碁打ちが得手ではないはずだった。無論、だからと言って于禁が手を抜くことはないが、それにしても。
――見覚えがある。この打ち方に。
ぐっと于禁の眉が顰められる。周囲で対局を眺めている将のうち、賈詡は顎髭をさすりながらちらりと隣に立つ荀攸を見、荀攸は表情を変えぬまま盤上を見つめ続けた。
曹休が隣に立つ李典に小声で、「今不利なのは于禁か?」と訊ねる。李典は軽く首を振り、「互角ですね」と答えた。
「ならばなぜ難しそうな顔をしているのだろう」
「やー……ははは」
李典の乾いた笑いがささやかに聞こえるなか、しばらく考えていた于禁が盤上に石を置いた。
「あっ!」
楽進が慌てたような声を発する。その様子に于禁は目を細め、すいと手のひらを差し向ける。
「貴殿の番だ」
「うっ……は、はい!」
今度は楽進が険しい表情をする番だった。于禁はその焦りようをじっと見つめ、それから盤上に視線を落とす。
以前、曹操との碁打ちの折、いくつかの棋譜を再現してその戦術を研究しようと二人で画策したことがあった。そのうちのひとつだったはずだ、と于禁は思い至る。両者の筋を綿密に計算に入れ、段階を踏まえる堅実な打ち方であり、突飛さはないが勝利に対して正確であった。
それゆえ今しがた于禁が打ったのは“筋”ではなく、あのとき見た棋譜に従ったものでもない。
対局を、己と楽進のものに引き寄せるための手段だ。
「…………では、ここに」
「ふむ」
于禁は少し考え、次の場所に石を置く。楽進は喉の奥で唸り、それから口許に拳を当ててじっと熟考の体勢に入った。その姿を于禁は見、それから横目でそれとなく荀攸に目線を遣った。彼は普段通りの茫洋とした表情で盤上を見つめているだけだ。
「…………」
于禁は、わかりやすく悩みながら次の手を考えている楽進に視線を戻す。自然と自身の眦が緩んでいることに彼は気づいた。
「よし! ここです」
「……む」
ついに楽進が盤上に打った一手は于禁をわずかに動揺させた。彼が次にどこに打ってくるか、于禁もいくつかの予想をしていなかったわけではない。だが、そのどれとも違っている。単純に、楽進が碁打ちに慣れていないから、とも考えられた。しかし于禁はそう見なかった。
――攻めの一手だ。
逃げ場がないわけではないが、ここで退くも于禁の本意ではない。
于禁が顎に手を当てて考えるのを、楽進は緊張した面持ちで見守っている。
「……なるほど」
于禁の指が石を持ち上げる。次の一手に、ほう、と嘆息したのは、一体誰であったか。
◇
「楽進殿、良い対局であった」
「ああ、于禁殿! いえ、こちらこそ」
終局後、于禁が碁盤から離れた楽進に声をかけると、彼は慌てて深く礼をしてきた。よい、とそれを制し、「貴殿は碁打ちに不慣れなものと思っていたが」と訊ねると、目線をさ迷わせた楽進がはにかみながら「勉強しました」と言いにくそうに口にする。
「…………」
指南役は“彼”か。そう問いかけて、于禁はやめた。彼は楽進が――楽進らしくなく――時折奥歯にものが詰まったような言い方をする理由に察しがついていた。
――邪魔立てなどせぬ。
――もとより貴殿らは、互いに互いを見ているのであろう。
「……こたびは私が勝ったが」
于禁が口を開くと、不安げにしていた楽進がぱちりと瞬いてひとつうなずいた。
「次に対局すればどうなるかわからぬ。貴殿は飲み込みが早いうえに思いきりもよい。まるで貴殿の武そのもののようだ。習練を続ければ必ず上達しよう」
常になく口数が多くなってしまった于禁に、楽進はしばらくぽかんとしていたが、やがて頬を染めてこくこくと何度も首肯した。
「恐縮です! また胸をお借りできれば」
「こちらこそ、いつでも対局を持とう」
ぱあっと明るい笑顔になった楽進は「はい!」と大きく返事をして、改めて深く一礼すると、では、と于禁の前を辞去した。彼の向かった先には荀攸がいて――于禁は、彼がずっとこちらを見つめていることに気づいていた。楽進を出迎え、並んで正庁を出ようとしたところで、荀攸が于禁を振り返った。
彼は于禁に向かって軽く頭を下げると、少し先を行く楽進の傍に並ぶように小走りで去っていく。
同じ高さに頭が並んでいる。
「……ふ」
気づけば、于禁の口許はほころんでいた。
『目の届く範囲すべてを自身の力で統率しようとするな』
曹操の言葉が思い起こされ、于禁は内心でうなずいて、今行われている対局の見物に行こうと入口に背を向ける。
見えずともそこにある、誰かの関係性に思いを馳せながら。