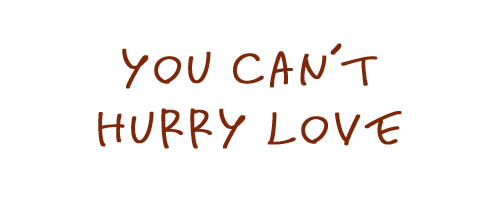兵士たちがすっかり出払った昼下がりの兵舎。張遼がそこを訪れたときには、彼は既に机に突っ伏して舟を漕いでいた。そうっと音を立てずにその側近くに寄れば、かすかに汗のにおいが張遼の鼻先を掠める。
「……高順殿……」
陥陣営とまで称えられる戦場での苛烈な戦いぶりが嘘のように、組まれた腕の隙間から見える彼の寝顔はいとけない。元よりどこか愛嬌のある顔立ちをしている高順は、その浮かべる快活な笑顔、すがすがしい物言い、竹を割ったような性格、とりわけ優れた武勇も相まって特に兵たちに好かれていた。そしてそれは――張遼とても同じこと。
張遼と高順とは歳が七つ違う。若い張遼が故郷から出て来て単身呂布軍に参入したとき、その上役として、或いは兄のような存在として教導してくれたのが彼だった。始めの頃は厳しく接され、負けん気の強かった張遼も腹を立てることがしばしばあったが、あるとき兵舎で一人残って訓練を続けていた己に差し入れだと言って彼が渡してくれた酪乳のうまさ、かけられた言葉、そして向けられた穏やかな微笑、そのすべてにほだされてすっかり心を奪われてしまった。一言一句思い出せる――お前の武勇はいつかきっと呂布殿をも越えていくのだろうな、もしその様を近くでずっと見ていられたらどんなにか素晴らしいと思う。お前は本当に、よくやっている。
あれ以来、彼の前で泣いたことはないが、今でも思い出してときどき恥ずかしく、目頭が熱くなる。あの頃自分の一番ほしかった言葉をかけてくれたのが、彼だった。
好意の目を通して見れば、どんどんかの人を好きになるばかりだ。時々へまをして照れくさそうに笑う目じりの皴や、軍師である陳宮との言い争いで負かされながらも納得のいかなかったときに小さく膨らませる頬や、兵士たちを見つめながらきれいに弧を描く口許や、驚いたときにぱちりと丸く見開かれる目。素敵だな、かわいらしいな、と思うことばかり降り積もっていく。
あれから随分時が経った。今ではもう、張遼は腕っぷしでは高順にすら負けることもないだろう。目の前にあるのはもはや呂布の大きな背中だけだと言ってもいい。
それでも、ずっと好きなままだ。
「…………」
緩やかに上下する肩は、彼が深い眠りの淵にいることを示している。体を折ってそっと覗き込むように身を屈める張遼の心臓はばくばくと高鳴っていた。
は、と己の呼気が高順の頬に触れるのを感じる。唇を震わせながら、そのこめかみに寄せたとき――
バタン!
兵舎の戸が騒がしく開けられた。勢いよく入り口を振り返れば呂布の娘である呂玲綺が槍を携えたまま、じっと張遼と高順を見つめている。張遼は目を見開いて絶句した――見られてしまった!
彼女は張遼の様子をくまなく観察し、それからニヤリと口の端を上げ、兵舎から身を乗り出してどこかへ向かって大声を出すような仕草をした。
「父上えーっ、文遠があーっ」
「ううわあああああ!!!」
翻って飛びかかってくる張遼をその身のこなしでいなし、はっはっは!と呂玲綺は哄笑した。腰に手を当てて張遼を睥睨する様は紛うかたなき呂布の娘である。歯噛みする張遼は、己の背後で身じろぎするものに気づいた。高順がむくりと起き上がり、大きく伸びをしたのである。
「んん……ん? 文遠? おお、玲綺殿まで」
とんだ失態を、と彼が浮かべる照れ隠しの笑みは張遼が好きな表情の一つであったが、今はやに下がっている場合ではない。何せその呂玲綺の存在が問題なのである。先ほどの様子からすれば事の次第をしっかり目撃していたのは明らかであり、彼女が高順と挨拶を交わしながらも張遼に向ける視線はどう見ても面白がりのそれである。
「高順殿、父上が探しておりました。すみませんが足を運んでやってくれますか」
「うむ、相わかった。文遠も、ではな」
「あ、ああ、はい……」
嘘かまことか呂布からの呼び出しに高順は軽く手を挙げて兵舎を去って行く。その後姿を見つめていた張遼の耳に、呂玲綺の声が飛び込んできた。
「『高順殿、お疲れなのだろうか……私が癒して差し上げよう』」
「ちょっ……!? そのようなことは!」
「『それがしの口付けで目覚めるだろうか』?」
「それがしの声色を真似ないでくだされ!」
無理に作った低音で呂玲綺が言うのを張遼が咎めると、なおも彼女はニヤニヤとして張遼を見つめている。
「そうかそうか。文遠は高順殿が好きなのだな」
「グ……」
ここにきてついに張遼は目を逸らし続けていた現実に直面した。呂玲綺に、弱みを握られてしまったということに。
心底口惜しそうに眉間に皺を寄せる張遼の肩に、彼女の少し小さくとも逞しい手が置かれる。
「案ずるな、我々は同志だ、文遠よ。互いの利のためここは一つ同盟を組もうではないか」
「え……? は?」
堂々たる佇まい、張遼の肩に置いていた手を今度は彼の目の前に差し伸べて、呂玲綺は高らかにのたまった。
「私は貂蝉殿が好きだ」
◇
青天の下、槍の穂先が打ち合う重い金属音が響き渡る。ヤア! と天を突き射すような甲高い声を上げるのは呂玲綺だ。何を隠そう参入時点で既に武力だけなら当時の高順の上をいっていたという伝説持ちの彼女は――少し凹んだ高順を慰めるのは実に役得だったと張遼は今も思い返す――既に呂布軍のつわもの達を五人立て続けに打ちのめしていた。
「やけに気合いが入ってるよな、呂姫殿」
「昇格したのがついこの前だろう。呂布殿が珍しく褒めていたと言うじゃないか、やる気も上がるさ」
張遼の近くにいる兵士たちが会話しているのに耳を寄せながらも、それもあるけどそれだけではないんだよなあ、と目を細めて渋面を作る。
「玲綺様の武芸は素晴らしいですね」
張遼の傍らでたおやかな笑みを浮かべるのは、何を隠そう呂玲綺のやる気の主要因、貂蝉その人である。槍兵訓練で模擬戦闘を行うと聞いた彼女は、初めのうちは心配をして兵舎に足を運んだものが、すっかり呂玲綺の武人顔負けの立ち振る舞いに感心してしまっていた。
いや――もはや呂玲綺は武人そのものと呼んで差し支えない。何より彼女が自身のことをそう表現した。
『玲綺様、殿方に混じって武芸に励まれるのも立派ですが、あなた様のお力は殿方には――』
『貂蝉殿、見くびらないでください。私の腕っぷしであれば高順殿にも勝てると父のお墨付きもいただきました。ご心配はありがたいのですが……もし不安なら、どうぞ目を伏せて私の側近くにおいでください。あなた様が感じるのは、きっと武者の気魄のはずです』
高順がその場にいたなら頭を抱えて屈みこんでしまっただろう。急に矢が飛んできたような心持ちになったかもしれない。幸いにも彼は騎兵の行軍訓練のために城内にはいなかった。
呂玲綺の迫真の表情に気圧された貂蝉は、でしたらよいのですが、と結局そのまま観戦している。呂玲綺の側近くには寄らなかった。当てが外れてあれっ? という顔になる彼女を見たのはどうやら同志である張遼だけらしい。
「それでも、やはり少し不安です。わたくしは奉先様とご一緒させていただいておりますから平気ですが、彼女は将としてお一人で兵を率いるお立場。まだお若いのに何かあったらと思うと……」
貂蝉は憂悶の表情で少しうつむく。
彼女を呂布の副将につけたのは陳宮の策であった。呂布はその神勇、巧みな騎馬術のために攻撃には優れるが、その猪突猛進さゆえに防御能力に欠ける。そこに知力のある貂蝉を副将としてつけることで防御能力の低さを補うことができ、また愛妾の存在ゆえに呂布が暴走することもなく、同時に貂蝉にいいところを見せるぞ! と奮戦もしてくれる。これぞ一矢にて三羽の鳥を得るが如し! と高らかにのたまった陳宮に、将兵一同――それは普段険悪な仲の高順でさえも――万雷の拍手を送ったのは昨年の今頃、ちょうどその呂布の外出を狙って開かれた極秘軍議の席でのことだった。
大丈夫ですよ、と張遼は彼女を励ますように言う。
「呂布殿や高順殿、たくさんの優れた先達のご指導の賜物で、彼女の統率力も日々磨かれております。その武勇はもはや言うに及ばず……我々が考える以上、彼女は伸びやかに成長しているようにそれがしには見えます」
「まあ……」
貂蝉は感嘆の声を上げて張遼をまじまじと見た。その反応に首をかしげる張遼に、彼女は嬉しげに微笑みかける。
「文遠様は玲綺様のことをよく見てらっしゃるのですね」
「ん? …………、いや、違う。違いますぞ、貂蝉殿」
「いいえ、ご謙遜なさらないで。お二人なら奉先様もきっと……」
「やはり! そうではありません貂蝉殿!」
「文遠!」
思わず大きな声を上げた張遼に気づいたらしい、六人目の兵士を地面に伏した呂玲綺が睨みを利かせて張遼の字を呼ぶ。呼んでらっしゃいますよ、とくすくす笑う貂蝉に、その様子を見てかさらに声を荒げて張遼を呼ぶ呂玲綺。張遼は内心叫びながら、肩を怒らせて呂玲綺の方へ大股で歩み寄った。
「貴様、貂蝉殿と何を良い仲になっているのだッ!」
「く……! 貴殿の普段からの頑張りをそれがしなりに顕示しようとしただけです!」
「ではなぜあんなに距離が近くなるのだ!」
小声で仕様もないことを言い合う二人の様子も、傍から見れば仲の良い男女の風情である。実際、離れたところで床几に腰かけている貂蝉にはそう見えた。
「ええい、まどろっこしい! 文遠、こやつらでは相手にならぬ。次は貴殿が相手をせよ!」
「な……!」
腕を振り払い、呂玲綺が声高に言った。口をぽかんと開ける張遼に、呂玲綺は片眉を上げて、私に勝つ自信がないのか? と挑発するようなことを口振りになる。
呆気にとられたのは周囲の兵士たちや、貂蝉も同じだった。彼女は――なぜそのような発言が出てくるのかも全く理解していないために――急に青ざめて、それはいけません、と慌てて駆け寄ってくる。
「玲綺様、いかがされたのですか? 文遠様は、あなた様を……」
「何を仰ろうと言うのですか貂蝉殿っ」
「貂蝉殿、今やこの文遠が軍の二番手と言ってもいい武勇の持ち主です。こやつを打ち倒さば、あなた様も心底から私をお認めくださいますか?」
迫る呂玲綺に、貂蝉は目を丸くして少し後ずさった。返す言葉もなく、着物の裾で口元を覆ったまま首をかしげる彼女に、呂玲綺はフンと鼻を鳴らす。
「刮目してご覧ください。私の武勇を!」
威勢よく貂蝉に背を向ける彼女は、武器を取れ、と言わんばかりに張遼に槍を差し出した。しばらくその槍をじっと見つめていた張遼だったが、やがてわかりました、と一つ首肯してそれを受け取り、兵たちの囲む中を進んでいく。
「ぶ、文遠様……!」
貂蝉の必死な声色に、張遼は立ち止まって振り返った。
「貂蝉殿、もはや玲綺殿は我々と同じ武弁者。あなた様のご心配には至りません」
「で、ですが……」
「――そして、身の程を知らねばなりません」
張遼は呂玲綺をじっと見据えた。その視線に、彼女は思わず口を引き結んで立ち止まる。その様を見た張遼は口許に笑みを浮かべ、幸いにも、と口にする。
「彼女は彼我の力量差も知らぬような愚者では決してありませぬ。大丈夫、強者は皆初めから強者だったわけではござらぬ」
すい、と槍の穂を呂玲綺に向けた張遼は、さあ、と笑ったまま構えの姿勢を取った。
「来られませ、玲綺殿」
結局、呂玲綺は張遼の類稀なる武勇の前になす術なく敗北し、大きな怪我こそなかったものの擦り傷を負ってひどく落ち込んだ挙句、貂蝉に介抱されがてらそれとなく甘えていた。役得だなあと張遼は思う――他方彼は、事態を聞いて駆けつけた陳宮と、訓練を終えて兵舎に戻ってきた高順という呂布軍の首脳陣にこっぴどく叱られた。
大人なんだから挑発を受け流すくらいしなさい、と二人は声を揃えて言う。大人げなかった自覚のある張遼はただただ縮こまるばかりである。
「……普段のお前なら玲綺殿を諌めるくらいしただろう? 文遠、何かあったのか?」
陳宮が呂布へ事の次第を報告するためその場を辞去してから、努めて優しげな声で高順がそう問いかけた。目を細めて小首をかしげるその仕草に、ああかわいらしいな、と場違いなことを張遼は考えてしまう。
「文遠」
「あっ、はい、いやその……どうかしておりました。ええと、頭に血が上って」
「? そんなふうには見えないが」
「あなたの前では見せたくない顔です」
そう返した張遼にきょとんと目を丸くした高順であるが、やがて得心がいったのか口許をその手のひらで覆い隠すと、なるほど、と何度も頷いた。
「随分立派になったものだと寂しく思っていたが、これはこれで複雑だ。文遠、お前はもう俺など簡単に捻り上げてしまえるだろう。俺に気を遣うことはないんだぞ」
軽やかに肩を二度叩かれ、そっと優しく腕を引かれて立たされた張遼は、高順が勘違いをするまま曖昧に彼に苦笑を返した。
そういうわけではないのだが――そう素直に言えばやはり彼は少し落胆したような表情を浮かべたであろうが――このまま師弟の関係に甘えているのが一番いいのだろう。呂布軍二番手の武勇を誇ると言われた男は、その実呂玲綺ほどの積極性も持てないでいるのだ。過ちを犯せば、先にかの鬼神の娘に弱みを握られたようにそれ相応の罰が待っているのだから。
◇
「文遠、あなたが玲綺殿に懸想しておるというのは本当なのですか?」
「ブハーッ!!」
休憩がてらの茶の席で陳宮に不意打たれ、張遼は飲みかけの茶を勢いよく噴き出した。汚いですな、と迷惑そうに言って布巾を取り出す彼を、誰のせいだ、と咳き込みながら睨み返す。二人きりなのが幸いだったが、だからこそかの軍師もそんな妄言を口走ったのだろうとはすぐに思い至った。
陳宮は未だ咳き込んでいる張遼を見、先を促すように顎をついと上げる。
「で? どうなのです」
「でっ、でまかせです! よもや貂蝉殿が仰っていたのですか」
「ええ」
応援して差し上げましょうと言われました、などとのたまう陳宮に、張遼は頭がくらんだ。脳裡に浮かぶ美姫の常ならば慈愛に満ちた微笑が今は忌々しい。
「信じないでください。彼女は誤解しておるのです」
「それならば良いのですよ。玲綺殿は――」
数瞬間が空き、呂布殿のご息女ですからな、と続ける陳宮に、おや、と張遼は目を丸くする。彼も伊達に陳宮、貂蝉に続く呂布軍の知力第三位を誇っているわけではない。
「…………陳宮殿。何かご存知ですね?」
「…………」
しまった、という表情をする陳宮はいつもどこか詰めが甘い。いよいよ察した張遼は彼の坐る傍まで回り込むと、実は私もです、と小声で言う。
「玲綺殿の、思い人のことです」
「…………文遠も気づきましたか」
その言葉に張遼は首を振った。怪訝な表情の陳宮に、本人から直接伺いました、と言葉を繋ぐ。
「! なんと……」
「それで、仲を取り持とうと玲綺殿を褒めそやしていたら誤解されたのです。そういうわけで、それがしは一介の協力者に過ぎません!」
高らかに宣言した直後、張遼ははっとなった。
「ま、まさか、かの女人は高順殿にまで同じようなことを……!?」
「……さて、それはどうでしょうな」
高順を常日頃から目の敵にしている陳宮は彼の名前が出ていささか気分を害したようではあったが、張遼の不安にはきちんと返事をした。
「ところで、あなたが協力者となった所以が気になりますな。玲綺殿から直接秘密を打ち明けられる経緯といい……」
ぎくり、と張遼は肩を揺らす。陳宮は詰めが甘いとは言え、やはり視野は広く、察しも良かった。
「あなたにも似たような秘密でもおありなので?」
「はて、なんのことでしょう。それがしは思い悩んでおった玲綺殿の相談に乗ったまでで」
「日頃から景気良く走り回り、兵士たちを打ちのめして回り、あなたにまで勝負を挑むような剛の者が思い悩む、ですか」
さすがの張遼も陳宮のあんまりな言い草に黙り込む。ようやく失礼ですよと窘めれば、陳宮は少しも悪びれず、これはこれは、とのたまった。
「ですが、軍や自身の士気に関わらない限りは、思う様自由に振る舞ったって私は構わないと思いますがね。なにせ君主がああだから」
呆れたような声音の陳宮ではあるが、その言葉には張遼を励まそうとする色が見えて、張遼は思わず笑みをこぼす。その顔を見て安心したように嘆息すると、陳宮は椀に残っていた茶をあおって席を立った。