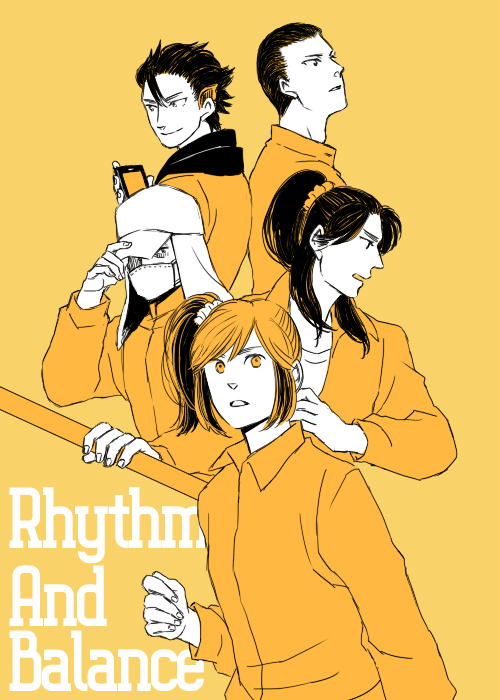中秋だというのに冬と紛うばかりの寒さが続いている。
大通りから小路に入って少し歩くと見えてくる越南菜飯店の店内から奥へ伸びる狭い通路を進むと、折り返して二階に登る階段がある。ギシギシと不安な音の鳴るそれを注意深く登れば目の前に、ところどころ錆のある古い金属の看板にA3サイズに一文字ずつ『百鬼実験室』と書かれテープで繋がれた紙が重ね貼りされ、そのまま開きっぱなしの赤い扉の横に立てかけられているのが現れる。それを確認した彼女は、その手に持ったチラシに目を落とし、大きく頷いた。
「あのう、ごめんくださあい」
赤い扉の室内を覗き込むと、ゴミか機械か何かで溢れた中に三人の男性がいた。彼らは互いに交わしている議論が白熱している風で、彼女の声に気づかない。パートナーはいつも彼女の声に耳を傾けてくれるだけに、彼女は少しだけむっと口をへの字に曲げ、再び口を開いた。
「あのう!」
些か強い口調で呼びかけると、彼らはほとんど同時にその声のする方に顔を向けた。その中の一人、赤毛の男がぱちりと目を瞬かせる。
「小喬!?」
「あれ? 孫権様!」
小喬と呼ばれた女に孫権と呼ばれた男は駆け寄った。小喬は大きく首をかしげているが、孫権は驚きと心配とが入り混じった表情をしている。
「な、なぜここに? なぜここが? 周瑜は? 知っているのか?」
「孫権様こそ何してるの? お手伝い?」
「わ、私は仕事だ。手伝いではない」
そう返したところで孫権は、小喬の手に一枚のチラシがあることに気づく。
「それ……」
「え? あ、うん。あたしね、お手伝いに来たの。下のお店で見っけてえ……」
「え!」
孫権は俄かに慌てた。いや、それは、とか言っている彼の後背にいた二人の男が、孫権の体越しに小喬を見る。
「お前さんの知り合いなら、全く知らない人が来るよりはいいんじゃないかい」
「私もそう思います。ええと、小喬殿?」
彼らは孫権の横に立つとそれぞれ彼女に挨拶をした。
「あっしは龐統、字を士元だよ」
「私は諸葛誕、公休と申します」
「あたしは小喬! えへへ、よろしくね、龐統さん、諸葛誕さん」
「ま、待て待て待て!」
三人の間に押し入った孫権はまず小喬を向いて、周瑜は君のすることを知っているのか、と問うた。小喬はそれに対し首を振って返す。
「周瑜様ね、最近あんまりお家に帰って来ないし、帰って来ても疲れてるからすぐ寝ちゃうし、なんだかずっと怒ってるみたいなの。あの駅の爆発からだよ。ずーっとかかりきりなんだって……。だからね、あたし、何か周瑜様を助けられることができないかなって思ったんだけど、あたしお金すぐ使っちゃうからお小遣いもあんまり残ってなくて……それで」
「わかった。周瑜は把握していないのだな」
冗長な小喬の返答から端的に欲する答えを見つける孫権に、龐統と諸葛誕とは二人の関係性や小喬の性質などを察する。
孫権は彼らを顧みるとその肩を抱き、小喬に、しばし待て、と言い置いて部屋の奥に引きずっていった。
「周瑜というのは私と朱然の共通の知人で、私の兄の親友であり、兄と共に中央警察の刑事をしている」
ごく小さな声で孫権が言う。朱然とは今この場にいないもう一人の仲間である。二人は首肯で先を促す。
「そして彼女はその周瑜のパートナーでもある。ご覧の通り天真爛漫で善良な人物だ。だが私は兄の親友の恋人を危険な目に晒すつもりはない」
兄上と兄嫁と周瑜に袋叩きにあう、ぽそりと孫権は付け加える。
「二月も経ってようやく現れた雇用希望者ではあるが私は彼女を帰そうと思う。異論はあまり認めたくないが聞くだけは聞く」
「あ、いえ、でも、孫権殿……」
険しい表情の孫権に、諸葛誕が肩越しに後背に目を向けながら冷や汗をかいている。
「なんだ?」
「……意に沿わないようですが」
「?」
諸葛誕の手のひらが示す先、孫権が振り返ると、ごく近くに小喬の頰を膨らまし眉根を寄せた不機嫌な表情があった。
「孫権様! あたしのこと追い返すつもりだったでしょ!?」
「うっ……だがしかし、我々がしているのは危険な仕事だ!」
「そしたら孫権様も危ないんじゃん! 孫堅様や孫策様は孫権様のお仕事知ってるの?」
孫権は言葉に詰まった。龐統と諸葛誕は、知るはずがないだろうなあ、と内心でため息をつく。彼らを見返したくて、彼らの役に立ちたくて、孫権が己の能力を生かしたくて始めた仕事だ。龐統と諸葛誕とは彼と利害が一致して共同運営という立場にいるが、朱然に至ってはほとんど付き合いと好奇心で参加している節がある。
小喬は目ざとく孫権の動揺を見て取った。
「あたし、言っちゃうかも。孫権様が危ないことしてるって。このチラシ見せたらきっと二人とも心配してここに来ちゃうよね……」
「だ、だめだだめだ! 小喬、それを返せ!」
むんずと小喬の手にあるチラシを掴んだ孫権だが、小喬も譲らず力いっぱい足を踏ん張る。
「じゃああたしのこと雇って! なんでもできるから!」
「なんでもできるわけがないだろう! そうだ、君には妖魔が見えるのか!?」
「まあまあ、孫権殿」
一歩も譲らぬ二人の攻防に呆れ混じりに龐統が割って入る。彼は両の手で二人の肩を押しやり、ひょいと破れかけたチラシをつまみ上げた。
「外仕事は確かに危ないけど、電話番なら心配もないさ。それに、その“周瑜殿”が出かけた後に出勤して、帰ってくる前に退勤させるようシフトを組めばいいんだよ」
龐統の言に、しかめっ面だった小喬の顔が明るくなる。
「ありがとう〜! あたし、お掃除でもなんでもするよ!」
「あ、いえ、それは結構です」
間髪入れず諸葛誕が断りの意を示す。確かに見回せば部屋中がゴミと見紛う機械や資材で溢れていたが、これらは全て彼らの仕事に必要なもので、その中には取り扱いに細心の注意を払わねばならない“武器”や“精密機器”も多くあった。
そうなの? と小喬は首をかしげるも、重ねて龐統に室内の一部を示して、特にあの辺には決して触らないように、と戒められ不承不承頷いた。
そうして小喬は孫権をぱっと見上げる。最終確認のためである。自身をこのいかがわしい実験室に雇い入れることの了解を他でもない彼に得ようというのだ。孫権は苦虫を噛み潰したような顔で唸り、やがて、わかった、と言った。
「ただし、決して周瑜を始め我々の親類縁者には他言無用だ。それから、雇用期間を周瑜の仕事が落ち着くまでと定める。不定になるから給与は日当てになるが構わないか?」
「うん、わかったよ。ありがとう孫権様!」
笑顔が花咲く。孫権は変わらず不満げな顔つきをしてはいたが、龐統と諸葛誕とはほっとしたように顔を見合わせて微笑んだ。
「いやあ、実際人手が足りないのは本当だったしねえ。受話器を取ることができる人が増えてありがたいよ。まあ碌々かかってもきやしないんだけど……ん?」
そう述べた龐統はそこではたと気がついて目を瞬かせる。他の三人が彼を見やると、龐統は諸葛誕と小喬とを交互に見比べた。二人はほとんど同時に首をかしげる。
「そういやあお前さん、諸葛誕が見えるのかい」
「え?」
「え?」
「あ、確かに」
ぽふん、と諸葛誕が両手を合わせた。
◇
我々は陰陽の環のなかに暮らしている。陽の界に暮らす生者は死ねば陰の界の死者となり、陰の界で暮らす死者は死ねば陽の界の生者となる。
一般に生者が死者となるとき、あるいは死者が生者となるとき、その者は一方の界より他方の界へと住処を移すことになるが、このとき必ずくぐるのが泰山にある巨大な“門”であり、我々のもとには必ず泰山府からの使いが訪れ、これをくぐるようにと口うるさく言われ門前まで引きずってでも連れて行かれる。それに反抗して“門”を通らず独自のやり方で陰の界に足を踏みいれようとすればすぐに泰山府君の目に留まり、懲戒処分として泰山府の小間使いとして百年休みなく使役させられてしまうばかりか、晴れて戒めが解かれてそれぞれの界で生活をするとなったときにご近所に悪評が広まってしまう。
これには理由がある。個人が容易に陽の界より陰の界へ、またその逆へと移ることができようものなら、ただでさえ魅力的な生死に必要以上の個人の自由意志が働いてしまうことになり、陰陽の均衡が崩れることになりかねない。均衡の崩壊は宇宙の崩壊である。そんなわけで特に泰山府君の司る陰の界では、陽の界よりも滞在日数が比較的短く見積もられているかわりに安易に自ら死を選ぶことができない構造になっている。常にそこら中に泰山府君の監視の目があり、自ら死を選ぼうとしようものなら府の役人によって迅速に引き立てられ、こちらもまた百年小間使いの刑に処される。陽の界に移りたかったのに結局陽の界への道が遠ざかるというわけである。
しかし、昨今この均衡が陽の界の側から崩されようとしている。先行き不透明な暗い世相、思慮に欠けた政治情勢、蔓延る過激思想、あるいは行き過ぎた信仰、各地で頻発する紛争や飢餓、災害または貧困。戦時においてのみならず、平時の個人であっても容易に武器を手に入れられる時代になった。武器とはかつては為政者により支給されるものだった。それが今や一般庶民の手になり、我々はいつも道具があればそれを使いたがる生き物だった。
そしてこれらは遠からず起こり得ると予測された事象でもあった。陽の界の膨張する力が一時的に陰の界の収縮する力を圧倒し、飲み込まんとする太極の流れ。陽の攻撃性の暴走である。
◇
諸葛誕は三ヶ月前に何者かによって殺害され死者となった。ちょうどこの越南菜飯店二階にある、当時は空き部屋となっていたこの部屋の中での出来事である。折しも飯店は休業日で、建物内には諸葛誕と殺害犯の二人のみがあった。殺害犯はそのまま逃亡し、しかし、諸葛誕のところへ泰山府からの使いが向かう手続きが取られる前、ほとんど同時刻に街の南部にある三國駅で大規模な爆発と周辺施設を巻き込んだ大火災――恐らくテロかと思われたが、いかなる犯行グループからの声明もない――が起き、多数の死傷者を出す事件に発展した。突発的に発生したこの爆発事件により泰山府は死者の処理や名簿の整理に追われてんやわんやとなり、結局諸葛誕はそのまま死者名簿からこぼれ落ちてしまったのである。
越南菜飯店二階の空き部屋で、諸葛誕は途方に暮れた。そもそもこの二階は飯店の従業員らもほとんど訪れず、売りに出されたまま買い手もつかないような忘れられた場所だった。諸葛誕は己がなぜこんな目に遭っているのかも、なぜここで殺されなければならなかったのかもわからない。彼の記憶は混濁していた。
そのうち――三日もすると、何やら怪しげな臭いがするということで久しぶりに二階を訪れた店主により諸葛誕の死は地元交番に知らされたものの、くだんの駅爆発事件に人手のほとんどが駆り出されていたため、やる気のなさそうな二名の警官により身元不明者の自殺と明らかに状況証拠にそぐわぬ結論を出され、さっさと事後処理をして特殊清掃業者に片付けさせようと話がつけられてしまった。もう二度と買い手はつかんなあ、とぼやく店主に対し、店を移せばいいのにと諸葛誕は思った。
そのときに現れた“清掃業者”が、孫権と龐統であった。彼らは諸葛誕――遺体ではなく、部屋の奥、通りに面した窓際でぽつねんと坐っている死者のほう――を見るなり、双眸を溢れんばかりに見開き、彼らの仕事道具をその手から取り落としてしまった。
二人は窓辺の諸葛誕と床に転がる諸葛誕だったものとを何度も交互に見、やがて背の高いほうの男――つまり孫権――が恐る恐るといった風に諸葛誕に歩み寄ってきた。
「あの……死者の方?」
「へ? あ、はい。そのようです」
「おお……!!」
二人は互いに手を高く上げ、ぱしんと軽やかな音を立てて合わせる。ぱちりと目を見開く諸葛誕に彼らは駆け寄ってきた。
「いや、嬉しいよ。ようやっと死者に会えた。理論上はね、いるはずだったんだよ。これであっしの研究がはかどるよ!」
「これでまた怪異の謎に近づくぞ!」
わっと諸手を挙げて歓喜する二人を交互に見、諸葛誕は呆気に取られるも、やがて二人がずいぶんと仰々しいことを口にしていることに気づく。太極がどうの、混沌と自然がどうの、天地がどうの……
「あの、すみません」
騒がしい彼らに声をかけることは諸葛誕にとってとても勇気の要ることだった。なぜなら彼らの様子は実に喜色に満ち満ちていたからである。
諸葛誕は至極申し訳なさそうに眉根を寄せた。
「私はそんな大層なものではありません。いつの間にかなぜかここにいて、どうするべきかもわからないのです。自分が死んでいるということは理解できていますが、なぜ死んでいるのかもわかりませんし……」
ちらりと彼らの後背に転がる己の遺体に視線を向けると、そこでようやく二人は面に哀切を浮かべた。
「すまなかった。あなたにはお悔やみを申し上げる。無念だったろう」
「いえ、別に……」
今更そんなことを言われてもという気持ちである。
「あっしらは一応お前さんのご遺体を片付けにきたわけだけど、どうする? あっしの機械を使えば保管しておくこともできるよ。まあずいぶんと……」
龐統は言葉を濁した。それもそのはずである。腐臭もさることながら諸葛誕の遺体には胸や腹、背中に大量の刺し傷があり、あまりに痛々しい惨状だった。
「いえ、もうそれは処分してもらって構いません。なぜこのようなことになってしまったのかは気がかりですが、あまり見ていたいものではありませんから」
「そうかい、それじゃあ」
諸葛誕はそれから、二人が自分の遺体を丁寧に袋にしまって片付け、床を綺麗にしていくのを側に立って見ていた。妙な心地だった。己の意識はまだここにいるのに、あれはもう空っぽの容れ物になってしまったのだと思った。
一通り業務を終え、街の火葬場に諸葛誕の遺体を届けた二人は、なんとなしについてきた諸葛誕本人と共にそれがすっかり灰になってしまうまで扉の前で話し込んだ。
孫権と龐統とは、各々街に生じた異変を調べていたのが偶然出会って手を組んだ仲であるということだった。孫権は生来怪異なる事象を視ることのできる碧い眼を持っており、このために余人に虐げられることも多く、龐統は彼の両親が陰の界の研究の最中に禁忌に抵触したために、その咎として爛れた肌を持った子供として生まれた。彼らは己の境遇を倦んだり他者を恨んだりしなかった。そればかりか却って“この世の怪異の謎を暴く”という執念に燃えた。そうして特殊清掃業務――彼らはこの業種が最も陰の界に近しいと考えたようだ――に携わる傍ら、怪異の研究を進め陰の界への手がかりを探していたらしい。そこへ諸葛誕との出会いがあったということである。
彼らはさっさと特殊清掃業務を“副業”に位置付け、本格的に陰の界への研究に専念することとした。しかもそのための本拠をあの諸葛誕が殺害された越南菜飯店の二階の空き部屋にするという。トントン拍子に進む話に諸葛誕は呆気に取られた。
「犯人は現場に戻るというだろう? いずれお前を殺した犯人も私たちが探し出してやる。お前もいつまでもそのままではおれないだろう」
孫権が言うのに諸葛誕は、確かに、と得心する。人を殺した犯罪者が未だに大衆生活の場でのうのうと生きているというのは彼の義心にも許しがたい所業だ。だが、そこで諸葛誕はようやく、己が意固地なまでに正義と正当性を重んじる人物であったことを思い出したのであった。
◇
「んー、じゃあ、諸葛誕さんはもう死んじゃってるの……?」
「ええ、そうなりますね」
「あたしたち以外には見えないんだ?」
「今のところ、私の実感する限りではそうです」
「えっと……触れたりする?」
「ええ。どうぞ」
諸葛誕は右手のひらを小喬の方へ差し向ける。その上に小喬が自身の手を乗せると、あっと驚いたような表情をした。
「すごく冷たい」
「そうさ。諸葛誕の熱は陽の界のためのものじゃないからね。冷気は陰の界に属するもののわかりやすい特徴だよ」
「へえー」
感心したように何度も頷いている小喬を見ていた孫権は、彼女の頭越しに見える時計が示す時刻に気づいた。
「しまった! もうこんな時間か。龐統、諸葛誕、すまないが小喬に業務内容の説明を頼む」
「ああ、わかったよ」
「孫権様、どこ行くの?」
問われ、孫権は、パトロール、と叫んで外套と肩掛けのバックパックをひっ掴むとばたばたと実験室を出て行った。階段を降りる足音の途中で、うわ、という誰か別の声と、すまない、と返す孫権の声が聞こえる。
「中央図書館に行ったのさ」
「ふーん?」
龐統の言葉に小喬はやはり首をかしげたままである。彼は小喬の様子を気にも留めず、さて、と場の空気を変えるような声を発した。
「小喬殿。孫権殿はああ言ったけど、正直人手が増えるのは本当にありがたいんだよ。お前さんにはこれから、あっしらが今何をしているのかと、その危険性と、対策とをよくよく頭に叩き込んでもらうからね」
ぱちりと小喬は瞬く。諸葛誕が、いいのですか、と不安げに口にするが、構わないよ、と龐統は返す。
「素質があるようだ。だったらそれを使わない手はないよ。電話番なんてもったいない」
部屋の隅に置いてあった椅子に小喬を促すと、龐統もその向かいの椅子に腰を掛ける。諸葛誕もまた、空いていた席に着いた。傍らのミニテーブルをがたがた引っ張り寄せた龐統は真剣な眼差しで小喬を見据える。
「実は、そんなに時間があるわけじゃないんだよ」
低く発せられた声に、小喬はごくりと唾を飲み込んだ。
◇
三國市立中央図書館は、いびつな円形を描くこの三國市のほぼ中央に位置する。二百年程前に建てられた、元は領事館として利用されていた擬洋風建築をそのまま使用しており、本館は赤や茶褐色の目立つ中華風、渡り廊下を挟んだ別館は白味の灰色をした西洋風の造りをしている。周辺は公園として整備されており、広い芝生や季節の花が咲き誇る花壇の合間を縫うように市民が行き交う遊歩道が伸びる。
その入り口である大きな門をくぐり抜けて自転車を駐輪場に乱暴に停め、掛けねばならない二つの鍵を煩わしく思いながら孫権は手を動かす。ようやく立ち上がった彼は外套の裾を払って整え、肩にかかる赤い髪を少しだけ撫でつけて整えた。
時刻は昼時ということもあって人影はまばらである。開いている玄関から中に入り、少し奥へ進んだ先の返却カウンターに持ってきたバックパックの中から取り出した本を置く。
きょろきょろと周囲を見渡すが、孫権の目的は見当たらない。
整然と並ぶ本棚の列を覗き込むように渡り歩き、孫権はようやく行政関係の本棚がある一番奥の突き当たりに目当ての人物を見つけた。片膝をついて屈み込んでいるその人物は、抱えた蔵書を一冊ずつ丁寧に棚に戻していく。素っ気ない黒のエプロンがとても似合っている、と孫権は彼に会うたびいつも思う。
「于禁殿」
ささやくように声をかけると、名を呼ばれた彼――于禁は顔を上げ、孫権の姿を見とめてまなじりをすぼませて会釈をした。
「ああ、こんにちは」
「こんにちは。先日教えてもらった本、すごく面白かったです」
「そうですか、それはよかった」
立っている孫権は棚の前にしゃがんでいる于禁を自然と見下ろすかたちになる。他に人もいない本棚の突き当たりでこうしているとなんだか、この人を閉じ込めているような、むずがゆい気持ちになって、孫権もまた彼と同じようにその場にしゃがみ込んだ。
「これも面白そうだ。こういうの好きな人も多いですよね」
「なんですか?」
孫権の手許を覗き込んだ于禁はその示す本の背表紙を見て、ああ、と頷く。僅かに近くなった二人の距離に動じる孫権には気づかない。
「ダムはそうですね。その写真集もよく借りられています。子供からお年寄りまで」
「于禁殿は黄北ダムに行ったことはありますか?」
于禁は首を振る。三國市の北部山あいにある黄北ダムは、市の大部分の電力供給を担う大規模な水力発電所である。落差のある断崖からの放水は圧巻で、毎年秋になるとダム祭りなどのイベントも開催されており市外からの観光客も多く訪れる名所の一つであった。
しかし、興味がなければ于禁のような態度にもなるだろう。孫権もまた同様だった。
「そうですか、私もです」
「ええ」
そこで何気なさを装った会話が途切れ、孫権はこくりと唾を飲んだ。何を気にすることもなく本を棚に戻していく于禁の様子を見ながら、バックパックのストラップを握る手に力がこもる。今日の孫権には緊張するだけの理由があった。
全ての本をしまい終え于禁が立ち上がったのとほぼ同時に、孫権もすっくと立った。
「あの、于禁殿」
「はい?」
強張った孫権の声など知らぬ風に、于禁は首をかしげる。孫権はわたわたとバックパックから一枚の封筒を取り出した。
「じ、実は先日、映画の鑑賞券が当たったんです。今やってる徐大嶺の新作……、知ってますか?」
「……ええ、気になっていました」
その返答に、孫権は握りしめたチケットに落としていた視線を上げる。于禁はその切れ長の眼差しでじっと彼を見下ろしていた。ぶわりと孫権の頬に朱が差す。
「で、では、では、あの、よかったら、共に行きませんか! ペア券なんです! その、行く人が、いなくて……」
嘘である。孫権は初めから于禁を誘うつもりだったし、彼に断られたら兄と兄嫁に譲るつもりだった。
だが于禁は困ったように眉根を寄せた。その表情の変化に孫権はどきりとする。
「期限があるものだと……」
「あ、来月の十日までです!」
「そうですか。私は木曜が休みなのですが、あなたの都合が」
「わ、私はいつでも大丈夫! 木曜日でも!」
切羽詰まる、という表現にふさわしい孫権の様子をどう取ったのか、于禁は髭を生やした口許に緩く笑みを浮かべ、でしたら、と答えた。
「今週、行きますか? 早い方がいいでしょう。……あなたの気が変わらないうちに」
「は、はい! はい、行きましょう!」
気が変わるなんてそんな、大きな声で孫権がそう返した瞬間、本館中央に伸びる心柱に掛けられた柱時計が、ゴーン、と低く鳴り響いた。正午を知らせる鐘の音――于禁の休憩時間である。
「では木曜に……時間はどうしますか?」
「ご、午前十時過ぎからのがあります。あの、もしよかったら、そのあと昼飯でも」
「そうですね。では、九時半にここの玄関前で」
こくこくと何度も頷き返す孫権に于禁は、ではまたそのときに、と返した後、それから、と低くささやくように付け足して、自身の人差し指をその口許にそっと寄せた。
「館内では静粛に。では、ごゆっくり」
「は、はい、すみません……ではまた……」
会釈をしてきびきびと去って行く伸びた背を顧みて見つめながら、孫権は火照った頬をぱたぱたと手であおる。あんな風に柔らかな――まるでなりたての友人同士のような態度を取ってもらえるまで、二ヶ月と半分を要した。百鬼実験室の拠点を構えて程なくからである。
もちろん孫権がこの中央図書館を訪れたのはたまたまではない。三國市の地勢に基づき、“北部”を除きこれから最も大きな異変が発生するとするならば市の中央に位置するこの一帯以外にないと踏んだためであるが、その地で運命の出会い――孫権曰く――があるとはさしもの碧い眼も予想だにしていなかった。己より遥かに大柄な人物に対して、と龐統にはからかわれたが、彼に危険がふりかかることを孫権は見過ごすことはできない。今はまだ若干の猶予があるとはいえ、いつ何が起こるとも知れないのが怪異の恐ろしさである。孫権は彼の守り人たるために連日の“パトロール”を欠かすことはしなかった。あわよくば逢い引きに誘えたらという下心もないではなかったが。
目的を果たした孫権は先程自身が示したダムの写真集と、郷土史の棚から目ぼしい災害の記録が載った本を借りると、訝られないよう慎重に周囲に気を配りながら館内を見回った。二百年前の建造物は、時代を下るにつれ幾度かの改修や耐震対策を経て堅固な建物となっている。
来客用の読書スペースの奥には資料室が並ぶフロアに出るための扉があるが、ここを利用する者はあまり多くない。ほとんどの場合は館内で働く司書に目的を伝えれば適切な書籍を探し出してきてもらえるからだ。資料室内に乱雑に積まれた大量の資料の中から目当ての書籍を探し出そうとするのは骨の折れる作業である。
ノブを捻るとガチャリと金属音がやけに大きく鳴る。パトロールを始めてから何度もこのフロアにも足を運んではいるが、孫権は未だに慣れない。彼はそうっと扉を開き、恐る恐るというようにフロアに出た。書架のある本館メインスペースも静謐な空間ではあるが、このフロアにはいっそうの静寂がある。壁の天井付近にある明かり窓から射す外の陽光が、反対側にある資料室の扉を照らして揺らめいているだけの、まるで死んだような空間。
廊下の奥に孫権は目を凝らした。陽炎のような揺らぎが見え、その先の突き当たりに扉が一つある。真ん中に大きく赤い太文字で――三十メートル先の孫権からも見えるようにはっきりと――禁止入内と書いてあるのがわかる。
孫権の肌はぞわりと粟だった。彼は、そのようなものを見たのは初めてだった。これまでの二ヶ月半、少なくともこのフロアの一番奥は何もない壁だった。何度も訪れている中央図書館では、昨日まで増設工事をしている様子もなかったのに。
「…………」
孫権はゆっくりと歩き出した。彼の靴の音だけが響く廊下を違和感の方へ。
じっくり三十秒掛けて立ち入り禁止の扉の前に着く。目の錯覚でも、壁に書かれた落書きでもなく、確かに扉がそこにある。木製の古めかしい扉はところどころが掠れたように色褪せている。
ごくりと唾を唾を飲み込んだ孫権がその冷やりとしたノブに触れ、ゆっくり力を入れたとき――
「その先は立ち入り禁止ですよ」
「ふわあああ!!」
飛び上がった孫権は慌てて後背を顧みる。黒いエプロンが一番に目に入ってきて彼はぱっと顔を上げた。
于禁と同じくらい上背のある、司書の一人であろう男が、その秀麗な面に美しい笑みを乗せて柔らかく微笑んでいる。彼の黒く長い髪が明かり窓から射す光に縁取られてきらめいているのに孫権は息を飲んだ。
「お客様にはお立ち入りいただけません」
「あっ、すっ、すみません、あの、資料を探して……」
「どのような資料ですか? このフロアの書籍は雑多ですから、よろしければ私がお探しいたしましょう」
司書の優しい声が孫権を追い詰めていく。孫権は己の手許にそろりと視線を落とし、黄北ダム、と必死に言葉を発した。
「だ、ダムの、歴史です……」
「おや、それでしたら開架の郷土史の棚にあったはずですが……」
「ほ、本当ですか。私は調べるのが下手で」
「いいえ。わかりにくかったのでしょう。この部屋ももっとわかりやすくしておけばよかったですね」
にっこりと微笑む彼に返した孫権の笑いは乾き切っていた。これほどわかりやすく立ち入り禁止と書いてあるのにこれ以上のものがあるだろうか。
こちらへ、と言い置いてさっと歩き出す司書に孫権も慌てて続く。
メインフロアの壁際にある郷土史の棚から出された黄北ダムの歴史について書かれた資料を受け取りくだんの司書から貸し出しの手続きをしてもらった孫権は、足早に中央図書館を出て来てしまった。本当は于禁の休憩明けまで待ちたかったが、あの司書の目があるところにいつまでもいるのが恐ろしかった。
あんな狭い空間にあれだけ満ちた静寂の中を、彼は物音一つ立てず孫権の背後に立ったのだ。
◇
「それで、この水行っていうのが……」
「す、い、ぎょう……」
「ただいま!!」
指南の最中に大声を上げて帰ってきた孫権に、室内にいた三人は口々に、おかえり、とか、おかえりなさい、とか声をかける。
「どうだった? 今日の于禁殿は」
「素敵だった……ではなくて!」
からかう龐統に生真面目に返してから、孫権は三人の集まるテーブルの傍に自身の椅子をがたがたと引っ張ってくる。彼が前のめりになるのに合わせて、三人もまた身を乗り出して面を突き合わせた。
「やはりあの図書館は危険だ」
「何かあったのですか?」
「妙な扉があったのだ」
孫権が中央図書館での出来事を伝えると龐統は、薄気味悪いね、と述べた。
「だが、その後再び確認することができなかったのだ。あの男の目があって……」
「それなら、一度朱然殿に見てきてもらってはどうでしょう」
「あたしも行きたーい!」
ぴょんと小喬が手を挙げるのに孫権は瞠目し、次いで必死に首を振る。小喬は途端に不満げな表情を作った。
「なんでー? 孫権様ばっかりずるいよ!」
「ずるいじゃなくて、危険だと言っただろう! 何が起こるかわからないのだぞ」
「いや、孫権殿」
またしても対立しかけた孫権と小喬の間に龐統が割り込む。二人は揃って彼の顔を見やった。
「あっしや孫権殿は面が割れているし、諸葛誕殿では扉を開けるところから難儀だからね。朱然殿と小喬殿なら怪しまれずに行けると思うんだがね。それに……」
続ける前に龐統は一度沈黙した。皆が彼の次の言葉をじっと待つ。
「……これから先、単独行動はなるべく控えたほうがいい。いつ何が起こるかわからないのは、確かにそうなんだからね」
その響きの深刻さに、彼らは重く頷いた。
待ち合わせ場所である中央図書館の門前に現れた小喬を見、朱然は、うわ、という表情を隠しもしなかった。
「ほんとに小喬様だ……」
「えへへ、よろしくね! 朱然様」
事の次第は孫権から送られたテキストで知っていたが、実際に自身の目で見るまでは何かの間違いではないかと朱然は思っていた。あの聡明で眉目秀麗な刑事の、おてんばなパートナーが、彼に隠れてこっそりと自分たちの進める怪異の謎を解き明かす事業に加わったなどというのは。
「ほんとにやるんですか?」
「ひどいなー。ちゃんとお役に立つよ! 龐統さんだって、素質はあるって言ってくれたんだから」
「素質は、ですよね……」
げんなりと肩を落としながらも、朱然は孫権に小喬と合流した旨をテキストで連絡し、さっさと先に行こうとする彼女を慌てて追った。
「待ってくださいって!」
「早く行かないとお化けが逃げちゃうよ!」
お化けじゃないですって、と朱然は彼女を引き留める。
「そういうことを大きな声で言うのは、だめ。シー、です。誰が聞いているかわからないんですよ」
ささやく朱然に小喬ははっと何かに気づいたような表情をし、それからきゅっと眉根を寄せて握りこぶしを作った。
「うん、わかったよ。ごめんね。あたし、わかんないからいろいろ教えてね」
同じくささやき声で返す小喬に朱然は親指を立てて了解の意を返し、二人はいよいよ連れ立って図書館に入った。
小喬はこの中央図書館に来るのは初めてで、きょろきょろと忙しなく周りを見回している。朱然が漫然と読書スペースとは反対の位置にある本棚の群れに向かうのを追いながら、大きいね、と彼女はささやいた。そうですね、と返しながら、朱然は本棚の間を縫うように進んでいく。
「あたし、周瑜様の書斎でも目を回しちゃうから、こんなに本がいっぱいあるのすごくどきどきする」
「無理しないでくださいね。何かあったら、俺たちが周瑜殿に叱られます」
本棚の脇に置かれた椅子を示す朱然に、へーき、と返して、小喬は首をかしげる。
「奥の部屋行かないの?」
「近くに司書がいるんです」
さっと本棚の陰に隠れて、朱然は読書スペースに目配せをする。奥にある資料室へ通じる扉の脇、そこに置かれた雑誌ラックを整理する背の高い司書の姿があった。
「多分あいつです。髪も長いし……警戒してるのかも」
目を逸らせないかな、とぼやく朱然に、小喬はぴょこんと飛び上がって彼の肩をぱたぱた叩いた。
「あたしが本を探してるふりして話しかけたらいいんじゃない? それでなるべく遠くの本棚に連れてくの!」
「おお! 妙案!」
小喬の提案にぱちんと指を鳴らし、朱然は、それなら、と本棚を見上げた。
「あの本を探してください。えーっと……古代の遺産メソポタミア編」
彼らの身長よりも高い位置にある本棚に置かれた軽く五センチはある本の背表紙に小喬は、うひゃあ、と小さく悲鳴をあげる。朱然は苦笑しながら、それじゃあ行動開始です、と言っておもむろに歩き出した。スポーツ関係の棚を物色する彼を横目に、小喬は一つ深呼吸をすると彼女なりの大股で背の高い司書に向かっていく。
「あのう、ごめんなさい。えっとね、あたし、本を探してて……」
「はい、タイトルはなんでしょう?」
自身よりも頭二つ三つ分ほども上背のある司書を見上げて一所懸命に訴える小喬と、彼女に連れられた司書が資料室の扉の脇を離れるのを見て朱然はさっと歩き出す。早足で扉の前に着いた彼は、確かに孫権の言う通りやけに軋むドアノブを捻って、その奥のフロアに潜り込んだ。
――モバイルに朱然から届いたテキストとデータを見て、孫権は目を見開き、龐統と諸葛誕とはしかめ面を見合わせることになる。
『ありません』
とだけ書かれた内容に添付されていた画像には、資料室フロアの一番奥にある突き当たりの、つるりとしたアイボリーの壁が写るのみだった。
◇
見上げた自宅マンションの三階、自室の窓から煌々と照る灯りに小喬は慌てた。時刻は午後五時、このところは常ならば七時過ぎに帰って来れば早いほうの周瑜が既に帰宅している。管理人への挨拶もそこそこに、六階に停まっているエレベーターの到着を待つのも煩わしくて、彼女は一段飛ばしに階段を駆け上がる――体力だけは昔からあるほうだった。
「ただいま、周瑜様っ」
飛び込んだ自室は人の気配はあるが空気がひやりと冷たく、廊下の向こうのリビングの灯りは見えるのに、小喬の帰りを迎える周瑜の声がない。首をかしげてリビングに足を踏み入れた彼女は、その中央に置かれたソファーベッドに仰向けに転がっている周瑜の姿を見つけた。
「周瑜様……」
その傍らに膝をつき天井を向いたままの顔を覗き込めば、彼は目を閉じてすうすうと寝息を立てている。小喬の声も届かないほどの深い眠りだ。小喬は慌てて暖房をつけ、ソファーベッドに彼女が放り投げたままにしていたブランケットを周瑜にかけた。いつごろ彼が帰宅したのかは判然としないが、彼をこのまま寒い室内に寝かせておくわけにはいかない。
帰途に寄ってきた市場での買い物品をバッグごとキッチンカウンターに置いて、小喬は今度寝室から周瑜の愛用している毛布を抱えてきた。よいしょ、と小さく力む声も周瑜を覚醒させるには至らない。重い毛布をかけてやってようやく暖房も本領を発揮したかのように唸り始めた。出そうになったくしゃみを慌てて止めた小喬の変な顔が、テーブルを挟んでソファーベッドの反対にある大きな窓ガラスに映る。忍び足で歩み寄る彼女には、カーテンがレールを走る音も煩わしい。
どれほど周瑜は疲れているのだろう。濃くなった目の下のくまにそっと触れて小喬は切なくなる。少しでも長く眠ることができればいいのに。
今日、彼女は不思議な話を聞いた。周瑜が今携わっている駅爆発火災もまた、怪異の一端なのだという。龐統と諸葛誕とは努めてわかりやすい言葉を使って説明してくれたが、それでも馴染みのない話題は小喬にとって飲み込むのにとても苦労した。
三國駅爆発火災は経過なのだという。始まりは、昨年冬に市西部の山岳地帯で発生した大規模な雪崩と土砂崩れ、そして当地にあった複数の宗教施設がそれらに飲み込まれ多くの犠牲者が出た災害にあり、これは金行の異常であると彼らは言った。続いて春に発生した市東部にある森林で起きた広範囲の立ち枯れもまたそうで、春だというのに木々に葉はつかず、花も咲かないという事態は、明らかに木行の異常だという。
そして、三ヶ月前に起きた原因不明の駅施設での爆破事件と火災は火行の異常であり、すなわち陽気の爆発なのだ、と彼らはコピー用紙に鉛筆で書かれた太極図を示した。
「陽気が最も強い南がこれで崩れたのさ。残るは陰気のこもる北――恐らく、黄北ダムで何かが起こる。その何かは、まだ判然とはしないけどね。いずれ何が起こるにしても、太極が全く陰陽のどちらかに染まってしまえば、死は生に、生は死に飲み込まれる」
龐統の陰鬱な表情が事態の重大さに拍車をかける。小喬は一所懸命に考えたが、結局思い至ることは一つしかなかった。
「じゃあ、そのきんこうのほうかい? を止めることができたら、周瑜様ももう大変じゃなくて済むんだよね?」
その言葉に龐統と諸葛誕とはぱちりと瞬き、同時に互いの顔を見合わせ、それからおかしそうに笑った。
「そうさ。そういうことだよ。身近な人が助かる。これが一番の重大事さ」
「うん。じゃあ、あたしもいっぱいがんばるよ!」
小喬は気合を込めて拳を握った。大好きな周瑜をもっと慈しみ、気遣ってやりたい。その一心で手に取った――人から見ればうさんくさいと思われるような――チラシだったが、思いがけず最短距離を彼女は走ってきた。
――呼び寄せられたのかもしれない、とすら思うほどに。
小さな寝息を立てる周瑜のやわく、乾いた頬を指先でそっと撫ぜ、小喬は小さく微笑んだ。
「周瑜様、あたしが、助けるからね」
囁かれた声はおぼろげな暖気に滲んで、しかし一層強く大きく、彼女の中に波紋を拡げた。
◇
翌日の午前九時過ぎ、小喬が百鬼実験室に着くと、中には諸葛誕一人だけが残っていた。
「おはようございます、小喬殿」
「おはよう、諸葛誕さん! ねえねえ、みんなは?」
「特殊清掃の業務が立て続けに二件入って。帰ってくるのは午後になるようです」
背負ってきた鞄を傍らの籠に放り入れる小喬に諸葛誕は答える。ふうん、と彼女は相槌を打った。
「それって、死んじゃった人の部屋とかを綺麗にするお仕事だよね?」
「ええ、そうです。いろいろなことをするみたいですね。私は自室ではありませんでしたが、私もお世話になりました」
鞄からノートと筆入れを取り出した小喬はミニテーブルに諸葛誕を手招き、自身も椅子に腰掛ける。
「よし、みんなが帰ってくるまでお勉強しよ! 先生よろしくお願いします」
「ふふふ、はい。わかりました」
小喬のノートに不恰好に描かれた太極図に目を落とした諸葛誕は、ああ、と声を発した。
「小喬殿、こことここに丸がありませんよ」
その言葉に首をかしげる小喬に、諸葛誕は壁に掛けられた太極図のタペストリーを示す。
「あ、ほんとだ。丸があるんだ」
小喬は鉛筆で黒く染めた太極図の半分を消してまた塗り直していく。
「ええ、実はこれがとても大切なのです」
諸葛誕は彼女の手許を見つめながら、陰陽の円の中に出来上がった小さな二つの円を示した。陰中の陽、陽中の陰です、と彼は言う。
「いんちゅうの……?」
「はい。全ての物事ははっきりと陰と陽や、白と黒や、善と悪で分けられるものではないということを表したものです。陰の中にも陽があり、善の中にも悪がある。例えば、小喬殿は私からはとても明るく活発な方と見受けられますが、あなたにも悲しかったり、つらかったり、厭だなとか、めんどうだなと思う気持ちになることがきっとあるはずです」
「ある!」
小喬は大きく頷いた。そうでしょう、と諸葛誕は微笑み返す。
「それこそが大切なのです。全てのものはただ一面だけを見て語られるような構造にはなっていない」
「そっか……」
ぽつりと呟いて言葉を切った小喬だが、しばらく考え込むようなそぶりで口を尖らせた後、意を決したように顔を上げた。
「それってすごく、当たり前のことなんだね」
諸葛誕は瞬いた。真剣な表情の小喬に、彼はじっとその面を見つめ返し、ええ、と強く答える。
「その通りです」
――カタン。
入り口から軽やかな音がして、二人はそちらを振り返った。
そこに、白い道袍をまとい綸巾を頂いた、白い羽扇を持つ背高の男が佇んでいる。品良く生えそろった口ひげを口角と共に緩ませた彼は、決して珍しい色ではないはずの瞳をきらめかせて、慈愛に満ちた眼差しを彼らに向けていた。
二人は驚いたが、小喬が、お客様、と小声で言うのに諸葛誕も我に帰って、落ち着いてください、とその肩を軽く叩いた。
「私のことは見えませんから、私の言うのに続けてください。いらっしゃいませ」
「い、いらっしゃいませ!」
「ご用件はなんでしょうか?」
「ご用件は、なんでしょうか!」
男は羽扇でそっと口許を覆い隠し、ふふふ、とおかしそうに笑った。
「見えていますし、聞こえていますよ」
低く、しかし優しげな淡い声が二人の耳に響く。二人は肩を震わせ、互いに顔を見合わせた後、また男の顔をまじまじと見た。
「私の顔も、忘れてしまったようですね。諸葛誕」
「え…………」
小喬が、お友達? と尋ねる声にも答えを返せず、諸葛誕は男を見つめる。本当に、見覚えがなかった。ただ――何か、腹の中に何かが凝って、むかむかするような感覚がある。
意図せず、諸葛誕は自身の腹を撫でさすった。男がその動作に目を細めるのにも気を止めず。
そこへ小喬が、あのう、と声を発した。
「諸葛誕さんのお友達なら、おしゃべりする? あたしとお勉強中だったけど、お友達ならいいよ」
「いいえ……話をする時間は、あまり取れませんので」
男は俯きがちになって目線を僅かに落とした後、静かに面を上げた。
「じきに、陰気が蠢くでしょう。それもこれまで以上に強大に。そして恐らくはそれが最大にして最後の機会になります」
その言葉に二人は首をかしげる。なんのこと、と小喬が問うのに、すぐにわかりますよ、と男は返した。
「諸葛誕、あなたは本当によく耐え、よくがんばりました。あなたのしたことは必ず報われます。どうか、今少しの辛抱を――それでは」
「え……あ、お待ちを!」
言い残して、真白い道袍を翻した男は隙のない動きでまるで消えるように去って行った。慌てて部屋から飛び出した諸葛誕であるが、いつの間に階段を降り切ったのやら、その姿は既にない。窓際に駆け寄って外を見渡しても、その純白の道袍はどこにも見つからなかった。
「白い羽根、落ちてる」
拾い上げた小喬の言葉に諸葛誕は振り返る。
「お友達じゃないの?」
「いや、私には本当に見覚えが……ただ、なんだろう」
諸葛誕は今一度、自身の腹をさすった。
「なんだかすごく胃が重くなりました」
「お腹痛いの?」
「痛いとも少し違うような……」
首をかしげるばかりの二人である。
孫権、龐統、朱然の三人が帰ってきたのは午後三時を少し過ぎてからであった。諸葛誕と小喬から午前の客人について伝え聞いた彼らのうち、龐統はあからさまに表情を強張らせた――口周りを布で覆い隠し縁の広い帽子を被って目許しか見えないような格好ではあったが、誰にもそれは明らかであった。
「知り合いか?」
孫権に尋ねられた彼はそっと頷き、そんな男は地上に一人しかいないよ、とごく小さな声で返す。
「そいつが、諸葛亮さ」
孫権と諸葛誕とははっとする。朱然は、誰です? と訝しげに問い、小喬はといえば大きく首を捻るばかりだ。
諸葛誕と孫権、龐統が出会ったとき、火葬場で話し込みながら二人は彼ら自身の持ち寄った話を諸葛誕――いわゆる死者――との共有のため広く明らかにした。その中の一つが龐統が語った西の宗教施設の災害による倒壊と、当地で隠棲していた彼の友人の話である。特に西の地は陰気が多くを占めるため、均衡を保つには強大な力を持つ守人を必要とした。それが諸葛亮である。同姓である諸葛誕に龐統は彼のことを知っているか尋ねたものの、なにせ死後のてんやわんやで記憶が判然としない諸葛誕は首を振るよりない。それに対し龐統は落胆した。
「実は、くだんの山崩れのせいで生きてるか死んでるかもわからなくてねえ……」
その理由も聞かされてしまえば得心に足る。お気の毒に、と返す諸葛誕に顔を上げた彼は、死者に言われてもね、と気安い笑みを返した。
「だが、生きているとなれば心強い。話を聞くだに彼の存在は陰気の抑えであり対抗手段に相違ない」
ぱしんと手を叩く孫権だが、結局ここへ姿を現してすぐに行方知れずであることに思い至って、ああ、と肩を落とす。
「何か、陽気のGPSみたいなものは作っていなかったか」
「ないねえ。陰気のGPSさえ計画段階で頓挫したじゃないか」
「うう、そうだった……」
がらがらと部屋を覆い尽くすように置かれた機械の山を漁る孫権の後姿を見た小喬は、ねえ、と彼に声をかけた。
「孫権様、それなあに?」
「これは来たるべき戦いのために作った我々の武器だ。剣に……弓に……鉄鞭……この翳扇はどうしてこうなったのだったか」
「遠くからも攻撃に対処できるようにだろう?」
軽く長柄の扇を振って、孫権はそれを龐統のほうへ投げてよこす。それをぱしりと受け取った龐統も翳扇を左右に振りながら、もう少し勢いが、などとぶつぶつ言っている。
小喬は眉根を寄せた。
「攻撃って何の?」
「それはもちろん妖魔の……」
はた、と言葉を止めた孫権がまるで軋んだ機械のような動きで小喬を振り返る。
小喬は口をあんぐり開けて孫権を見ていた。
「孫権様、そんなに危ないことしてたの!?」
「くっ! 言っただろう、危険な仕事だと!」
「だってそんな剣まで持ち出して、そういう危ないだなんてあたし考えてなかったよ! やっぱり孫堅様に言った方が……」
小喬がそこまで言いかけたとき、二人の間に割って入るように大きな扇がバフン、と開かれた。虚を突かれた彼らが扇の持ち主を辿ると、朱然がニヤニヤ笑いながら、扇をもう一つバフンと開く。人の首から上であれば全く隠し切ってしまえるほどの大きさである。
「じゃーん。小喬様、実はこれも武器なんです。一振りで風を起こして妖魔を吹き飛ばすんですよ。見てくださいよここ、花柄」
「えっ? うわーっ、かわいい!」
気をそらした小喬に孫権はほっと胸をなでおろし朱然に目配せした。朱然もまたそれに応える。
「もし何かあったときのために、小喬様にもこれ、持っておいてほしいんです。でも、誰にも内緒ですよ?」
「うう……わかったよ。ひみつだね!」
二人して人差し指を立てて口許に持っていき、シー、とする様に孫権らはあっけに取られる。龐統は彼を肘で小突くと、お前さんは家族の名前を出されると弱いね、とからかった。
――ところで妖魔って何?
ひとしきり騒ぎ終えてようやく、小喬はそう尋ねた。最もな疑問であり、生命活動にも直結する喫緊の課題である。
龐統はタペストリーの太極図を示し、その白と黒の境を指先でなぞった。
「ここにいる連中が妖魔だよ」
「その……境目のこと?」
「そうさ、境目を彷徨うものたち。奴らはとても魅力的だし、そして蠱惑的だ。奴らはいつも仲間を探してる……境目を彷徨う仲間をね」
「なんだか怖そう」
小喬は眉根を寄せ、彼女の口許を拳で隠した。境目を彷徨うってどういうこと? と尋ねる彼女に龐統はおどろおどろしい声で、永久に生も死もない、と答える。
「あっしらは本当なら、生者のときも死者のときもあっしらなのさ。それがあっしらじゃなくなるのが境目だ。怖いだろう?」
小喬は自分が自分ではなくなることを考えたが、それがどういうことなのかがわからなかった。素直にそう言うと龐統は、“周瑜様”のことがわからなくなるのは? と聞いた。
「…………やだ」
「だろう? 奴らはそういう胡乱な寄り合いにあっしらを引きずり込もうってのさ。迷惑な話だろう?」
「めーわく! 巻き込まないでほしい!」
「そういう不届き者を退治するのがあっしらの仕事さ」
龐統の言葉に小喬の心は燃え立った。己から周瑜を奪うものは、きっと他の人たちからもその大切に思う人を奪おうとするだろう。それは彼女にとって到底許せる行いではなかった。
「あたしもやる!」
「よし、その意気だよ」
小喬と龐統が手を合わせる音が室内に響く。自身の額に手を当てた孫権の深いため息は熱気にかき消された。