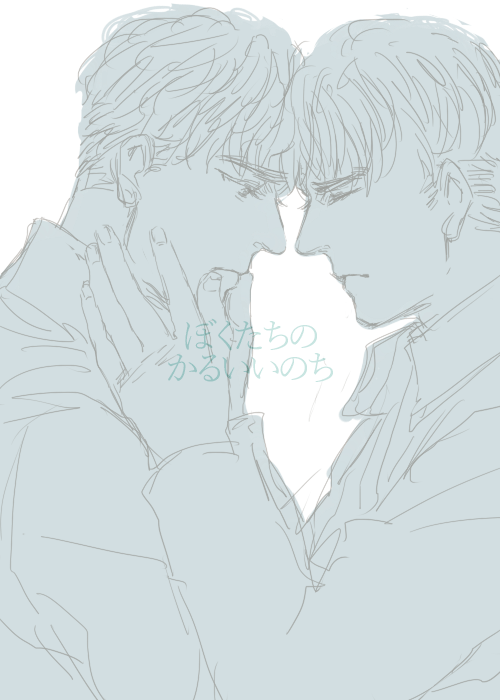曇り空もいいな、と思いながら、フィリップはロンドン郊外の街をのんびりと歩く。短期留学で初めて訪れたイギリスの空気は、想像していたよりももっと輝いて生き生きとしていて、まるで己はこのときのために今までがんばってきたのだと言わんばかりの充足感をフィリップにもたらした。
生来それほどせっかちなたちではないうえ、フィリップの前を歩いているのが杖をついた老人なのだからますます彼の足はゆっくりと動く。代わりに眼差しは忙しなくあちらこちらへと動き、この国の風景をつぶさに見ようと熱心だった。
しかし、そのきょろきょろ動く視界の隅で何かがかしいだ。目線を戻すと前を行く老人がよろめいているのが見える。フィリップは慌ててその背を支えた。
「だいじょうぶですか!?」
覚えたての英語を必死に繰る。若いフィリップにすればずいぶんと頼りなげに見える老人の様子だが、平気だよ、と返ってきた答えは明瞭だった。
「杖が挟まってしまったようだ」
フィリップが目を落とすと、石畳の上にぽきりと折れた杖の先が転がっている。
「Oh la la la…」
困ったような声に、ふふ、と老人が笑みをこぼした。フィリップが顔を向けたところに、彼もまたフィリップを見るように面を上げる。そうして、その目が驚いたかのように見開かれた。
「“ギブソン”?」
「え?」
他方、きょとんと目を丸くするフィリップの手に、老人の体がわずかに強張ったのが感じられる。“ギブソン”とは人の名前だろうか。フィリップの知っている中に、その名を持つ人はいなかった。
「えー、あーっと、人違いですよ。僕はジレです。フィリップ・ユーゴー・ジレ」
「……フィリップ……」
老人は目をわずかに伏せてフィリップの名を呟く。そうですよ、とフィリップは笑って、あなたのお名前は? と気安く尋ねた。
老人は呆気に取られた表情をしたが、すぐに小さく微笑んだ。
「僕は、トミーというんだ」
「ミスター・トミー?」
「ただのトミーだよ」
そう呼んでくれ、と老人は言い、やにわに彼のしわしわの手を自身の額に添えた。
「ああ、少し目眩がするようだ」
「メマイ……え、だいじょうぶ? お宅はここから近いですか?」
「ああ、五分くらいかな。僕の足では十五分かかるけれど」
「送りますよ」
フィリップが申し出ると彼は、本当かい、と声に喜色をにじませる。
「でも、君の用事は?」
「この辺を、えーと、散歩していただけなので。せっかくイギリスにいるんだし、紅茶を飲もうかなとは思っていたんですけど」
二、三度、トミーは瞬き、それなら僕が淹れてあげよう、と口にした。本当ですか、とフィリップは微笑む。きっとこの老人は話し相手を求めているのだとフィリップは察したし、実はフィリップもこの老人と会話がしたいと思っていた。なぜだか奇妙なことに、すんなりとそう納得することができたのだった。
トミーは高齢者用フラットの一室に暮らしていた。パートナーは五年前に他界し、子供たちはロンドンの街中に暮らしているという。フィリップが年齢を尋ねると、九十より先は数えていないな、と彼はおかしそうに笑った。ケトルに水を入れコンロにかける彼の様子を、何かあったらいけないから、とフィリップはその隣で注意深く見つめていた。
「すごいですね。九十歳になってもそんなに、んーっと……しっかりしてて」
「そんなことはないさ。石畳に杖を持っていかれるし、目眩もするし」
「ああ、杖。どうするんです? 僕、スペアを買ってきましょうか」
「スペアはそこにあるよ」
示されたテーブルの縁を見ると、確かに先ほど折れた杖とそっくり同じものが引っかかっている。ならいっか、とフィリップは頷いた。
「君は何か運動をしているのかな?」
「運動? 運動はしてないです」
「そうなのか? ずいぶんがっちりした体格だから」
「そうかな」
自身の肩回りや腰回りを不思議そうに見やっているフィリップを振り返り、トミーは目を細めた。
「君は外国から来た人?」
「そうです。フランスから。語学研修でこっちに。あとー……研究をしてるんです。第二次世界大戦の」
トミーの目がまたも驚きの色に染まる。この人はそんなにたくさん驚くことがあるのかな、とフィリップは小首をかしげた。
キッチンカウンターに片手をついた彼が、例えばどういうことを? と小さな声で問いかける。
「ド・ゴールのこととか、自由フランスとか、チャーチルやヒトラーの……」
そこまで言ってフィリップは、今己が会話している老人が齢九十を越えていることを思い出した。
「なんて言うか、その……いろいろあったとは思うけれど」
「西部戦線?」
「とかね。わかってほしいんだけれど、軽い気持ちで研究してるんじゃないんだよ。もちろんです」
「もちろんわかっているさ。君が何を言っているのかはわかりかねるけれど」
シュウ、とケトルが音を立てる。フィリップは気恥ずかしそうにそちらにちらりと目線を寄越した。ああ、とトミーは緩慢な動作で火を止める。それを持とうとした彼をフィリップは制し、僕が、と言った。傍らのティーポットに湯を注ぎ入れ、二つのカップと一緒にトレーに乗せてリビングのテーブルに運ぶ。トミーはゆったりとその後ろをついてきた。
二人で椅子に並んで腰かけたら、あとはトミーに任せることにする。彼は実に手慣れた所作でカップに紅茶を淹れながら、僕もいっとき戦争に参加したよ、と口にした。
「十代後半か、二十歳になったころだったか……とにかくもうずっと若いころだ。陸軍の僕のいた部隊はベルギー方面に投入されて、知っての通り戦線は崩壊してダンケルクの浜辺に追い詰められた。僕の部隊の人員は、市街地を移動する中ですっかり僕一人になっていた」
「……ダンケルクの戦い?」
ゆっくりとトミーは頷く。フィリップは己が調べた中にあったダンケルクの戦いの資料を頭の中に展開させた。フランス北部の港湾都市ダンケルクに追い詰められた英仏合計三十万人以上の兵士が、イギリスの民間のあらゆる船舶を利用して救出された奇跡のような撤退戦。
そっとフィリップのほうに紅茶の入ったカップを差し出したトミーは、フィリップの目から見ればとても沈痛な面持ちをしている。
「……それって、僕に話してもだいじょうぶなこと?」
「なぜ話してはいけないと?」
「だって……つらそうに見えます」
フィリップの言葉にトミーは動揺したようだった。カップを持つ手が震え、ほう、と彼はため息を吐く。
「浜辺で、君に……」
ふと目線を上げフィリップの顔を見たトミーは、目尻のしわをもっと深くして、ヘーゼルの瞳を不思議にきらめかせた。
「君のような、巻き毛の兵士と出会って、一週間僕は彼と行動を共にしていた。……運命共同体みたいなものだった。僕たちは互いに一人ぼっちで……二人とも、何をしても生き残りたかった」
言葉はなくとも僕たちは互いのことがわかっていた。
互いに互いの存在が不可欠で、互いが互いの命綱なのだと。
そして確かに彼は何度も何度も僕を助けてくれた。
手を差し伸べてくれた。
光を与えてくれた。
でも――言葉にしないとわからないことがあった。
それでも彼と共にいたあの一週間は――
「…………彼は死んでしまった?」
フィリップの問い掛けにトミーは眉根を悲傷に歪め、それから目を伏せた。
「……わからない。彼が“そう”なってしまったところを見たわけではないから」
けれど、彼はあの民間船に乗り込んでくることはなかった。トミーはそう言ってついに顔を俯けてしまう。フィリップは彼の傍に椅子を引き寄せ、そっとその肩を抱いてやった。
「つらいことならもう言わないで」
フィリップの言葉にトミーは緩く首を振った。
「何を利用して、何を犠牲にしても、僕たちは僕たち自身の命を守るために、いつも他の誰かの命を盾にした」
“いかなる犠牲を払っても”――あの名文が心に浮かぶ。トミーの頬を静かに涙が伝った。それを見ていたフィリップの目頭もまた熱くなり、鼻の奥がつんとした。トミーの悲傷が彼の肩を抱いているフィリップの腕を伝って、体内に一息に流れ込んできたかのようだった。
「でも、それは、仕方なかったことでしょう?」
「……仕方ない? ……仕方ないとは、どういうことなんだろう」
小さく呟かれたトミーの言葉に、フィリップは全身の血が冷えたような心地がした。その言葉はまるで氷の振る舞いをして、“何も知らない”フィリップを突き放しているような、お前に言えることは何もないのだと言われているような、そんな気にさえなった。
実際、フィリップには何もわからないのだ。戦争のことも、死地のことも、命のことも。
「他にやりようがなかったものかと今でも思うよ。けれどそんなものは、そのときになってみると僕の中から霧散して、ただ剥き出しの生きたいという欲望しかなくなってしまう。時折彼のことを思い出すよ。それでも時折だ。いつもじゃない。思い起こす彼は君みたいな目の色をして、君みたいな愛らしい口許で、君みたいな凛々しい輪郭をしていた」
老いたトミーはフィリップの腕の中で身じろぎし、その面を若者のほうへ向けた。触れてもいいだろうか、と彼は尋ねる。フィリップは一も二もなく頷いた。どうかそうしてほしかった。しわしわの手がその輪郭に覚束なく触れ、そうっと、恐る恐るというようにフィリップのふちをなぞってゆく。
トミーは、君の名前をもう一度僕に教えて、と言った。
フィリップがその通りもう一度名を名乗ると、彼はいよいよ歯を食いしばり、いい名前だ、と引き絞った声でそう返した。
「君の名前も、チャーチルの名前も、ヒトラーの名前も、僕は知っているのに、ただ彼の名前だけが、今でもわからないんだ」
――途端、ぶわりとフィリップの両目から涙があふれた。堰を切ったように流れ出るそれはまるで小さな滝のように、次から次とフィリップの頬を覆い尽くすように濡らしていく。
老人は驚いた様子もなく、彼のかさついた指先で若者の両目から止め処なく流れるものに触れた。そのあたたかさに、フィリップの心は急に悲しく、切なく締めつけられて、思わず嗚咽が漏れた。
悲しくて、悲しくて、悲しくて、溺れてしまいそうだった。
フィリップには、戦争のことも、死地のことも、命のことも、何もわからないのに。
“彼”の名前もわからなかったのに。
彼らはずっと、そうして抱き合っていた。
夕暮れが部屋の中を飲み込んで、淹れた紅茶がすっかり冷めてしまうまで。