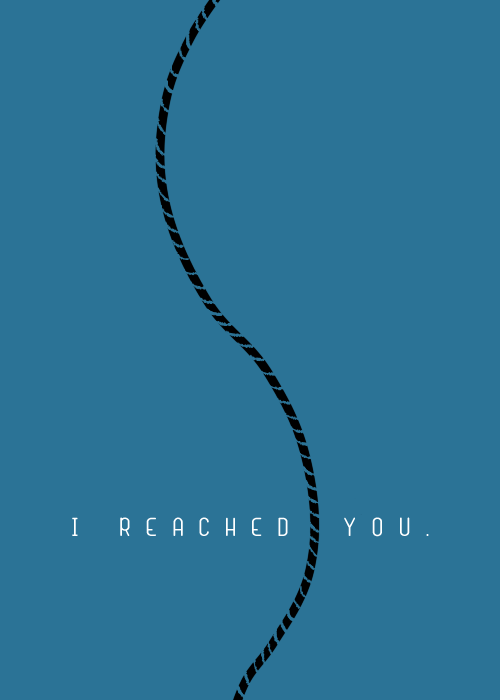僕は猫です。名前はギブソン。そして僕の隣で本を読んでいるのがヒト。名前はトミー。
僕たちは今、ペット同伴可のブックカフェなるお店にいます。名前はWater's Edge。トミーの友達のアレックス曰く攻めてる名前ですが雰囲気のいいお店です。主にいるのは犬や猫ですが、たまにうさぎやかごに入った鳥たち、小さな豚がいることもあります。そしてお店の中ではみんなおとなしくいい子にしています。もちろん僕もそうです。
そして当然のようにトミーはこのお店がお気に入りです。このお店のミルクティーとチキンレタスベーグルサンド、バタービスケット、それからこのお店いっぱいに詰まる本のにおいと、壁一面に並んだ本棚の品揃え。
「お待たせしました、ストロベリージャムサンドです」
そうそう、トミーはこのお店のストロベリージャムサンドもお気に入りです。そして一番が、このストロベリージャムサンドを持ってきてくれた店員さんなのです。
「…………ありがとう」
ぺこんと軽く頭を下げただけのトミーは、もしかしたら他の人には愛想がないように見えちゃうかもしれないけれど、シェアメイトのジョージやピーターといるときもあんまりしゃべるほうじゃないし、なにより気になっている店員さんの前ではほんのちょびっとだけ恥ずかしがり屋さんになってしまうのです。少し茶色っぽい緑色の目と巻き毛を持った店員さんはちゃんと目を合わせられないトミーににこっと笑いかけ、それから隣の僕に向かってパチリとウインクをしました。この人はトミーみたいに奥手な人ではなさそうです。それよりトミーはさっきの店員さんの笑顔を見ていないんだから損ばっかりしています。
トミーはカウンターに戻っていく店員さんの後姿をじいっと見つめたあと、先に頼んでいたミルクティーを一口飲んで、おいしい、と本当に小さな声で呟いて、それからストロベリージャムサンドに手をつけました。トミーがほっぺをもぐもぐさせながら食べているとなんでもおいしそうに見えるから不思議です。猫の僕には食べられないのが本当に惜しいです。
そんなことを考えながらしっぽを揺らしていたら、カウンターからまたあの店員さんがお皿を二つ持って出てきました。彼はなぜかまっすぐ僕たちのテーブルに向かってきます。僕はトミーを見ました。注文が全部届いたと思っていたトミーはびっくりしたみたいにほっぺを膨らませたまま店員さんを見つめています。
僕たちのテーブルに来た店員さんはやっぱりにこりと微笑みました。
「もしよかったら、こういうのだめじゃなかったら、これ、猫さんに、お店からサービスしたいんだけど……」
「あ、えっと……うん、大丈夫。ありがとう」
トミーがそう答えて、テーブルの僕の前に置かれたのは、魚の形のビスケットとお水でした。うわあい! 僕がぴょんとテーブルに飛び乗ってにゃんと一声鳴くと、店員さんは、いつも来てくれてありがとう、と言いました。そんなそんな! 僕はトミーについてきてるだけだよ! もちろんこのお店も好きだけどね!
万感の思いを込めてビスケットをほおばる僕の耳に、トミーと店員さんの会話が聞こえます。わざわざありがとう、ううん、こちらこそいつもありがとう、そんな、僕は、ここのミルクティーが好きで。
「今日のミルクティー、どうだった?」
「え? お、おいしいよ。すごく。うん、いつもより、もっとおいしい」
「ほんと?」
大きな声に驚いて僕は顔を上げました。でも二人はそんな僕に気づいていませんでした。トミーもです。トミーがこのとき気づいたのは多分、店員さんがぱっと明るい顔をして、少しだけほっぺを赤くして、声を上ずらせた理由です。トミーはとても頭のいい人なのです。
「…………」
「今日の、僕が作ったんだ……」
「そっ、そうなんだ……!」
「んふふ……ありがとう」
「ううん、こちらこそ、ありがとう……」
下唇を上唇で食む店員さんの仕草はトミーをめいっぱい照れさせました。僕もそんなトミーを見てひゃああと照れてしまいました。トミーはすごいです。何も知らないのにすんなり正解に辿り着けるんですから。
照れてしまって仕方ない僕たちを助けるようにお店のドアベルが鳴りました。店員さんはもう一度、ありがとう、と言って今来たお客さんの方へ向かいます。僕が覗き込むと、いつも茶色と白黒のうさぎを連れて来るおばあさんがいました。おばあさんとうさぎたちは店員さんに挨拶をしています。トミーに目を戻すと、彼は首まで真っ赤にして、やっぱり真っ赤なストロベリージャムサンドをほおばっていました。僕は焦げ茶の猫なので真っ赤にはなれないけど、焦げ茶をいっそう焦がしてビスケットを食べました。
帰り際にいつものバタービスケットを三つ注文して、トミーはお店の奥にあるカウンターのそのまた奥、キッチンに立つ店員さんを見ています。腕の中にいる僕も。店員さんの隣で店長さん――すごく背の高いおじさん――が、うさぎのおばあさんのためにミルクティーを淹れています。
「バタービスケットもすごくおいしい」
「ほんと? ……バタービスケットはいつも僕なんだ」
店員さんがオーブンに向けていた目をトミーに向けます。トミーはむっと口を尖らせました。照れ屋さんになってしまうときのトミーのいつものくせです。また正解でした。店員さんは緑色の目をゆっくり瞬きさせて、相変わらずトミーを見ています。それは僕にはとても素敵なアイコンタクトに見えました。きっとトミーにもそう見えたことでしょう。
でも背の高い店長さんが視界の傍をかすめていったので、二人のアイコンタクトはそのうち外されてしまいました。店員さんはほかほかになったバタービスケットをオーブンから取り出して紙袋に丁寧に入れていきます。
トミーはお金と引き換えにその紙袋を受け取りました。僕は、受け取ったトミーの手と、店員さんの手がちょっとふれ合ったのを見てしまいました。ひゃああです。
「じゃあ、また……」
「うん、また来てね。猫さんも」
「あ、ギブソンっていうんだ」
店員さんは目をぱちぱちさせました。僕がにゃあんと鳴くと、猫さんの名前? と彼はトミーに尋ねます。トミーは頷きました。
「拾ったとき、横にでっかく“Gibson”って書かれた看板が落ちてたから」
「それでギブソン?」
素敵だね、と店員さんは笑いました。トミーも嬉しそうに口をもごもごさせます。僕はもう一度、にゃあんと鳴きました。
トミーはそれから店員さんのお名前を聞きたかったんだと思うんだけど、お客さんがいっぱい来たので結局お店を出てきました。でもまた次に聞きに来ればいいのです。きっと次はそれができるはずです。
ほかほかのバタービスケットの香ばしいにおいのする、緑が多い家路です。この街はいつもそんな感じです。小さな人たち、若い人たち、中くらいの人たち、歳を取った人たち、いろんな人たちがいます。
僕たちが歩いていると、公園の向こうから若い人たちが五人、楽しそうに歩いてきました。その中の一人に、僕も、それにトミーも見覚えがありました。なんなら、トミーの友達です。その人もトミーと僕に気づいて、ヘイ、と軽く手を挙げました。
「トミー、またギブソンとデートか?」
この人がアレックス。トミーの音楽好きな友達です。いつもギターを抱えていて、僕は一回それを引っかいちゃってすごく怒られたことがあります。
アレックスは友達に何かうにゃうにゃ言ってその人たちと別れ、トミーのところへ走ってきました。
「なあ、お前ギグ来ない? 俺たちみたいな若いインディーズバンドが集まってやるんだけど、土曜日にMoleで」
アレックスはトミーにぺらぺらの紙を二枚渡しました。そうして僕に向かってウインクします。右目と左目をぱちぱち。僕はにゃあんと答えました。
「ギブソンと一緒に」
「猫は無料にならないのか?」
「そうなんだよ、悪いね」
こてんと首をかしげたアレックスは、冗談だよ、と笑います。はあ、とトミーはため息をつきました。
「僕はいい。たくさんいる君の仲間に渡せば?」
「もう渡してるよ」
アレックスの答えにトミーは肩を竦めました。
「誰かいないの? 気になってる奴とか、感謝したい母親とか。これで俺のノルマ最後なんだよ」
「感謝したい母親に聴かせられるような音楽なのか?」
「お前の母親がお前くらいの歳にはもう世の中ロックに染まってたし、ロックはなんでも歌にする」
トミーがアレックスの手からぺらぺらの紙を受け取って、いくら、と尋ねると、アレックスは、いーよ、と楽しそうに笑いました。顔をくしゃくしゃにして笑うアレックスは愛嬌があって、みんなアレックスのことを好きになります。
「お試しってことで! 俺たちはこれ、HIGHLANDERS。一番最初なんだ。六時半からの演奏だから、六時までには来いよな」
じゃあな、とアレックスは僕の頭をごしごし撫で、トミーの肩をぽんぽん叩いて、去って行きました。
僕はトミーを見上げます。トミーはじっとぺらぺらの紙を見つめていたけど、そのうち上着のポケットにそれを突っ込んで歩き出しました。なあん、と僕が鳴くと、トミーは僕を見て小さく微笑みました。
あの店員さんを誘えばいいのに、と僕は思いました。
僕たちがシェアフラットに帰ったときにはもうジョージもピーターもリビングにいて、おかえり、と僕らを迎えてくれました。床に下ろされた僕は玄関マットをふみふみしてから廊下を小走りしてソファに坐っているジョージの膝に飛び乗ります。隣に坐っていたピーターが僕を撫でてくれました。
トミーがバタービスケットをテーブルに置くと、二人は、ワオ、ありがとう、と口々に言いました。二人もWater's Edgeのバタービスケットが大好きなのです。そのまま食べるのも好きだけれど、出来立てを二つに切って、ジャムを挟んで食べたり、紅茶に浸して食べたりするのも大好きです。
トミーは二人に、ギグに行かない? と尋ねました。ちょうど二枚あるし、と言うと二人はバタービスケットをもぐもぐしながらぺらぺらの紙を覗き込んで、ああ、ごめん、と言いました。
「僕ら土曜日に一回ウェイマスに戻るんだ。日帰りではあるんだけど、六時には帰って来れないかも」
そう言うピーターにトミーは、そっか、と返しました。ピーターたちは同じ海岸の街から都会に出てきた人たちなのです。
ジョージはトミーに、あの人を誘えば? と言いました。あの人とはもちろん、店員さんのことです。二人もトミーが店員さん目当てにお店に通っていることを知っています。
うう、とトミーは珍しくぐるぐるしながら、二人の坐るお向かいのソファーに腰を下ろしました。
「いいじゃん、ちょっと賑やかなほうが緊張しないと思うよ」
僕ののどを撫でながらジョージは続けます。ジョージの指先はやわらかくて僕は大好きです。
「……断られるよ」
にゃおん! やわらかいジョージの指先を振り切って、僕は大きく鳴きました。あんな素敵なアイコンタクトをしておいて、断られるなんてあり得ませんから。
「ほら、ギブソンも、いけるよトミー! だって」
ピーターが言うのに、トミーは僕を見ました。僕はもう一度、にゃんと鳴きました。
大丈夫かな、とトミーの目は言います。大丈夫だよ、と僕の猫の目は返します。ロマンチックなやつじゃないけれど、僕たちもアイコンタクトができるのです。
「…………行ってくる」
「え、今?」
「気をつけてね」
勢い立ち上がったトミーは駆け足でリビングを出て行ってしまいました。僕はあわててジョージの膝からぴょんと降りてトミーを追っかけましたが、ドアは僕の鼻先で閉じられてしまいます。ピーターの手が僕をひょいと抱えました。
「残念、ギブソン。ミルクポトフ作って待ってようね」
僕はひげをたらしてにゃんと鳴きました。自分で食べられないおいしいものを作ったって……
三十分もしないうちに、トミーは真っ赤になって、息を切らして帰ってきました。多分帰り道にいっしょけんめ走ったのでしょう。トミーは僕たちにブイサインを向けました。僕たちはわっと湧き上がり、まるで戦いに勝ったみたいでした。その夜の食卓でジョージとピーターが作ったミルクポトフをめいっぱい頬張るトミーはやっぱりすごくおいしそうで、自分で食べられなくてもお腹いっぱいになるんだなって僕は思いました。
金曜日の夜、僕とジョージとピーターはトミーのおめかしを手伝いました。二人は明日いないから、今日のうちに明日トミーが着ていく服を決めるというのです。お金もあんまりないので――だってトミーはWater's Edgeにつぎ込むので忙しいですから――トミーの持っている服から合わせるしかないのですが。
きっとパブの中は暑いから脱げるようにしないとだけど、外は夜になるとまだ少し寒いから羽織れるものもほしいんじゃない? 動きやすいパンツがいいと思うよ、デニムは大変そう。ジョージとピーターはいっしょけんめトミーにアドバイスします。トミーもうんうんと聞いています。僕は、トミーは多分何を着てても格好いいからなんでもいいやと思って、あくびしてしまいました。
結局トミーは、いつもトミーがしている格好みたいな格好になりました。二人も、いつものトミーが一番だ、と言って嬉しそうに笑います。トミーは口をもごもごさせてニヤリとしました。やっぱりトミーは正解でした。
土曜日の五時半、トミーと店員さんの待ち合わせの時間はもうすぐです。僕はお留守番です。多分ジョージとピーターの方が先に帰ってくるだろうので、二人が帰ってくるまでのんびりしています。
トミーはずっとリビングをうろうろしていたけど、そのうちぎゅっと拳を握って、じゃあ、行ってくる、と声を強張らせて言いました。にゃん、と僕は返します。僕たちは目を合わせました。勇敢なトミーへのエールです。
エントランスに向かうトミーの後ろを僕はついていきます。トミーはいつもの靴を履いて、僕を振り返りました。
「行ってきます」
「にゃーん」
行ってらっしゃい、楽しんできてね、の気持ちを込めて、僕は大きく鳴きました。
◇
少し前に出て行ったギブソンの飼い主さんが息を切らして戻ってきて、僕はびっくりした。忘れ物をしたのかな、と僕が首をかしげながら駆け寄ると、彼は僕のほうへ腕を伸ばして、僕の目をじっと見つめてきた。
僕は彼のヘーゼルの目が好きだった。初めて彼と目が合ったとき、射止められて震えてしまったくらいだ。フランスから渡って来た僕がこのお店で働き始めてから一月経ったくらいのことで、以来ギブソンと二人で来てくれるギブソンの飼い主さんに会えることを僕は毎日楽しみにしている。
彼が持っているのはチケットだった。僕がそれを指し示すと彼はこくんと頷き、友達がギグするんだ、と言った。
「Moleっていうパブで……若手のインディーズバンドと一緒に……友達はHIGHLANDERSっていうバンドで……六時半からの演奏なんだって」
「うん……」
僕はちらりと受け取ったチケットに目を落としたけれど、すぐにギブソンの飼い主さんに目線を戻した。彼から目を離していたくなかった。彼が何かを言う前に、僕にはすぐわかった。ギブソンの飼い主さんの目は、僕と一緒に行きたい、と言っている。そしてそれは僕も同じだった。土曜日の六時半……
「て、店長に聞いてみる」
ギブソンの飼い主さんはまた一つ頷いた。僕がお店の奥に戻ると店長が腰に手を当てて目を細めている。
「店長、土曜日、六時で上がってもいいですか?」
「もちろん構わんよ。……ところで土曜日は午後から店を休みにすると先週伝えたはずだが?」
「あっ」
そうだった。ギブソンの飼い主さんをちらちら見ていて話半分だった。僕がはにかむと店長は呆れたみたいに笑ってため息をついた。そうして彼が後ろを顎で示すので僕は、ありがとう、と言ってギブソンの飼い主さんのところに戻った。
「土曜日、午後からお店休みなんだった。行けるよ」
ギブソンの飼い主さんはほっとしたように笑った。僕もなんだか嬉しくて笑い返してしまう。ギブソンの飼い主さんももっと口をほころばせている。
「じゃあ、六時に……Moleの前で」
「うん。わかった」
僕とギブソンの飼い主さんはまたじっと目を見合わせて――僕が、ありがとう、と言うと、ギブソンの飼い主さんは、こちらこそ、と返してくれた。こちらこそ、に、こちらこそ、と返したくて僕はやっぱりはにかんだ。
ギブソンの飼い主さんは、じゃあ、とぺこりと頭を下げると、頬を赤らめてお店を出て行く。僕もその後を追いかけて、去って行く店員さんに、またね、と大声で言った。ギブソンの飼い主さんも、また、と返してくれた。
「…………」
嬉しくて頬が緩むのを押さえられない。僕は手の甲で頬をごしごしこすった。
土曜日の六時、Moleの前は人であふれていた。インディーズのギグでもこんなにたくさん人が来るんだ、と僕は圧倒されてしまう。実は、フランスにいたころも、イギリスに来てからもこういうギグに来たことはなくて、初めての空気に僕はそわそわしている。
ギブソンの飼い主さんはまだ来ていないのかな、ときょろきょろ辺りを見回した僕の目に、その彼の姿が飛び込んできた。彼もちゃんと僕を見ていた。嬉しくてやっぱり頬が緩む。
「こんばんは」
「こんばんは」
ありふれた夜の挨拶におかしくなってしまって僕たちは同時に吹き出した。ギブソンの飼い主さんは僕の前に来ると、今日はありがとう、と言った。こちらこそ、と僕は返す。僕たちは同時に歩き出した。でもすぐに人込みに流されそうになって、ギブソンの飼い主さんがさっと僕の手を取った。
僕が彼を見ると、彼の目が、離れないで、と言った。僕は頷いた。ギグに行くだけなのに、不思議な緊張感があった。僕の手が汗ばんでいませんように、と思った。
スタッフにチケットと鞄の中を見せて、僕たちはまた手を繋いで歩き出す。
「友達は、僕に渡したのが最後のノルマだって言ってたから、そんなに人が来ないのかと思ってた」
「すごく人気なんだね。みんな音楽に熱心だ」
フロアに入ると、途端に熱気がぶわっと僕たちの体を包んだ。ギブソンの飼い主さんが僕の手をぎゅっと強く握ってくる。僕も同じように握り返した。
バーカウンターの隅に隙間を見つけて僕たちはそこに滑り込んだ。目の前のスタッフが、何飲む? と聞いてくる。僕たちは互いに目を見合わせ、ギブソンの飼い主さんが、ギネスを二つ、と言う。スタッフは返事するとすぐに出してきた。きっとみんなこれを頼んでいるのかも。
僕たちはグラスを軽く掲げて目を合わせた。ぐっとあおったビールは今まで飲んだ中で一番おいしかったかもしれない。
テーブルにグラスを置いたギブソンの飼い主さんは、カウンターの奥の棚にあるお酒のラベルを見ているみたいだった。僕もそれに倣う。瓶は暗い色ばかり、ラベルはカラフル、でも今はお店にあふれるライトの七色に輝いている。僕はちらりとギブソンの飼い主さんを見た。
彼のきれいな目も七色に輝いている。
その目が僕を見て、細められる。ギブソンの飼い主さんは小首をかしげ――
どん、と体を震わす音がした。
僕たちはステージを見た。あ、とギブソンの飼い主さんの小さな声が聞こえる。僕は彼の方を見た。
「友達?」
「うん」
「どの人?」
「フロントマン、ギター抱えてボーカルしてる」
「前に行こうよ」
今度は僕がギブソンの飼い主さんの手を引いた。彼は少し遠慮がちだったけれど、それでも一緒に前に来てくれる。
HIGHLANDERSは人気みたいで、結構ステージの前に来ている人たちがいる。僕たちは前から四列目のあたりでステージに立つHIGHLANDERSを見上げた。
若々しく少し高い、情熱的な声でギブソンの飼い主さんの友達が歌っている。切なげにかすれたり、パワフルに叫んだり、熱心につま先を見つめるみたいにギターを弾いたり、楽しそうにメンバーの人たちと顔を見合わせたりしている。時々、ギブソンの飼い主さんの友達はギブソンの飼い主さんとその隣にいる僕を見て目じりを緩ませたりもした。
HIGHLANDERSはいろんな歌を歌った。ところどころ僕にはわからないフレーズも出てきたけど、メロディーや演奏がすごく好きだと思った。恋の歌や人生の歌、家族の歌、誰かを励ます歌、スノウ・パトロールのカバー、そして最後の曲は、何を歌った歌だったんだろう。
その問題を見つけたところで
答えを出すことさえ難しい
僕たちはみんなどこへも行けない
僕たちはみんな海の底にいる
冷たい水面に涙を溶かして
泣いてないって笑うんだろう
剥き出しの歯が折れたって
腕がちぎれたって手を振るさ
喉がつぶれたって叫んでやる
君を失った千年 黒い影
僕はここに立っている
流星が僕の腹を貫いても
僕はここに立っている
――HIGHLANDERSの歌が終わって、僕らはまたカウンターに戻ってきた。ギブソンの飼い主さんが僕の手を引いていた。僕らはまたギネスを頼んで、ちらりと目を合わせた。
「……かっこよかったね、友達」
「そうだね」
僕が言うとギブソンの飼い主さんは少しだけ口を尖らせた。彼の目が僕をじっと見ている。僕はなぜだかその七色に輝く目の緑色と黄色だけをどうしても見たかった。――ここじゃないところへ。僕がそう思ったとき、ギブソンの飼い主さんはまた僕の手を引いて、カウンターから離れようとした。
「トミー!」
僕の反対側からどん、と誰かがぶつかるみたいに寄ってきた。見るとギブソンの飼い主さんの友達が僕の肩に腕を回してニヤリと笑っている。トミー?
ギブソンの飼い主さんが、おい、と咎めるような声を上げた。
「いいじゃん。ちゃんと来てくれてよかったよ。お前のことだから、ジョージとピーターにチケット譲るかもって思ったけど」
「二人は帰省」
「帰省しなかったら譲るつもりだったな。この人が感謝したい母親?」
友達が僕を示して言う。ギブソンの飼い主さんは、違う、と言って僕の肩に回っていた友達の腕を振り落とした。彼は僕やギブソンの飼い主さんよりも少しだけ背が高かった。
「ハイ、アレックスだ」
「フィリップだよ」
「よろしく。……トミー? 何だその顔?」
友達――アレックスと握手して振り返ったら、ギブソンの飼い主さんが目をまんまるくして口をきゅっと引き結んで、変な顔をしていた。でも僕にはすぐにその変な顔の理由がわかった。それは僕にも思い当たることだったから。
「……いや、なんでもない。そう、……僕はトミーだ」
「うん。僕はフィリップ」
二人して恐る恐る出した手を握り合い、また目が合う。おかしな気分で、でも僕たちの間にある空気はどこか甘やかだった。おいちょっと、って僕の後ろでアレックスが声を上げるまでは。
「なんで自己紹介? あれ、今ここで初めて会ったの?」
僕たちは首を振った。そうするとアレックスがますます訝しげな顔つきになる。ステージで見た凛々しい表情とはまた違う、とてもコミカルな姿だ。
おい、トミー、彼は強めの語調でギブソンの飼い主さん――トミーの名前を呼んだ。トミーはため息をついて、名前を初めて知った、と言う。
「今? 初めて? いつ知り合ったんだよ。ネットの友達とかか?」
「ネットじゃないよ……二か月くらい前かな」
オーマイゴッド、とアレックスの口が動く。誰かがそう言うのを映画やドラマ以外で初めて見た僕は少し感動してしまった。
アレックスは、トミーは奥手すぎるとか、二か月も何してたんだよ、とかいろいろ言っていたけど、トミーは耳だけ彼に傾けてビールをぐいぐい飲んでいた。そんな二人が面白くて僕は黙って二人を交互に見ていたんだけど、しばらくして別の誰かがアレックスに声をかけてきた。白髪交じりの髪の毛の、きりっとした女性だ。
「あ、こんにちは。こないだはどうも……すみません、今ちょっと友達と」
「いいよ、アレックス。大事な用事だろ」
その人に申し訳なさそうに断りを入れるアレックスを制して、トミーは僕に目線を向けてその場を離れようとした。アレックスが、何だよ、もう少しいなよ、と言うけれど、トミーはやっぱり首を振って僕を見る。僕もこくりと頷いてアレックスを振り返った。
今日はありがとう、かっこよかった、と言うと、アレックスは少しだけ寂しそうな表情をした後に顔をくしゃくしゃにして笑って、また誘うから来てよ、と返してくれた。
「楽しみにしてる。最後の曲、すごくよかった」
「嬉しいな。Strandedっていう曲なんだ」
僕は何度も頷いた。あれは誰かのままならない歌だったんだ。
それからトミーも素っ気なく、じゃあね、と言って、僕たちはまた人込みをかき分けてパブを出た。時計を見ると七時半。この街の空はもう真っ暗だ。でも僕は……
「僕のフラットに行こう」
「え?」
「ここからそんなに遠くないよ、歩いて十分くらい。ギブソンもいるし、きっとシェアメイトももうすぐ帰ってくる頃だろうし……二人も君のバタービスケットが好きなんだ。きっと喜ぶ」
ぽかんとしてしまった僕を見てトミーがまくしたてる。僕はそんな彼がおかしくて口をもごもごさせて笑った。
僕は、僕たちの繋がれていないほうの手を取った。トミーが僕をじっと見る。トミーは喜ぶ? って思いながら見つめ返したら、トミーが顔中、耳まで真っ赤にして唇をかんだ。
◇
今日も僕、ギブソンキャットとトミーはWater's Edgeです。
トミーはフィリップとずいぶん仲良くなりました。僕らがドアベルを鳴らすと、振り返ったフィリップが今まで以上、とってもとっても嬉しそうに笑うくらいに。
「いらっしゃい、トミー、ギブソン」
フィリップはすぐに歩み寄ってきます。トミーは席に僕だけ下ろして、四角くて薄い板を持ってフィリップを待ってます。
「アレックスからテキストが届いたんだ」
それを見せるトミー、覗き込むフィリップ。
「YouTubeにまた曲をアップしたみたい」
「すごいね」
「すごいけどさ……」
トミーが板を指差すと、フィリップの目がそこに動きました。少しして、これトミーのこと? とその目がからかうような色でにこりと弧を描きます。トミーは口をつんと尖らせて、さあね、なんてとぼけました。
僕はにゃーんと鳴きました。二人してなんのお話してるの? 僕に内緒で!
そうしたらフィリップがにこにこ笑って僕の前にかがみ込みました。
「アレックスがね、トミーは相手の名前も知らないで二か月も駆け引きを楽しんでたおかしな友達だって」
「この曲、デビューアルバムの先行シングルになるんだって」
「えっ? ほんと?」
ぱっと立ち上がったフィリップがまた板を覗き込みます。もー! だからそーやって僕の見えないところで!
ぴょんとテーブルに飛び乗ってにゃんと強く鳴いた僕に、トミーは少しだけ首をかしげながら笑いました。そして、僕にもその板を見せてくれました。
「アレックスって、百年とか、千年とかが好きなの?」
「さあ?」
板の中の四角の中ではアレックスが、ギターを抱えて歌っています。僕が引っかいちゃった傷もそのまま残っています。アレックスのきれいな歌声も僕は大好きです。
君が誰だって関係ないんだ
僕らの目が合った それだけで十分だ
百年 頭がおかしくなるくらい願ってた
今日 僕らがこんなふうになること
いっしょけんめに歌っているアレックスを見て、僕は思いました。
たくさん、たくさんの人たちに、アレックスの歌が届きますように、って。