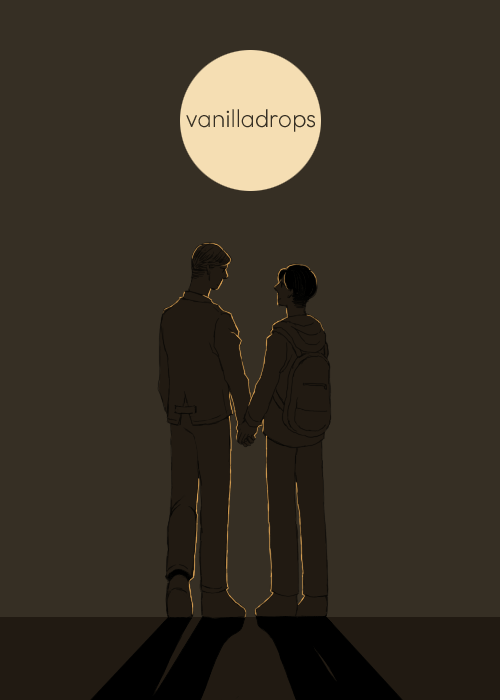さらさらの金髪はいつも輝いて光を透かしているみたい。青に灰色を混ぜたような深い瞳の色は朝焼けに照らされる海の影のよう。彫りが深いからできる目許の濃い陰の思慮深さ。くっきりした二重。眉間から正しく伸びる鼻すじ、その先のきれいな鼻の形。唇の健康的な薄赤い色。その真剣な様、ニヒルに口の端を上げる表情、言葉を発するときの動き。その低い声、全部好き。
僕の知っている彼のことは、全部彼の見た目のことばかりだ。それでも僕は彼のことを好きだと言いたいと思う。
カフェの窓際にある、いつも同じ二人掛けの席に、今日も僕は一人で腰掛ける。窓を背にして、お店のカウンターが見えるように。その向こうでは彼がお客さんに対応している。一見クールなのにどこかあたたかく優しい面が僕は好きだ。注文を受けるとカウンターの下の棚からテイクアウェイのカップを取り出して、別のスタッフさんにひょいと渡す。あ、今日は彼はメッセージ書かないんだな。次にお客さんも待ってるしな。受け取ったスタッフさんがペンを取り出してさらさらとカップの側面に何か書きつける。テイクアウェイのたびに彼自身からメッセージを書いてもらっている僕は本当にラッキーだ。こうしてイートインで軽食を摂りながら働いている彼を見ているのも好きだけれど、テイクアウェイカップに書いてくれるきれいな字もすごく好き。もらったカップを全部取っておこうかなって思っちゃったくらい。さすがにしなかったよ、写真を撮ってモバイルに残すだけ。
ひょいと彼が顔を上げてフロアの僕がいるほうを見た。慌てて視線を落とし、疎かになっていた鞄から勉強道具を取り出す手を動かす。まずいまずい、こんなに見てたら気持ち悪がられるといけない。彼はあんな素敵な見た目だから、僕にだけじゃなくてすごく人気がある。老若男女問わず話しかけられているのを見るし、女の人からも男の人からも何かアピールされているみたいな場面には何度も出くわす。すみません、お客さんがいるから、って、カウンターから少し離れたところで居たたまれなく様子を窺っていた僕を手招いてくれた、あの親切な指先を忘れない。そのときの困ったふうな苦笑いを見て僕は決めたんだ、彼の迷惑になることは絶対にしないって。
丸いテーブルに自分で拡げた課題を見て僕はため息をつく。勉強は苦手だ。自分が好きな生物と専攻してる写真、友達やおじさんのおかげで歴史と地理とフランス語は得意だけど、それだけできたってカレッジではどうしようもない。鞄に入ってるカメラを見下ろしてため息をつき、その隣に収まっていた筆記用具を取り出した僕の耳に、コンコンと背中側のガラスを叩く音が聞こえた。振り返ると友達のギブソンとトミーがいて小さく手を振っている。彼らは身振り手振りで自分たちもそっちに行くと示す。僕は頷いた。
「君に会いたかったらここに来ればいいね」
僕のテーブルの傍に来て、にこにこと大きな瞳を細めて笑うギブソン。トミーもふふっと小さく声をもらして彼の袖を引き、注文に行こ、と言った。カウンターに向かう二人の背を眺めるふりをして、僕はカウンターの向こうにいる彼を見る。ぱちりと目が合って僕はすごく驚いた。彼はとても自然に小首をかしげ、やわらかく微笑んでみせる。僕が息を止めているうちに二人がカウンターに着いたので彼はそちらに目線を向けた。ひゃああ、あんなふうに笑ってもらっちゃった。顔じゅう火照って真っ赤になっている気がして僕は顔を伏せてノートに向かったけれど、参考書の文字列は全然頭に入ってこない。
そのうち二人が戻ってきて、隣のテーブルを僕のテーブルにくっつけて席に着いた。
「何の課題?」
「数学……」
「あ、じゃあトミー先生」
「任せて」
「お願いします、先生」
身を乗り出してくる二人に僕はぺこりと頭を下げる。笑い合って僕らは三人して参考書を覗き込んだ。
トミーは僕と同い年のプロダクトデザインを専攻している学生で、ギブソンはアダルトコースで彫刻を専攻している学生。仲良くなったきっかけは本屋さんで僕が探していた、そして結局見つからなかったフランス人フォトグラファーの写真集を、そのお店でアルバイトをしているギブソンが貸してくれたことだった。僕も好きなんだこの写真家、明日また来てよ、僕んちにあるやつ持ってくるからさ、フランス訛りの英語と笑顔が素敵で、僕はうんと頷いた。それから僕とギブソンが仲良くなって、そのうちギブソンのことを気にしていたトミーと知り合い――カレッジの講堂でいきなり隣に坐ってきて、君、あの人の友達? と無表情に詰められたのが最初だ――なんやかんやあって二人は恋人同士になって、僕はその一番の友達になった。
二人は顔を寄せ合って僕の参考書を覗き込みながら、ああでもないこうでもないと話している。教えられているのは僕なのに、僕は二人がそうしているといつもぼんやりと見てしまうんだ。二人はとても楽しそうで、穏やかで、幸せそうで……僕は、とてもうらやましい。お互いに好きな人とそうやっていられることってどんなに素晴らしいんだろう。
「ジョージ?」
四つのヘーゼルの瞳が僕を見上げる。僕はなんでもないよと笑ってペンを握りなおした。
三十分もするとギブソンは僕の鞄からカメラを取り出していじり始めた。飽きたの? なんて訊くトミーに彼は、うーん、と曖昧に答えている。
「君の写真に写るとなんでも良く見えちゃうから難しいな」
ギブソンはぼやく。こないだ僕が撮った彼の作品の写真を確認しているみたいだった。
「だって君の作品、本当に素敵だったよ」
「うう、嬉しいけど……」
「ふふふ」
悩ましそうにするギブソンに小さく笑ったトミーはうんと伸びをして彼の腕時計を見、今日はもう勉強終わり、帰るよジョージ、なんて言う。勉強してたのは僕なのにね。でもかなり長いこと居坐ってしまったからそろそろ帰らないと。店内はディナーメニューを楽しみにする人たちで賑わい始めていた。
僕たちがカフェを出ようとすると、またどうぞ、と声がかかった。振り返るとカウンターの向こうから彼が、接客中なのに店を出て行く僕らに顔を向けてにっこりと微笑んでいる。僕は慌てて頭を下げると、先を行くギブソンとトミーを追いかけた。
「ジョージ、また彼いたね」
ギブソンに言われて僕はこくりと頷く。彼は嬉しそうにこっとした。
「素敵な人だと思うよ。さっきだって、きっと君に声をかけたんだよ」
「歳も近そうだけど、しゃべったりしないの」
トミーに訊かれて僕は首を振る。
「お客さんにプライベートっぽく声かけられるの、迷惑してるみたいだったから。彼に厭な思いさせたくないんだ」
「でも、君からなら気にしないんじゃない」
わけもなくトミーが言うから僕はむっと眉をひそめてしまった。どうして二人とも、そんなふうに人を期待させるようなことを言うんだろう。僕の顔を見た彼は口許をそっとゆるませて、怒るなよ、と言った。
「だってあんなに通ってて、君のこと認識してないわけないだろ。もう知り合いだよ、知り合い。友達」
「トミーってほんとに大雑把だよね」
ギブソンがおかしそうに笑うのにトミーは口をとがらせたけど、すぐに彼も笑い出した。僕もおかしくなって一緒に笑う。ギブソンはひょいと僕の肩に腕を回してきれいに目を細めた。
「きっと大丈夫だよ」
そうしてぽんと僕の肩を叩く手はやわらかくあたたかくて、僕は頷けなかったけど、口許をもごもごさせた。
「じゃあ、また明日ね、ジョージ」
「バイバイ、あ、写真集忘れないでよ」
「あ、そうだった。またね」
二人の帰路との別れ道で僕らは手を振る。僕は海のほうへ、二人は街中のほうへ行く。トミーに貸すつもりの写真集、帰ったらすぐに準備しないとな。明日まで覚えていられる自信はないや。
遠ざかっていく二人の後ろ姿は肩と肩の隙間がほとんどないくらい寄り添って、顔を近づけて笑い合う様子は本当に親しく、当たり前のように見える。二人と別れるとき、僕は一人でそれをずっと見ているのが好きだ。そうして、僕の隣に誰もいないことを思ってほっとため息をつく。
彼とあんなふうになってみたいと妄想するけど、名前も知らないし、知り合いみたいにしゃべったこともないのにさって、いつもうまくいかない。だけどもしそうなってしまったら僕はきっと、もっともっとって願ってしまうんだろう。それじゃあまりにもわがままだ。見てるだけでいいんだ。もし本当に顔を覚えてもらえてるなら、それだけでもいい。これ以上望んだってどうしようもない。
遠ざかっていくギブソンとトミーの輪郭を、暗くなる街を照らす街灯がオレンジ色に縁取っている。スポットライトみたいに二人を世界から切り取っていく。
写真に撮って残したいくらい、きらきらしていてとてもきれいだ。
◇
ロンドンからおじさん夫妻が遊びに来た。おじさんっていうのはあだ名で、僕の父さんの大親友さんのこと。僕の父さんが結婚したときは彼がベストマンを務めて、彼が結婚したときは家族だけのパーティーに唯一呼ばれた家族以外の人が僕の父さんと母さん、そして母さんのお腹のなかにいた僕なんだってさ。おじさん夫妻には子供がいないんだけど、その分僕がすごくかわいがってもらってるみたい。
お姉さんは――彼のことはおじさんでいいけど私のことはお姉さんって呼んで、とおじさんのパートナーさんが言うので僕はそう呼んでる――僕の母さんと映画に行って、父さんは急用でちょっとドーチェスターまで。水族館で僕の写真撮影に付き合ってくれたおじさんが、君がいつもテキストで教えてくれるカフェに行ってみたいな、と言うので、僕は彼を案内することにした。
ドアベルを鳴らして店内に入ると、いつもの彼が僕たちを見て、いらっしゃいませ、と明るく声をかけてくれる。僕とおじさんは二人してカウンターに並んだ。
「君のおすすめは?」
おじさんはひょいと僕の肩を抱いて僕越しにメニューを覗き込む。バニララテ、と答えるとおかしそうに笑うおじさんは、君は本当に好きだなあ、と言った。おじさんは、僕がロンドンに住んでいる彼のところに遊びに行くときも、どこかのカフェに入るたびメニューにあればバニララテを注文するのを知ってる。
「バニララテは君のを少しもらうから、俺はアメリカーノにするよ」
「それだと僕がちょっともらえないじゃない……」
「ケーキを買ってあげる。どれにする?」
おじさんの、骨ばっているけど丸い指先がメニューの上を滑る。僕は嬉しくなって、ブルーベリータルト、と答えた。ふふ、と小さく笑ったおじさんのきれいな薄青の目が細まる。
注文内容を伝えると、カウンターの彼はどこか固い表情で金額を教えてくれる。しまった、カウンター前に長居しすぎたかも、と焦ってしまって、僕はおじさんがさっさとカードを出して支払いを終えてしまったことに気づかなかった。おじさんに腰を押されて受け取り口のほうへ促されたときにはもう彼の手にはブルーベリータルトの乗ったトレーがあった。
「あ、払うよ、お金」
「払わせると思うか? 奢られてくれ」
「ひどい。でも、ありがとう。ごちそうさま」
おじさんはにこりと笑って、どういたしまして、と言う。本当におじさんは優しくてスマートで、お姉さんがうらやましいくらいだ。僕の母さんが、きっとみんなに人気があるんじゃない、なんてお姉さんに言ったらお姉さんは、この見た目だから遠巻きにされちゃうんだよ、って笑っていた。でも、僕たちはおじさんがすごく穏やかな人だということをちゃんと知ってる。僕はおじさんにすごく憧れているんだ。僕もこんなふうになれたらいいのにって。全然だめだけど……
「あー、バニララテとアメリカーノ、どうぞ」
いつもカウンターの彼と一緒にいるキッチンスタッフさんがカップを二つテーブルに置いてくれる。ありがとう、と言うおじさんと僕を、彼はなぜか気まずそうに見ていて、僕はまたどきりとした。
「あのさ、あなたたち……」
「アレックス」
カウンターの彼が強い声を出して僕はどきりとした。彼はテイクアウェイのカップをアレックスと呼ばれたスタッフさんにぐっと差し出していて、すごく険しい表情をしている。それを見た僕は恐ろしくなって、思わず俯いてしまった。おじさんがまるで何も気にしていないみたいにカップをトレーに乗せて、アレックスさんにもう一度、ありがとう、と言っている。僕も慌ててお礼を言って、いつものカウンターが見える席じゃない、カウンターから遠く離れた隅っこの席におじさんを連れて行った。
「どうしたんだ?」
「は、早く出よう。僕、あの人のこと怒らせちゃった……」
「ん?」
ひょいと振り返ったおじさんが、なんだろう、と呟く。
「こっちを見ていたけど、彼らは君の友達なのか?」
「ううん、全然、違う」
向かい合う一人掛けのソファにそれぞれ腰を下ろして、僕はすぐにブルーベリータルトに手をつける。一刻も早くお店を出たかった。おじさんは首をかしげて、陶器のカップの側面を指で鳴らす。納得がいかないことがあるときにやるおじさんのくせだ。
「なんで彼が君に怒るんだ。君は何も悪いことをしてないだろう」
「さっき、カウンターの前でもたもたしちゃった」
「あのくらい誰でもする。いいから落ち着いて食べて。おいしいだろう?」
僕は頷く。おいしいに決まってるよ、このお店の手作りブルーベリータルトだもの。
おじさんが一口ほしいと言うので、僕はタルトを載せたフォークをおじさんの口許に差し向ける。ぱくつくおじさんは目を細めて、甘くなくていいな、と笑った。僕はまた頷く。
「きっと今日は調子が悪いんだろう。人間毎日元気なわけじゃないんだから、君も気に病むな」
「……うん……」
おじさんが腕を伸ばして僕の前髪を撫ぜてくれて、僕はほっとした。
「もしかして君は……」
すいと眇められた目が楽しそうで僕はむっとなってしまう。にんまり笑うおじさんは僕の父さんをからかうときみたいな顔つきになって、きっと今の僕は不本意にからかわれたときの父さんに似てるんだろうと思った。
「そうか。それなら気になるのも仕方がないな」
「僕何も言ってないよ」
「ごめん」
何も言われてない、おじさんは両手をホールドアップする。それでも表情は楽しそうなままで悔しい僕は、タルトに乗っていたブルーベリーを一粒ぽいとおじさんのアメリカーノに放り込んでやった。
「こら」
「ふふふ」
いたずら小僧め、とおかしそうに笑うおじさんがアメリカーノをぐいとあおって、落ちてこないな、なんて言うから僕はいよいよ笑ってしまう。
「……すごく格好いいんだよ、彼」
「ん? ああ、そうだな」
ぼそぼそ声になる僕に、身を乗り出して相槌を打ってくれるおじさん。僕の視線はテーブルの上の空になったタルトのお皿に留まっている。
「それに、優しいんだ。テイクアウェイのカップに、がんばってね、とか、お疲れ様、とか書いてくれるし」
「うん」
「ちゃ、ちゃんとわかってるよ。お客さんみんなにしてることなんだって。でも、僕はすごく嬉しかったから……」
「わかるよ」
ちらりと目線を上げると、おじさんはすごくきれいに笑っていて僕はどきどきした。こくりと一つ頷くおじさんは小さく首をかしげて、もっと聞かせて、とささやく。
僕の口は軽かった。
「今日は全然見れなかったけど、笑顔がすごく格好いいんだよ。僕それがすごく好きで……でもあの、もう一人のスタッフさんと話してるときのくしゃっとした笑い方もすごくいいんだ。いつも遠くから見てるだけなんだけど……って、なんか僕、変なやつだね、わかってるんだけど」
「変じゃない。気になる相手のことは見ていたくなるものだ」
「本当に?」
「本当だよ」
「写真に撮りたくなる?」
「もちろん」
続けて、と優しくおじさんは促してくれる。
「僕、前に、授業でひどい失敗をしちゃって……現像液をぶちまけちゃって、みんなの写真だめにしちゃったんだ。みんなは、いいよ、次から気をつけてって言ってくれたけど先生にすごく怒られて、当たり前だけどさ、ほら薬品が危ないから……それで……」
肩を落とす帰路、そのころ新しくできたこのカフェの前に差し掛かると、彼が店の前を掃除していた。珍しく抜けるような青天で、彼の金髪は太陽の光に反射して美しく輝いていた。僕は性懲りもなく写真のことを――彼を被写体にすることを思っていた。こんなに美しい人を写真に撮れたらどんなに素晴らしい作品ができるんだろう。ぼんやりしていた僕に、顔を上げた彼が気づいた。
こんにちは。調子はどう?
爽やかな笑顔と軽やかな社交辞令に僕は返事ができなかった。口先だけでも、いいよ、って言えたらよかったのに。彼は返事もしないで見つめるだけの僕にぱちりと二度瞬いて、それからぴっと人差し指を立てた。
待ってて。甘いもの平気?
僕がよくわからないで頷くと、よかった、と言って彼はお店のなかに入って、すぐに戻ってきた。手には紙袋を持ってて、それを僕に差し出してくれた。
バニララテとスコーンだよ。サービスしてあげる。
彼は僕の手を取って紙袋を持たせてくれた。なんだかすごく重たく感じられて僕はありがとうって言うしかできなかったんだけれど、彼は僕の手をぎゅっと握って、元気出して、と微笑んでくれた。
大変なこといっぱいあると思うけど、今日はゆっくり休んでね。
――なんて優しい人なんだろう。僕は心の底からそう思った。きっと彼はこんなふうに毎日誰かの心をやわらかくしているんだ。だから当たり前みたいに見ず知らずの僕にも優しさを差し出してくれる。
こんな人がいるんだって思って僕はたまらなくなった。だから僕、この人がこうしているかぎりがんばろうって思ったんだ。僕もいつか、誰かにこんなふうに優しくなりたい。
「……この人が生きてるかぎり、僕も生きてたいって思ったんだよ」
僕がそう言うと、おじさんはまた僕の前髪をくすぐって、素敵だな、とささやくように言う。僕は口をもごもごさせた。
「君は彼のファンってことかな」
「……そうなのかな。おじさんにとってのザッパみたいに。トム・ヨークだっけ?」
「どっちもだな。まあ、それじゃあ熱烈だ」
おじさんは、だったら今日はさびしいね、と続ける。
「きっと今日は彼が大変で、ゆっくり休まないといけない日なんだろう」
僕は頷いて、バニララテを飲み干した。どうかこんなふうな優しい甘さのなかで、彼もゆっくり休むことができるといい。僕にはそうやって願うことしかできないけれど。
ちらりと懲りずにカウンターに視線を向けると彼と目が合って、僕はびっくりして肩を震わせてしまった。彼の傍で何かしゃべっていたアレックスさんも同じようにこっちに目を向けて、アレックスさんはというとひらりと手を振ってくれる。僕はどうしていいかわからなくて会釈をした。ん? と僕の様子に気づいたおじさんもカウンターを見た。
「気さくな人たちなんだな。君が好きになるのもわかる」
「……うん」
「そろそろ出ようか」
「うん」
トレーを持ったおじさんと僕が立ち上がると、さっとカウンターから彼が出てきて、片付けますよ、と言っておじさんの手からトレーを受け取った。
「ありがとう。ごちそうさま」
「いいえ。また……どうぞ」
彼はそうして僕のほうを見て、目を細めてにこりと微笑む――なんて格好いい笑顔なんだろう。
「また来てね」
「…………あ、う、うん。ご、ごちそうさまでした。ありがとう」
僕はおじさんの腕を押して慌てて店を出た。アレックスさんの、またな、という声が僕の背中にぶつかる。
全然うまく返事ができなくて泣きたくなった僕の頭をおじさんはぽんと軽く撫ぜて、
「よかったじゃないか。声をかけてもらえて」
と笑った。僕は頷く。本当はそれだけで、あんなに落ち込んでた気持ちがすごく楽になったんだ。僕ってどうしてこんなに自分本位なんだろう。
「大丈夫、気にすることないよ」
おじさんはそう言って僕の髪を優しく優しく撫ぜてくれた。
◇
僕って彼のファンなのかな。おじさんに言われたことを考える。でも、もし彼がインスタグラムやツイッターをしていたらきっと僕は彼をフォローしていただろう。僕はクラスメイトたちみたいにアカウント持ってないけどさ。やりなよって何度か言われたけど、ハマっちゃうのが怖くてできないでいる。きっと僕は彼のポストにいちいちlikeやfavoriteを送って、多分コメントはしないだろうけど、何分に一回タイムラインを確認したりして……っていよいよストーカーみたいで厭な気分だ。
来月の展示会に向けて設置準備をしているとき、話のなかでギブソンとトミーにそう言ったら、二人は首をかしげて、君って彼のファンだったの? と訊いてきた。わかんないから訊いてるのに。
「彼のこと好きなんだと思ってた」
「ファンと好きって違う?」
「違うだろ」
角材を抱えたトミーが言う。そういえば、ギブソンとトミーがお互いに向ける好きと、僕が彼に向ける好きはどんなふうに違うんだろう。
「トミーはどうしてギブソンのことが好きなの?」
「…………それ訊く?」
「だって、ファンではないんでしょ?」
そうだけど、と口をもごもごさせたトミーはそれから、あっていう顔になった。
「僕は彼の作品のファンでもあるよ」
「ありがとう、トミー」
ギブソンが言うのに彼は照れくさそうに笑ってみせる。なんのヒントにもならなくて僕はつい口をとがらせてしまった。
にこにこと微笑むギブソンはそうして僕を見た。
「もしかしたらファンと好きって一緒なのかもね。だって僕はトミーのこと好きだし、トミーのファンだもの」
その言葉にトミーは勢いよくギブソンを見て、それからその肩に頭突きをした。危ないよ、と笑うギブソンにトミーも笑っている。僕は照れているトミーの様子がおかしくて吹き出した。
「じゃあ、ファンも好きもおんなじことだね」
あっさり自論を覆すトミーに、仕方ないなあ、なんて笑うギブソン。二人はやっぱり、とてもきれいだった。
カフェのドアを開けると彼の、いらっしゃいませ、という明るい声。カウンターを見ると彼はぱっと朗らかな笑顔を浮かべて小首をかしげた。今日は機嫌がいいのかな。僕もなんだか嬉しくなって口許がほころんでしまう。
カウンターでバニララテのテイクアウェイを注文すると不意に、好きなんだね、と言われた。顔を上げた僕に彼は、バニララテ、と続ける。僕は頷いた。だって、君が一番最初に僕にくれたものだもの。
「いつも来てくれてありがとう」
彼はにこりと笑って言う。僕は首を振って、こちらこそ、と言った。すぐに変な返事になってしまったことに気づいたけど、どうしようもなくて彼を窺うだけになってしまう。
「カレッジの学生さんだよね? いつも勉強してて、えらいなあって思ってたんだ」
「そ、そんなことないよ」
みんなしてるよ、と僕が言うと彼は、謙遜するなよ、と返した。
「俺は君ってすごく立派だと思う」
僕は泣きたくなった。だって、本当にみんなしていることなんだ。僕はたまたま彼の視界に入るところで――彼を自分の視界に入れられるところで――勉強していただけで、褒められるような特別なことは何一つしていない。それに僕は、“彼にこんなことを言われたくてしていたんじゃない”んだ。どうして彼は急にこんなことを言い出したんだろう。
僕が首を振ると、彼はカウンターの下からカップを取り出した。
「俺はピーター。君の名前、聞いてもいい?」
「え?」
「君の名前を教えてほしいな」
「あ……えっと、ジョージ……」
ピーター。今、彼はそう名乗った。僕がぽかんとしていると、うん、と一つ頷いた彼はさらさらとカップに何か書いて、それを僕に見せてくれる。
『George, nice to meet you!』
僕は自分の顔が真っ赤になるのを止めることができない。きっと涙目にもなっているだろうけど、それだってどうしようもなくて、僕はただありがとうと言って、どうにか財布からカードを取り出すのでいっぱいいっぱいだった。
アレックスさんがピーターさんからカップを受け取りながら、俺はアレックス、よろしくな、とにこりと微笑む。僕はそれにも頷いて、ピーターさんにカードを渡す。思いがけず彼の指先が僕の指先に触れて、僕はびっくりして手を引っ込めてしまった。
「こないだは……知らない人と一緒に来てたよね」
「へっ?」
不意に言われた言葉に僕が顔を上げると、ピーターさんはカードを僕に返しながら首をかしげている。
「年上の人に見えたけど……格好いい人だったね。彼は……君の友達?」
「え……? えっと……」
きっとおじさんのことだ。だけど僕はそう口にすることができない。
なんでピーターさんは僕にそんなことを訊くんだ?
僕は心臓がどきどきして、息苦しくなってくるのを感じた。うまく言葉が出てこない。ピーターさんはちらりと目を細めて僕を見る。まるで窺っているみたいに――
“もしかして”、僕の頭に浮かんだ一つの考えは、僕を打ちのめすには十分な仮定だった。
「と、友達だよ……でも、彼は、け、結婚してるよ」
――何言ってるんだ、僕!
「ん? ああ、なんだ、そっか」
「うん……」
ありがとう、僕はなんとかそう言うと急いでカウンターの前からアレックスさんのいるほうへ向かった。バニララテはもうできていて、彼はカウンターに優しくカップを置いてくれる。僕は側面のメッセージを隠すようにカップを取るともう一度ありがとうと言って、早足でカフェの出入り口に向かった。
「あ……お疲れ様! また来てね!」
僕は自分がピーターさんの言葉に頷いたか頷かなかったかわからない。半泣きだったから、涙が出そうになるのを押さえるので精いっぱいだったんだ。
「ねえ、こないだマーケットでカフェのあの人に会ったよ。君、彼に名前教えてあげたんだね」
講義の合間、講堂で隣に坐ったトミーが出し抜けに言った。やったじゃん、なんて言いながらじりじり傍に寄ってくるトミーの話に僕が驚いていると、彼は首をかしげて、君がどうしてるか訊かれた、と続ける。
「最近行ってなかったの?」
尋ねられて僕は首を縦に振る。最近って言っても、毎日のように通っていたときに比べれば一週間と少し足が遠のいた程度なんだけど。それだって、僕自身にすらびっくりだけどね。
トミーの目は何かあったのと僕に訊く。僕は特別何もないよと首を振るけど、それはトミーには通じないんだ。トミーはじいっと僕を見つめる。
「……実は……」
ばか正直な僕の口は、きっとピーターさんは僕の友達が気になるみたい、とトミーに打ち明ける。トミーはみるみる表情を歪めてついには、
「はああ???」
と声を上げた。僕は唇をかんで俯いてしまう。きっと、トミーもギブソンも僕のこと応援してくれてたと思う。だけどそれが全部意味のないことだったなんて、僕は自分が不甲斐なくて、どうしたらいいんだろう。
「え、それ本当? 君のあの年上の、ロンドンの友達だよね?」
「本当だよ……彼、おじさんのこと格好いい人って言ったんだ」
「えー、えー……いやちょっと……」
「僕、咄嗟に、彼は結婚してるよって言っちゃってさ……本当に最低だ……」
頭を抱えて机に突っ伏す僕に、トミーもまた机に顎をくっつけて顔を寄せてくる。
「君は何も悪くないよ。事実を言っただけだろ?」
「そうだけど……もし、おじさんのこと紹介してって言われたらって思っちゃって……」
「もしそうなったときは彼のほうが最低なんだよ。人を仲介役にしようなんて」
僕は目線を上げてトミーを見た。
「僕、君のことギブソンに紹介してあげたよね?」
「あれは、僕から僕を彼に紹介してって言ったんだからいいんだよ。君は僕とギブソンの橋だ。本当に感謝してる」
トミーはそうして僕の眉間にちゅっと唇を寄せ、にこりと笑った。
「でも、今回は君が当事者だから。僕もギブソンも、何でも君の力になる。君の味方だよ」
その言葉に、僕は思わず涙をこぼした。トミーは彼の固い親指で僕の眦をそっとぬぐってくれる。
「君はどうしたい? 何でも言って」
「…………僕……」
こんなこと本当に僕が言っていいのかわからなかったんだけど、トミーが、ん? と優しく目を細めて僕を見つめてくれるから、僕は鼻の奥がつんとして、腹の底がざわざわして、たまらない気持ちになってしまった。
「彼に僕のこと見てほしい」
「うん」
「彼のこと写真に撮ってずっと残して、いつまでも見つめていられたらってときどき考える」
「わかるよ」
「……君たちみたいに、彼となれたらって、本当はずっと思ってた……」
「そっか」
トミーは僕の頭を優しく撫ぜてくれる。その指先があたたかくて僕はまた涙をこぼしてしまった。
「僕はわがままだ……」
「そんなことない。前に君、言ってたろ。彼に厭な思いをしてほしくないから声をかけないんだって。僕はそれってすごく勇気の要ることだと思ってる。僕は本当に君が偉いと思うよ」
褒め上手なトミーは僕の髪の毛を指先でいじりながら、今日はギブソンの本屋さんも早上がりだし、とぽつりと言う。
「展示会準備終わったら作戦会議しよう。本当は、君はもうがんばんなくていいよって言えたらいいのに。彼が鈍感なせいで」
唇をとがらせるトミーに僕は笑ってしまう。
「彼はなんにも悪くないよ」
僕が言うとトミーは、君を泣かせるやつはみんな悪いやつだよ、とにやりと笑って言った。
その夜、僕たちはギブソンのフラットに集まって“作戦会議”をしようとしたけれど、トミーの話を聞いたギブソンがまず訝るような表情をするから、早速会議は暗礁に乗り上げた。
「ねえ、それ、本当に? 彼が本当に君の友達のこと好きになったって?」
「好きになったかどうかは……でも、彼のこと気にしてるふうだったし、格好いい人だねって」
「だってあの人、本当に格好いいもんね。それはわかるけどさ」
ギブソンは顎を手のひらに乗せてううんと首をかしげる。
「君との会話のきっかけを探してただけじゃなくて?」
「あ、やっぱり、その線あるよね」
トミーがぱちんと指を弾いてみせる。そんなふうに考えたことがなくて、僕は二人の顔を何度も見た。トミーはうんうんと頷きながら続ける。
「マーケットで会ったとき、君のこと本当に気にしてたよ。心配そうだったし……僕は君がしばらくカフェに行ってないの知らなかったからさ、カレッジでは元気にしてるよって言ったら、だったらいいんだって」
彼が僕のことをそんなふうに心配してくれたことが嬉しくて、僕はぎゅっと握った拳を胸に当てた。同時にすごく申し訳なくもなる。勝手な嫉妬で僕は彼の思いやりをないがしろにしてしまったんだ。
「明日にでもカフェに行ってみなよ。それで、君から話を振ってみたら?」
ギブソンが言うのに、トミーは唇を少し突き出して腕を組んだ。
「なんだか癪だな。ジョージばっかりがんばってる気がしない?」
トミーの言葉にギブソンは苦笑いするけど、僕は慌てて、そんなことないよ、と言った。
「だって僕が勝手に彼のこと好きなだけなんだし」
「それだよ。僕、彼も絶対君のこと気にかけてるんだと思ってる。君、いっつも窓際の席に坐ってるだろ? 窓越しに君を見つけるとき、いつも彼が君のほうを見てるんだよ」
「…………本当に?」
ぱくんと口を開けた僕に、隣からギブソンも、そうなんだよ、と頷く。
「そのあと僕らと目が合って、逸らされるのがいつもの流れって感じかな」
僕の知らない彼の姿を知っている二人の言うことに僕は緊張する。彼が本当に僕のことを気にしてくれてる?
どぎまぎしている僕の肩をギブソンが軽く叩く。にこりと笑うギブソンは、きっと大丈夫だよ、と言った。ギブソンはよく僕にこう言う。勇気づけてくれたり、背中を押してくれたりするその言葉が、僕はギブソンの声と相まってとても好きだった。
「……明日、行ってみる」
「よし、その意気だよ」
「あ、僕たちが何か言ったからなんてことは言うなよ。知らんぷりで行ったほうがいい。君のことなんか気にしてないよ、みたいにね」
駆け引きだ、とトミーは真剣な表情で頷く。ギブソンはその顔におかしそうに笑って、経験者は語るね、なんて言った。
◇
「いらっしゃ……」
彼は――ピーターさんは言いかけて、それからもう一度、いらっしゃいませ、と言った。僕は内心どきどきしながらカウンターに向かう。平気なふうを装いたいのに顔が真っ赤になっている気がする。
「あ、えっと」
「久しぶりだね」
カウンターに辿り着いた僕が注文する前にピーターさんの声が聞こえて、顔を上げると、彼の笑顔が間近にあって僕は思わず、わ、と口にしてしまった。
「学校忙しい?」
「え? あ、うん。そう、そうだね。いろいろ準備があって……久しぶりに来れたよ」
へへ、と乾いたへたくそな笑いが口から漏れる。ピーターさんは、大変だね、お疲れ様、と言って、それから、バニララテにする? と訊いてくれた。
「時間ある? ゆっくり食べていきなよ」
「あ、うん……」
「じゃあ、俺が奢ってあげる。好きなの頼んで」
「ん?」
思わず口に出て、僕は慌てて口許を手で覆った。ピーターさんは目を丸くして、それから笑って、
「がんばってる君に何かしてあげたい」
と言う。僕はぽかんとしてしまった。ピーターさんの言っていることの意味が全然わからなくて――どうして彼がそんなことを言うのかがわからなくて、僕はしばらく返事ができなかったけれど、ただ何を言うべきかはすぐにわかった。
「い、いらないよ。僕、自分で払うから。気持ちだけありがとう」
「けど」
「ピーターさんは優しいんだね」
「こないだはあの人に奢ってもらってたでしょ」
「あれは……おじさんは大人だもの」
「俺だって学生の君よりは年上だ」
思わず、言葉が僕の口を突いて出た。
「君に何かしてほしくてがんばってるんじゃないから!」
強い口調になってしまったとしても、発せられた声は戻らない。ピーターさんは僕の大声に驚いて、小さく口を開けていた。僕は大変なことをしてしまったことに気づく。謝らないと……!
「ピーター、お前が悪いよ」
アレックスさんの声がして、僕が恐る恐るそちらを見ると、アレックスさんは拳でピーターさんの二の腕を軽く叩いた。
「ジョージに謝って」
「…………ジョージ、本当にごめん」
悄然とするピーターさんに、僕のほうこそ申し訳なくて泣きたくなってしまう。首を振って、僕こそごめん、と返すと彼は、君は何も悪くないよ、と言った。
「俺、どうしよう、どうしたら許してもらえる?」
「お、怒ってないよ」
「でも、君に失礼なことを言った」
「僕のこと考えてくれたんでしょ」
「……ごめん」
ピーターさんはくしゃりと髪を掻く。
「君に優しくして、いいとこを見せたかった」
「それって」
――自分のことばっかりだ!
そのことに気づいたとき、僕は本当におかしくて、笑ってしまった。ぱちりと瞬くピーターさんは首をかしげて、心配そうな表情をしている。僕は小さく首を振って、そんなことしなくていいよ、と言った。
「いやだ、君によく思われたい」
「お前、懲りないな」
「アレックスうるさい」
横から口を挟んだアレックスさんをピーターさんはじろりと見た。僕は慌てて、本当に、と付け加える。
「だって僕、君が優しくてとてもいい人なことをもう知ってるんだ」
それに君のことを好きなんだから、心のなかでそう付け加えてピーターさんを見ると、彼はぽかんと口を開けて顔を真っ赤にして僕を見ている。
「なんで?」
ピーターさんはぽつりと口にした。
「俺、君に何もしてあげられてない」
「してくれたよ」
君は僕がひどい気持ちでいたときに、僕に優しくてあたたかいものをくれたんだよ。
いっしょけんめ笑顔を作って、僕はバニララテとベイクドチーズケーキを注文する。アレックスさんが返事をしてショーケースからベイクドチーズケーキを取り出し、ぱしんと強くピーターさんの背中を叩いた。
「うわ」
「ぼーっとしてるなよ。カップ。お皿。トレー」
「あ、ごめん」
アレックスさんに言われるがまま、ピーターさんはカップやお皿を彼に渡す。僕は彼がこちらに向き直ったのを見てそっとカードをピーターさんに差し出した。ピーターさんはそれを受け取ってリーダーに通し、僕にカードを返すと、あのさ、と言った。
「俺の連絡先……あれ、どこだ」
ぱたぱたとエプロンのポッケを叩き、手を入れたピーターさんは、しかめ面をしながらしわしわになったメモ紙を取り出した。
「しまった、ずっと入れてたから……ごめん、ちょっと待って、書き直すから。俺の連絡先もらってくれる?」
「え? あ、待って、その紙でいい、それでいいよ」
「でも」
「それがいい」
もう僕にはわかっていた。僕が勝手な嫉妬でこのお店に来なかった間じゅう、きっとそのメモ紙はピーターさんのポッケのなかに入ってたんだ。
ピーターさんは申し訳なさそうにメモ紙を僕に差し出してくれる。僕はそれを大事に大事に受け取って、いっしょけんめに笑顔で応えた。
足許がふわふわして、胃袋が底から浮き上がってくる。ピーターさんはまるではにかむみたいに笑って、連絡ちょうだい、と言った。僕は何度も頷いた。
それから僕はアレックスさんからバニララテとベイクドチーズケーキの載ったトレーを受け取って、いつもの席に――カウンターが見える窓際の二人掛けの席に一人で坐った。鞄を他方の椅子において顔を上げると、ピーターさんが僕を見ていてどきりとする。彼は両手でモバイルをいじるみたいな仕草をした。僕は慌ててモバイルを取り出し、さっきもらったしわしわのメモ紙に書かれたピーターさんのアドレスにテキストを送った。
『こんにちは』
カウンターの向こうでピーターさんはモバイルを取り出し、画面を見ると僕に顔を向けてすごく嬉しそうに笑う。それから彼がモバイルをいじると、僕のそれが軽やかにテキスト受信を告げた。
『こんにちは。よろしくね!』
今度は僕が顔を上げてピーターさんを見る番だった。僕が頷くとピーターさんも同じように頷いて、それから小さく手を振って今来たお客さんに対応し始める。
僕はバニララテに口をつけた。一口飲んでほうと息をつくと安心できた気がして、いつの間にか伸びていた背をだらりと背もたれに押しつけてしまう。
ギブソンとトミーの言った言葉が頭のなかをぐるぐる巡る。ピーターさんは本当に僕のことを気にかけてくれていた。それが好きなのか、ファンなのか――ファンはないけど、僕とおんなじ気持ちなのか、それはまだわからないけど。
でも、僕が無理やりもらったしわしわのメモ紙が、ぼそぼそとささやいている。君ってちょっと特別なんだよ、って。
◇
それから、僕たちの関係性はすっかり変わった。
僕がカフェに通う以外の時間でも、ピーターさんに――ピーターに会えるようになって、僕は彼に、ピーターって呼んでよ、と言われたからそう呼ぶようになったし、僕は彼の優しい声でたくさん、ジョージ、って呼んでもらえるようになった。僕が彼のフラットに遊びに行く機会や、彼が僕のフラットに遊びに来る機会も増えたし、昨日は――彼の部屋で、キスをしたんだ。
とても不自然な流れだったと思ってる。僕たちは並んでソファに坐って、彼のPCで社会派ドラマとアクションが一緒くたになったみたいな映画を観ていた。何一つロマンチックな雰囲気じゃなかったし、すごく面白い映画だったけど、観終わったあとに彼が僕の傍で、よかったね、と言う声になぜか僕はどきどきしてたまらなくなってしまった。彼の瞬く瞼のぱちりという音が聞こえた気がして思わずため息まじりの返事になる。ピーターは僕がどぎまぎしているのに気づいていたのかいなかったのか、それはわからないけど、彼は僕に、キスしようか、と尋ねた。僕は戸惑ってしまって初めは彼を見返すしかできなかったんだけど、ピーターが小さく首をかしげたのがとてもかわいくて、うん、と頷いた。
ピーターが震える僕の両肩にそっと手を置いて、ゆっくり唇を近づけるから、心臓がはちきれそうになりながら僕も目を閉じた。そうしたらピーターの唇が僕の唇に触れて……すごくやわらかくて、ほんの少しだけ湿っていて、映画を観ながら飲んでたミルクティーの味がした。
本当に触れるだけだったけど、僕は頭が爆発してどうにかなりそうだった。体じゅうの熱が顔に集まってるんじゃないかって思ったら目を開けるのも怖かったんだけど、恐る恐る瞼を開けたら、ピーターがにこっと笑って、もっとする? なんて訊いてきた。僕とは全然違って平気なふうで彼はずいぶんと大人びて見えた。僕は……うん、って返事をして、彼はもう一度僕に、やっぱり触れるだけのキスをしてくれた。
昨日は結局それで終わって、夜、自分のフラットに戻った僕はもうじたばたしまくって、ベッドに入っても全然眠れなくて、ギブソンかトミーかおじさんに思うままテキストを送りそうになっちゃったんだけど、なけなしの理性でみんなももう寝てるだろうからってそれはなんとかやめにした。
僕、どうしよう? 彼とキスしたんだ。あんなに優しい言葉をくれる人が、おんなじ唇で僕に触れてくれた。こんなのってありえないよ。夢を見てるのかも。最近の日々が僕の想像や妄想を簡単に超えていく。だって彼が僕の隣にいて笑ってくれているだなんて、それすら想像できなかったのに!
僕多分いつ死んでもおかしくない、って僕が言うと、設置準備の手を止めたギブソンとトミーは、何言ってんの、と口を揃えて返す。
「だっ、だって、昨日、僕、ピーターと、き、……キスしたんだ……」
それを聞いたトミーが、ああ、って大きく嘆息して、それから両腕を拡げて持っていたビニール袋をぽいと放り投げた。
「ジョージ、ハグさせて。君ってかわいすぎだ」
「待ってよ、僕もする」
続けてギブソンにも抱きつかれて僕は唸る。二人はひとしきりそうしてから僕の髪の毛をもみくちゃにした。
「ねえジョージ、心配することないよ。結構たくさんの人がそうやって生きてるんだから」
「君たちみたいに?」
「うん、そう」
僕は思わずため息をついてしまう。
「すごいんだね……」
「これからもっと想像以上だよ」
トミーがにやりと笑う。僕はどきどきして頷いた。
本当は二人に、二人はどういうふうに“生きて”いるのか訊きたかったんだけど、僕らのことは参考にならないよ、と言われてしまって僕はさみしかった。でも、ギブソンがこう続けた。
「僕らがしているとおりにしたって、君たちのしたいようにはならないよ」
それは確かにそうなのかも。だって僕とピーターとギブソンとトミーは、みんなそれぞれ違う考え方をする人間だ。
「ねえ、そしたら、アドバイスがほしいんだ。どうしたら恥ずかしくなくていられるんだろう? だってピーターはすごく平気そうに見えるんだよ。こんなの何でもない、普通のことだよみたいに。僕もいちいち驚かないでいたい」
「君は君のままでいたほうがいいと思う」
トミーは言う。でも、と僕が言いかけると、トミーの軍手に包まれた人差し指がそっと僕の唇に触れた。
「ピーターが好きになったのは、僕たちに入れ知恵されてないまっさらな君だよ」
僕は俯いた。まだ全然実感がなくて、トミーの言葉に戸惑ってしまう。ピーターって僕のこと好きになってくれたのかな。名前を呼んでくれるとき、そっと手をつないでくれるとき、肩に触れてくれるとき――ピーターの優しい温度が僕の体のなかに流れ込んでくるのがわかる。それはあたたかく、穏やかで、だけど僕はすごく不安になる。こんなに素敵なもの、本当に僕がもらっちゃっていいんだろうかって。きっとこんな不安さえなくなれば彼の前でも平気で振舞うことができると思うのに。
カフェに行くと、お客さんが全然来ないからとピーターとアレックスが僕がいつも坐る席でおしゃべりをしていて、僕もそれに混ぜてもらった。二人の会話を聞いているだけですごく楽しかったんだけど、たまに気を遣って話を振ってくれるのに答えるのは大変で腹がきりきりする。そのうちお客さんがやっと一人来て、ピーター行って来てくれよ、とアレックスに言われた彼が、なんでだよ、と悪態をつきながらカウンターに向かうのに僕は笑ってしまった。
「ジョージってカメラ好きなんだ?」
「ん? あ、うん。好きだし、写真科なんだよ」
「へえ、そうなんだ」
隣に坐るアレックスが僕の鞄に目を落とすので僕はカメラを彼に手渡す。手許でそれをいじりながら彼は僕にカバーが付きっぱなしのレンズを向けた。
「ピーター、君の前でちゃんとしてるか?」
「えっと……ちゃんとがよくわかんないけど、優しいし、楽しいよ」
「厭なことはされてない?」
「全然!」
「そっかそっか」
くしゃりと笑ったアレックスは僕にカメラを返すと、僕の髪の毛をそっと撫ぜた。首をかしげる僕に彼はにこりと笑ってみせる。
「ほら、いつか君、大声出しただろ。ああいうふうに厭な気持ちになることがあったら何でも俺に相談してよ」
僕はアレックスともアドレスを交換していたから頷いたけれど、でもそんなことで彼に連絡を取るのは悪いと思うし、そんな気持ちになることなんてきっとない。たくさんの社交辞令が重なっている気がして、僕は曖昧に笑い返して無難な答えを口にした。
「あれは僕が……むしろ、僕が彼に厭な思いをさせてないか心配だよ」
「それこそあり得ないね」
やけにはっきり言うんだな。僕が目を丸くしたのにアレックスはもう一度、あり得ない、と言った。
「でも、僕なんかでいいのかなって思っちゃうよ。ピーターはあんなにいい人だし……」
「じゃあ、お似合いだ」
アレックスはぱちりとウインクした。
「あいつも君もいいやつだから」
そんなことを言われると照れくさくなってしまう。僕が何も言葉を返せないでいるとアレックスはおかしそうに肩を震わせて、そういうところとかな、と歌うように言った。
「アレックス、次は君が行ってよ」
不機嫌なふりをしたピーターが僕たちのところに戻ってくる。アレックスは笑いながら、わかったわかった、と彼を手招いた。僕の向かいに腰を下ろしたピーターが僕に向かって、
「変なことされてない? 平気?」
と訊くので笑ってしまう。アレックスとおんなじことを訊くんだもの。そうしている僕に不思議そうな顔をするピーターは、テーブルの上のカメラをちらりと見た。
「最近はどんなの撮ったの?」
「カレッジのみんなやクラスメイトをモデルにしてる。横顔がテーマで」
カメラのメモリーを表示してピーターに見せると、彼は嬉しそうに笑う。
初めてピーターが僕の部屋に遊びに来た日、彼は僕の撮った写真たちを見て、君の写真すごく素敵だ、と言ってくれた。本当に嬉しかった。それから彼はいつもさり気なく僕の写真のことを気にしてくれる。あるとき、僕がどうにかなんでもないふうを装いながら、君のことも写真に撮らせて、と尋ねると、彼は満面の笑みで、君が撮ってくれるならいくらでも、と答えてくれた。それからは僕のカメラにピーターの写真がたくさん増えた。すでにアルバムが一冊できそうなくらいには。
「あ、トミーとギブソンだね」
ピーターが言う。アレックスもカメラを覗き込みに彼の後ろに回った。
「へー、彫刻?」
「そう、ギブソンの。トミーはプロダクトデザイン」
「お、こっちも格好いいな。このランプ部屋にほしい」
「ほんと? トミーに言ってみなよ、きっと喜ぶ。二人ってすごく素敵なんだ。僕ら、コラボしてるんだよ」
「コラボ?」
「来月のカレッジの展示会で……」
言いかけたとき、ドアベルが鳴った。ピーターとアレックスは同時に、いらっしゃい、と言ったけれど、それからピーターはじっとアレックスを見つめ、アレックスも観念したようにため息をついて席を離れる。僕がおかしくて笑うとピーターも、ふふ、と笑っていた。
「ねえ、その展示会って誰でも行っていいやつだよね?」
「うん、もちろん」
「見に行ってもいい?」
「……でも、仕事あるでしょ?」
本当は見に来てほしかったけれど、ピーターに今まで展示会のことを言えなかったのは、それがあるからだ。ピーターにはピーターの日常と生活があって、僕の些細な事情でそれを煩わせたくなかった。
でもピーターは事もなげに、休むよ、と言った。
「わ、悪いよ」
「どうして? 俺は君の展示を見に行きたいんだから、休んだっていいだろ」
「…………」
「ジョージ、言っとくけど、君と付き合ってるから君に気を遣ってるんじゃないよ。君の写真が好きだから君の展示を見に行きたい、それだけのことだ」
それとこれとは別だろ、とピーターは言う。僕はどきどきしながら頷いた。今、きっと彼にしてみれば何気なく言ったことが、僕を惑乱させる。
「……君の気に入る写真があるといいな」
「あるに決まってる。この、トミーとギブソンの写真が好きだよ」
「ぼ、僕も好き。その二人、すごくいい顔してるよね」
ピーターに言われたのが嬉しくて前のめりになると、彼はぱちりと瞬いて、それから笑った。
「君の見ている風景が好きだ」
――僕って彼と付き合ってるんだ。本当に? それってどういうことなんだろう。ううん、知ってるけど。ハグをしたり、キスをしたり、彼とそういうことをさせてもらえる立場なんだ、僕って。いつも一人で見ていたギブソンとトミーの後ろ姿、二人の笑顔。ああいうふうに、僕はピーターとなってもいいんだ。本当に?
「…………本当にいいのかな?」
ぽつりと呟いた声が一人ベッドに寝っ転がる部屋のなかにやけに響いて緊張する。だって、付き合おうとかそういう会話を交わしたわけじゃないんだ。いつの間にかそうなっていた。多分、結構たくさんの人がそうやって生きているんだろうけど、僕にはまだ未知の世界でわけがわからない。
無意識に指先が唇に触れていて、僕はため息をつく。……本当は、もっと触ってもらえたらと思ってる。ほら、どんどんこうなってしまう。
「僕はわがままだ……」
モバイルのメッセンジャーアプリを立ち上げて、おじさんのアドレスを呼び出す。
『おじさんとお姉さんってどんなふうにお付き合いしたの?』
開封済みのマークはすぐに付いたけれど、返事はすぐには来なくて、五分くらい時間が空いた。
『普通だよ』
「普通って何」
思わず声が出た。だって普通って何?
『例えば?』
『会話をして、デートをした。二人とも人混みが好きではなかったから、賑わっていて落ち着けないとわかるとすぐに目的地を変えるか家に帰るかの有り様だった。会話だってそんなに多くなかったし、手を繋いだこともない。俺たちは黙って互いの近くにいて、各々好きなことをして、たまに一方が面白いことを思いつくとそれを他方に話して聞かせるくらいの、それくらいの距離感でよかった』
『それって多分、普通じゃないよ』
『そうかな。そうかも』
あてにならないや、僕は思わず笑ってしまう。おじさんとお姉さん、二人の空気感は本当に独特で、確かに僕は憧れていたけど、きっとこの二人以外の誰もこういうふうにはなれないんだろうなと思ったことがあることを今更思い出した。それは、僕が今尋ねた相手がギブソンやトミーだったとしても同じことなんだろう。
『君が、君の隣にいる人となりたいようになりなさい』
――今、僕は一人ぼっちだよ。おじさんの気遣いが嬉しくてやっぱり僕の顔は笑っている。
『ありがとう、おやすみ』
『おやすみ。良い夢を』
ありがとう。僕は心のなかでロンドンにいるおじさんにメッセージを送って、目を閉じた。
◇
「ジョージ、こんな感じでどう?」
トミーに呼ばれて振り返る。淡いベージュを基調とした室内の壁の一面を白い木目のパネルが飾っていて、僕は思わず、最高、と言った。
「ギブソンはこことこっちだよね。棚の前にもいるんだっけ」
「そう。坐ってる子二人と立ってる子一人」
「君のは?」
「これ」
鞄からアルバムを次々取り出すとトミーは、うわあ、と言った。
「撮ったねー……ご、ろく、なな、ワオ、八冊」
「撮ったねー。トミーの本は?」
「これ」
トミーもまた彼の鞄のなかから十何冊かの上製本を取り出す。重かったよ! と感慨深く言う彼に、そりゃそうでしょ、と僕も頷く。トミーはブックデザインフリークでもあって、気に入ったデザインの本があるとすぐに手を出してしまうんだって。その趣味がきっかけでギブソンにも出会えたから金欠だろうと最高だよ、なんて言って楽しそうにしてる。
僕たちのコラボレーションする今回の展示はタイトルの『Somebody's Profile』の通り、“誰か”の部屋をイメージした作品になっている。一応参加者は彫刻を展示するギブソンと、室内の調度を設えるトミー、それから写真を展示する僕の三人という扱いにはなってるけど、コンソールゲーム機やいくつかのゲームソフト、大きなクッションやテディベア、映画のDVDや音楽のLP盤、キャンドルライトや観葉植物、様々な誰かの部屋にあるものをクラスメイトたちから借りて設置する、乱雑で、だけどどこかに自分の影を見つけられるような展示にできたらと僕たちは思ってる。僕の写真――カレッジの講師たちや学生たち、僕の知り合いや友達の横顔を撮った写真は、この部屋の壁の一面に飾られる“誰かの横顔”だ。
「一回ライト点けてみてい?」
「うん」
僕が室内の電気を落とすと、トミーは手許のスイッチをかちりと入れた。瞬間、淡いクリーム色の光が部屋に満ちる。天井一面からたくさん吊り下がっている様々な形の電球が一斉に灯ったのだ。
「よしよし」
満足そうに笑ったトミーはそのままぐるりと室内をゆっくり歩く。僕もトミーの後ろを歩いた。僕たちの足許に落ちる薄い影が不思議な模様を床に作る。
「ごめん、遅くなった」
ぱたぱたとギブソンが入ってきた。彼もまた天井の灯りたちを見上げて、すごいね、と笑っている。その面に影が揺らめいていて、普段からたおやかなギブソンの表情がもっと神秘的に見えた。
「君の子たちは?」
「これから連れて来るよ。外に待たせてるんだ」
肩から鞄を下ろしたギブソンに僕たちは、手伝うよ、と申し出て一緒に校舎の外に出た。薄明かりだった展示室内や暗がりのカレッジの廊下に目が慣れてしまって、外の強い光に思わず目をつぶる。何人か通りすがったギブソンのクラスメイトたちも彼の彫刻を運ぶのを手伝ってくれて、ギブソンの作品もついに室内に設置された。ソファに坐ってくつろいでいる二人と、棚の前に立って本を見ている一人。
「前から思ってたんだけど、ちょっとこの子、僕に似てない?」
そのなかの一人を指してトミーが言うのに、ギブソンのクラスメイトの一人が、いいや俺に似てるよ、と茶化して返す。僕たちはみんなして笑った。
カフェで展示会のDMを渡すと、ピーターは本当に嬉しそうに笑って、ありがとう、と夏の風みたいなさわやかな声で言った。そんなふうなかっこいい笑顔を見せられると僕は本当にまいってしまう。
「あれ? 二枚あるよ」
「あ、うん、アレックスにも」
「なんだ、そっか。観賞用と保存用かと思っちゃった」
「何それ」
僕たちは笑い合って、それからピーターは呆れたように横で見ていたアレックスにDMの一枚を渡した。アレックスはそれを見て嬉しそうに目を細める。
「俺たち二人ともこの日休むことにしたからさ。君らはみんなしてずっとここにいるわけじゃないんだろ?」
アレックスが訊くのに僕は頷く。僕たちは三人交代交代で展示室に待機することになっていて、午前中がトミー、午後の前半が僕、そして後半がギブソンだ。
ピーターが大きく首肯した。
「じゃあ、俺は一時過ぎに行こう。君を予約していい? 作品の案内をしてほしいな」
「あ、も、もちろんだよ」
僕が何度も首肯するとピーターはにこりと口の端を上げる。アレックスは別に用事があるからと少し遅れて来るそうだ。ギブソンにも言っとくね、と僕が言うと彼はこくりと一つ首を動かした。
「ねえ、あの人は来る?」
ピーターに尋ねられて首をかしげると彼は、君の年上の友達、と続ける。
「えっと……おじさんのこと?」
「おじさん、って。うん、でも、その人かな」
おかしそうに言うピーターに僕はどきどきする。まだ、ピーターがおじさんのこと好きなのかも、って思ってるわけじゃないんだけど、ピーターにおじさんのことを気にされたら僕の出る幕がなくなってしまうんだ。
「うん、来てくれるって言ってた……」
「そっか。よかった。君のことすごく大切にしてるみたいに見えたから」
ピーターの腕が伸びてきて、僕の髪にそうっと触れてくれる。僕は思わず息を詰めてピーターをまじまじと見てしまった。
「一度、挨拶したいなって思ってたんだ」
「おい、ピーター」
アレックスの声が横入りしてきて、ピーターは僕の頭をくしゃりと撫ぜてそれから手を離した。
「喧嘩売るなよな」
「何言ってるのかさっぱりわかんない。あ、ごめんねジョージ、今日は何にする?」
ようやくピーターは僕に尋ねる。思わず後ろを振り返って誰もいないことを確認する僕に彼は、大丈夫だよ、と笑う。
「あ、じゃあバニララテ……テイクアウェイで」
「いつものね。わかりました」
ぱたぱたとピーターの手がレジスターを軽やかに打つのを見るのが僕は好きだ。
「君のそういうところ、好きだな」
「えっ」
思わずカードをメニューの上に落としてしまった。だって、急にピーターが変なこと言うんだもの。
彼はくすくすと笑いながら僕が落としてしまったカードを取り上げ、はい、と返してくれる。
「周りの人を気遣ってるところ」
「え、でも……」
「みんなができることじゃないよ」
細められたピーターの青い瞳に僕はぎゅっと心臓を掴まれたみたいな気持ちになる。ピーターはカウンターの下からカップを取り出してメッセージを書くと、アレックスに手渡した。アレックスはちらりとカップに目を落として口の端を上げている。
「本当にお疲れ様。展示会、楽しみにしてる」
「……うん、がんばるね。ありがとう」
答えると、ピーターはにこりと笑った。
カップのメッセージには、がんばりすぎないで、と書いてあった。
◇
忙しいでしょ、と言われて、結局それから展示会当日まではピーターと個人的に遊ぶことはできなかった。カフェで会って、ちょっとだけ会話して、あとはテキストや電話のやりとりだけ。一週間ちょいくらいだけど、それでも僕は少しだけさびしかった。
だから、待ち合わせ場所に指定したカレッジの校碑前に現れたエプロン姿じゃないピーターを見たとき、僕はすごく舞い上がって、あいさつする声も上ずってしまった。
「こっ、こんにちは」
「こんにちは。どうしたの? なんかパニクってる?」
おかしそうに笑うピーターに僕は思わず髪の毛をいじりながら頷く。だって、初めて展示って形で僕の写真を見てもらえるんだ。緊張しないわけがない。
ピーターの気に入る写真があるといい。
「君の“おじさん”は?」
「あ、もうちょっとで着くって。今もう駅を出たみたいだから……先に入っててもいいって」
「待ってようよ」
ね、と言うピーターに僕は小さく首をかしげる。そんなにおじさんに会いたいんだ。僕も会いたいけどさ……
「僕、トミーと交代しないといけないから、行かないと」
「え? あ、そっか、ごめん。それじゃ行こう」
「ううん、君はおじさんを一緒に連れて来てよ。おじさん何回も来てるから、僕らの展示の場所もわかるはずだから。お願いしてもいいかな」
なんとか笑ってみせるとピーターは少し困ったような表情をして、それから、うん、と答えてくれた。よろしくね、と返して、僕は人で賑わうカレッジの前庭を一人校舎へ向かって歩く。変な歩き方になっていないか心配だった。
展示室に現れた僕にトミーが、ピーターはどしたの、と尋ねる。さっきのことを話すと、トミーは片眉を上げておかしな顔をした。
「彼、何考えてるんだろ。さっぱりわかんないや」
「うん……」
曖昧に笑う僕の肩をトミーはさすってくれる。そうして、でもね、と彼は口を開いた。
「彼が君のことを好きなことに違いはないと思うよ」
それを聞いていっしょけんめ上げた口の端が震える。好きってなんだろう。またあの疑問が心に浮かぶ。人ってそんなに簡単に誰かや何かのことを好きになるのかな? ……僕はなったけどさ。
「あ」
トミーが声を出した。僕の後ろに目を向けている。振り返ると、ピーターとおじさんが立っていた。
「いらっしゃいませ。今日は僕らが言う側だね」
「やあ、こんにちは、トミー」
「こんにちは。お久しぶりです」
にこやかにあいさつを交わすおじさんとトミー。トミーはそれからピーターを見た。
「やあ、ピーター。プライベートの格好を見るのは二回目だね。のんびり見ていってよ」
ピーターは、ありがとう、と返し、それから僕を見た。
「じゃあ、次はよろしく」
「うん。お疲れ様。また後でね」
ぽんと僕の肩を軽く叩くトミーのあたたかい手。彼が軽やかに展示室から出て行って、僕はそれからやっと二人を顧みた。
おじさんが歩み寄ってきて微笑み、僕の背中越しにぐるりと室内を見渡す。
「トミーのライトはいつもすごいな」
「でしょ? 今回はたくさん光を吊るしたいって」
「前は大きいのが一つどんとあった」
「あれも格好よかったね」
おじさんはそのまま室内を壁伝いに巡り始める。彼は自分のペースで見たい人だから、僕はピーターに向き直って、ありがとう、と言った。
「それじゃあ、ご案内いたします」
「……うん、よろしくお願いします」
ピーターがはにかむように笑うから、僕もおかしくて笑顔になる。ピーターは僕の隣に並んで立ち、それじゃあ、と言って顔を上げた。
「えっと、このライトはトミー?」
「そう。トミーはプロダクトデザイン専攻なんだけど、特に照明デザインをメインにしてるんだ。あとは趣味でブックデザイン集めとか」
ああ、とピーターは頷く。
「マーケットで会ったとき、両手に本を抱えてた」
「ははは!」
トミーの様子が想像できて僕は思わず笑ってしまう。ピーターもにこにこしながら、いつの間にか手にしていたらしい、展示室の入り口に置いていた作品紹介のフライヤーに目を落とした。
「『We Are All Light』?」
「うん。この展示全体のタイトルからそれぞれ連想してるんだ。トミーのは『みんな光』。よく見て」
僕がライトたちを指差すとピーターはそれをなぞって視線を天井に巡らせる。
「あ、それぞれ形が違う」
「そう。すごいよね」
ライトを見上げたままぽかんと口を開けるピーターから僕は二歩距離を空けて、彼を見た。たくさんの淡い光を浴びてやわらかく輝く彼の輪郭。そうやってにじむ彼のふち――僕はやっぱり彼が好きだ。
静かに、ピーターが僕に視線を向ける。
「……すごいね」
そうっと言う彼に僕は頷く。それから、彼はまた手許のフライヤーに目を落とした。
「彫刻は『Ours』?」
「うん」
僕らはソファに坐る彫刻たちの前に立った。彼らはのんびり背もたれに寄りかかりくつろいでいる。一人はうつむきがちで、一人はそんな他方に視線を向けている。もう一人は本棚の前に立って、その上に置かれたレコードプレイヤーに手を添えている。そのもう一方の手許には何枚かのLP盤。
「あ、これ、父さんが持ってる」
「ほんと!」
ピーターの言葉に思わず大きな声をあげる。ぱちりと瞬いた彼に僕は慌てて謝った。
「ごめん、あのさ、僕ら、そうやって見つけてほしくてこういう展示にしたんだ。本当によかった」
嬉しくてへらへら笑ってしまう僕をピーターは目を丸くして見ていたけれど、すぐにぱしんと彼自身の口許を片手で覆って、それからこくりと小さく頷いた。
「? ピーター? どしたの」
「いや、ううん、何でも……」
ピーターの目線がちらりと動く。その先には僕の写真を見ているおじさんがいる。
首をかしげる僕に、ピーターはちょっと唸って、それから僕にしか聞こえないような小さな小さな声で言った。
「ごめん、今の君、すごくかわいかった……」
「……!!」
顔じゅうに熱が集まってくる。だけど、ピーターも真っ赤になっていた。
「ほ、ほんとにごめんね。君の、君の展示を案内してくれる?」
「あ、う、うん」
そうして並んで隣に立った僕らを、おじさんはちらりと横目で見ておかしそうに口の端を上げた。その表情にまた恥ずかしくなってしまう。
「俺も聞こうかな」
「あ、どうぞ、どうぞどうぞ」
ピーターが促すのに、おじさんは体をこちらに向けて目を細め、小首を傾げる。
「えっと、僕のは、『One Of Us』だよ。みんなの横顔を写真に撮ったんだ……ほんと、タイトルそのままだけど」
「素敵だと思う。まっすぐで」
すぐにそうやって言ってくれるピーターは、本当に誰かを幸せな気持ちにすることが得意なんだ。僕は嬉しかったり、うらやましかったりで不思議な気持ちになってしまう。
「みんないい顔をしてる」
おじさんもささやくように言う。そうして、すいと一枚の写真を指差した。
「トミーだね。こっちはギブソンだ」
「うん。みんないるよ」
「…………」
ピーターはぐるりと壁の写真に視線を巡らせている。そうして彼が小さく口を開いたとき――
「あ、すまない」
おじさんのモバイルが軽やかに鳴った。
「お姉さん?」
「そうみたいだ。ちょっと外に行ってくる」
「はあい」
展示室から出て行くおじさんを目で見送った僕らは、もう一度壁の写真たちに向き直る。
「君がいないよ」
出し抜けにそう口にしたピーターに僕は虚を突かれて、え、と思わず彼の顔をまじまじと見てしまった。
「君の横顔がない」
「あ、ああ、僕は、だって、カメラマンだもの」
「でもそれじゃあ……」
ピーターは少しだけ俯いて、それからまっすぐ僕を見た。
「今まで黙ってたんだけど、俺、君の作品を前にも見たことがあるんだ」
「えっ?」
「半年前に展示してただろ。たくさんの人たちの笑顔を撮った写真だよ」
ああ、と僕は思い至る。僕とトミーとギブソンが初めてコラボレーションしたときの作品だ。そのときの展示タイトルは『Helios』。トミーが本で見つけた、覚えたてのフレーズだった。
ピーターは視線を僅かに俯けながら、言葉を選ぶようにゆっくり喋る。
「たまたま時間ができて、たまたまカレッジの総合展示会のポスターを見かけて……なんとなく行ってみようって思って……でもそこで、君の写真を見たんだよ。いや、正確にはまだ君のだとは知らなかった。けどすごく素敵だと思ったよ。写ってる人たちがみんな、本当に楽しそうに笑ってる。笑ってない人もなんだか……満ち足りた表情っていうか……とにかく、俺はすごく気に入ったんだ。君の作品を」
展示室じゅうに響いてるんじゃないかってくらい、僕の心臓がうるさい。まさか、まさかピーターにそんなことを言ってもらえるなんて思わなくて、ピーターが僕の写真をずっと知っててくれたなんて考えたこともなくて、僕は混乱した。
「名前が……名前を横に載せるだろ。ジョージ・ミルズって。それで、そこにいた学生に、この人はいるかって訊いたんだ。その日君はいなかったけど……この写真のなかにいるかって訊いても、いないって言われた」
ピーターは、それで、と言葉を続けようとする。僕はどきどきしながら彼が次に言うことを待った。
「そのときはそれきりだった。でも、いつからか君がカフェに通ってくれるようになって、ジョージ・ミルズのことは少しだけ頭から抜けてたんだ。ああ、なんて言うか、君が俺を……見てただろ。それが嬉しくて」
「え、わ、わ、ごめ、ごめん。僕そんなに」
「嬉しかったんだから、謝らないでよ」
慌てる僕に笑いかけるピーターは格好よくて、僕の顔は途端に真っ赤になってしまう。やっぱりばれてたんだ、って恥ずかしいのと、嬉しいとピーターが言ってくれたことが僕も嬉しいって気持ちと。
「ど、どうして嬉しかったの?」
「え?」
ピーターのきょとんとした顔で、僕は何かおかしなことを口にしてしまったんだということに気がつく。
「どうしてって……」
ピーターの頬がさっと赤くなって、彼はそれからぼそぼそと、君のこといいなって思ってたから、と続ける。
「だ、だからさ、トミーか、ギブソンだったか……それはちょっと忘れちゃったけど、君がカフェで友達からジョージって呼ばれてたとき、すごくどきどきしたんだ。もしかしたら君がジョージ・ミルズなんじゃないかって。君がカメラを持ってるのは見てたから……本当は、それより前に君にジョージ・ミルズのことを訊こうかとも思ったんだよ。カレッジの学生でカメラを持ってるなら知り合いの可能性が高いだろ。でもそれじゃ打算になっちゃうからできなかった。君を僕とジョージ・ミルズの仲介役にしようだなんて……最低だ」
こんなに饒舌なピーターを見るのは初めてな気がする。それに、いつかのトミーとのやり取りが思い出されて僕は勝手に舞い上がった。トミー、やっぱりピーターは素敵な人だよ。
「でも、君がジョージ・ミルズだった。こんな奇跡ってきっとなかなかないと思う」
そうして彼は僕をぱっと見た。
「だけどすごく時間がかかったから……君を探して、君の名前を知るまで、俺、きっと君にたくさん厭な思いをさせたと思う。本当にごめん」
まっすぐなピーターの深い灰青の瞳。その目が僕を見つめている。
「だから、君の笑顔がほしいし、君の横顔がほしいんだ。だって、君だって『Helios』だし、『One Of Us』だろ? もっとも、俺にとっては……それ以上だ」
――真っ赤な顔で僕を見つめてくれるピーターを見ていたら、不意に鼻の奥がつんとして、目の周りがにじんだ。
「……ジョージ?」
ピーターの焦ったような声。僕は俯いて首を振るけど、涙が止まらない。何度か両手で拭ったけど無理だった。ピーターは僕の肩に触れて、それから僕をぐいと彼のほうに抱き寄せた。ピーターの全身の、熱いほどのぬくもりが僕を包む。
「……泣かないで……」
「うう……」
僕は、そうっとそうっとピーターの背に腕を回した。不思議と心地よい熱さと、ピーターの背中にある骨の感触。ピーターの大きくて、だけど薄い手のひらが僕の後頭部に優しく触れて、そっと僕の頭を彼の肩口に寄せてくれた。
「……ぴーた、鼻水出てきたから……」
「……ふふふっ、全然構わないよ」
ピーターが笑うと、僕の髪の毛が揺れる。僕は鼻をすすって、背中を優しくさすってくれるピーターのお言葉に甘えて彼にすり寄った。
「おい」
鋭い声が飛んできた。顔を上げて僕らが同時に振り返ると、険しい表情をしたアレックスと、彼の後ろに少しだけばつが悪そうに眉を寄せたおじさんがいる。ピーターが、あ、と小さく言った。
「何やってる、ピーター。こんなとこで……あ! お前! 何ジョージ泣かせてんだ!」
僕を見て瞠目したアレックスが慌てて僕らに駆け寄り、僕をピーターから引き離した。
「違う! あ、違わないけど!」
「何がだ! はい、すいません、ジョージのおじさん。取り返しました」
「あ、ああ……? ありがとう?」
そのまま僕はひょいと困ったような顔をしているおじさんのほうへ押し出されてしまう。おじさんは僕の顔を見て、それからその丸い親指の腹で僕の目許をぬぐってくれた。
「アレックス!」
「周りを見ろよ! お前たちだけじゃないんだぞ。まったく……」
「そ、それはごめん……」
呆れたようなアレックスと悄然としたピーターのやり取りが聞こえて、僕は真っ赤になってしまう。恐る恐るおじさんを見ると彼は相変わらず困ったように微笑んでいて、すまない、と謝ってくれた。
「入りづらくて……そうしたら彼が来た。彼もカフェの人だったな」
「ご、ごめんなさい……」
おじさんはゆるりと首を振る。
「君にいいことがあったなら、それでいい」
やわらかい彼の声音と笑顔が僕の心にしみこんでくる。僕はこくりと頷いた。たくさんの優しい人たちといいことに囲まれて、僕は今きっと……とても大切なことに気づいたんだ。
◇
それから、用事があると言うおじさんと別れて、ピーターとアレックスはそのまま僕たちの展示の撤収作業まで手伝ってくれた。アレックスはすっかりその場の空気に馴染んで軽口を叩いたりしているし、夕方に展示室に戻ってきたトミーに、君の作ったライト言い値で買いたい、なんて言って彼を困惑させていた。
「はい、どうぞ」
ピーターは壁から取り外したたくさんの僕の写真を差し出してくれる。ありがとう、と言って受け取ろうとすると指先が触れ合って、僕はどきりとした。いつまで経っても彼と体のどこかが触れ合うことに慣れない。
だけど、不意にピーターが写真を受け取る僕の手を握った。
「ぴ、」
「ジョージ」
「は、はい」
ぎこちない返事をする僕を見つめるピーターの目は真剣で、心臓がばくばくするのが収まらない。
「これからも、君の傍にいていいかな」
「え……」
ぱあっと赤くなるピーターの頬。彼は口許をもごもごとさせて、こんなこと言うなんておかしいと思うけど、と続けた。
「君とずっと一緒にいさせてほしい」
――僕は言葉に詰まってしまって、ピーターをただただ見返すだけになってしまった。ピーターはじっとして僕の返事を待っているように見える。
僕は、大きく頷いた。
「僕も……ずっと君の傍にいたい。……いさせてくれる?」
「当たり前だろ!」
ピーターにいきおいよく抱きしめられて、僕は声をあげた。そうしたらギブソンやトミーが、はしゃぐなよ、なんておかしそうに囃す。アレックスは大きくため息をついて、それから、しょうがないやつだな、なんて笑っていた。
カレッジからの帰路、いつもの分かれ道で僕らは別れの挨拶を交わす。街中のほうへ向かうギブソン、トミー、アレックス。街灯のオレンジの灯りが縁取る三人の後ろ姿をじっと見つめてから顧みると、僕の隣にはピーターがいる。
「行こっか」
不意に彼が手を差し出してきて、僕はどぎまぎした。ん、と、やわらかく笑う彼がもう一度その手を促す。僕はそうっとその手を取った。細く凛々しく骨ばって、でもあたたかくて、ほんの少しだけしめっている。手をつなぐとピーターは他方の手で彼の鼻先をかいた。
「俺、緊張してる」
「……なんで?」
「……君んちに行ったら、キスをするつもりでいるから」
僕はびっくりして飛び上がりそうになってしまう。ピーターは僕の手を軽く引いて歩き出した。おぼつかなくついていく足がもつれそうで怖いけれど、ピーターが振り返って笑うからがんばって歩く。
僕んちに行ったら、僕は彼とキスをする。
ピーター、そしたら僕、きっともっともっとって願ってしまうよ。
それでも、君の傍にいてもいい?
◇
「すみません、恋人がいるので」
ピーターはずいぶん得意げな表情でそう言うと、カウンターから少し離れたところで居たたまれなく様子を窺っていた僕を手招きする。そうして彼はぱちりと僕に目を合わせ、ゆるやかにそれを細めた。とても格好いい笑顔。僕の顔は真っ赤になって、心臓はばくばくし始める。
カウンターの前にいたお客さんがはけて、僕の順番が来る。ピーターは昨日の熱っぽさなんか忘れたふりをして、軽やかに、いらっしゃいませ、と言った。
「何にする?」
細く凛々しい指先がカウンターの上を滑り、ひょいと手のひらが上を向く。その五本指がゆるりと動いて、僕は誘われるままに片手をその手に重ねた。ほんの少し、しめっている。
「……いつものやつ、を、テイクアウェイで」
「ふふふ」
かしこまりました、ピーターはそう言ってカウンターの下からカップを取り出し、そっと僕の手を握ってから解放する。ペンを取り出してさらさらとメッセージを書きつけたそれをアレックスに手渡すと、彼は、はいはい、と呆れたように受け取って、慣れた手つきでホットのバニララテを作り始める。
カードを出して支払いを済ませると、ピーターは、がんばってね、とやわらかい声で言った。それから、また夜にね、とも。僕はいよいよ耐え切れなくなって俯いたままこくこくと何度も頷くしかできなくて、アレックスが僕を呼んでくれてからようやくぎこちなく動き出すことができた。
「ほら、どうぞ」
「ありがとう……」
「熱いから気をつけてな」
優しい声に僕はまた頷く。もうじゅうぶん熱いよ。僕は、それじゃあ、と言ってそそくさとカウンターの前を辞去し、店を出ようとする。
「気をつけて」
ピーターの声に僕は振り返り、けれど目は合わせられなくて、首肯だけしてみせる。軽やかに鳴るドアベルがのん気で憎らしい。
カフェから少し距離を開けて、僕はようやくカップの側面を見た。
『u r special』
「ふうわああ……!」
しゃがみ込んでしまった僕を咎める人はない。真っ赤な顔を屈めた膝に押しつけて、僕は唸る。
『少しずつ、一緒に慣れていこう』
昨日初めて聞いた、ピーターの低くて甘やかな声が、全然うまくできない僕の髪や頬や肩を優しく撫ぜる手のひらが、その体温が、その肌の感触がよみがえる。照明を落とした部屋のなかでも光を湛えた金髪。灰青の瞳は滲んできらきら揺らめき、そのなかに僕の影を映して、凪いだ海のように穏やかでいる。濡れて赤が濃くなった唇。きれいな形の鼻先についている汗の雫。その呼吸、全部好き。
もっと、もっとって、僕は願ってもいいんだ。
嬉しくて、僕は昨日、たくさん泣いてしまった。