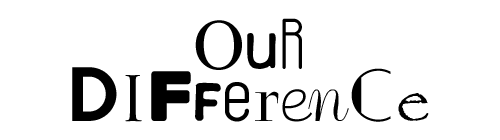街中で、クラスメイトのジョージ・ミルズを見かけた。隣にいる背の高いブロンドは去年卒業したピーター・ドーソン先輩だったか。年齢や男女の別なく人気のある先輩だなと思っていたけれど、ジョージ・ミルズとも仲がいいとは思いもよらなかった。ドーソン先輩が在学していたころ、彼らが一緒にいるのを見かけたことはない。まあ単に俺が興味を持っていなかっただけかもしれないけれど。
ジョージ・ミルズはクラスでもおとなしくて目立たないやつで、俺も会話した記憶がほとんどない。そもそも俺みたいなやつとあいつみたいなやつでは友人にもなれない。ギークっぽいかというとそうでもなくて、はっきり言ってしまえばこれといった取り柄のないやつだ。普段から一緒に行動するクラスメイトも思い浮かばないし、かと言って孤立しているかというとそういうわけでもない気もする。ともかく俺はあいつについてさほど印象を持っていない。
前を行くミルズとドーソン先輩は俺と向かう方向が同じようだ。なんとなく居たたまれなくて少しだけ歩くスピードを緩める。ミルズはドーソン先輩の話を聞きながらにこにこと楽しそうに笑っていて、それは俺や、クラスメイトの誰も見たことがない表情なのではないか、と思う。少なくとも俺はあいつの無表情しか覚えていない。ドーソン先輩がミルズの耳許で何かぼそぼそと言い、それにミルズはたいそうおかしげに笑って、軽くドーソン先輩の腕をたたいた。そのまま手のひらは腕をすべり、二人はごく自然に手をつなぐ。ドーソン先輩が、ミルズの頬にキスをした。
あー、そうなの。
ははあん、と俺は頷く。お二人は付き合ってんのね、あらそお。意外も意外だ。ドーソン先輩なら、何もミルズじゃなくてもより取り見取りだろうに。ていうかもしかしてミルズが一方的に言い寄っていてドーソン先輩は情けで付き合ってやってるとか。そっちのほうが可能性は高いよなあ。あいつ、友達いないくせしてそういうのはいっしょけんめなんだな。でも、傷つく前にやめたほうがいいよ。別に、友達でも何でもない他人のことだからわざわざ忠告したりはしないけど。
二人は並んで映画館に入っていく。俺はその前を通り過ぎてマーケットに向かう。二人はどういう映画を観るんだろうな。そういう趣味も合うようには見えないけど。
翌日学校で会ったミルズはやっぱり無表情で、昨日のドーソン先輩に見せていた笑顔は全体どうやって作ったんだと思うくらい表情筋が動かない。俺も別に話しかけはしなかったけど、なんとなくあいつがクラスのなかでどういう振る舞いをするのか見ていた。ミルズはよくグリゴリー・アボットとロイド・マクダネルと会話していて、そのときはちょっとだけ笑っている。あいつらもまあ、イケてもなければイケてないわけでもない中途半端な連中だ。類は友を呼ぶ、そんなところだろう。そのうち俺も仲間の一人に話しかけられて、やつの姉ちゃんの話で盛り上がって、その日はミルズについてはそれっきりになった。
また、街中でミルズを見かけた。しかもまた誰かと一緒にいる。学校の先輩でも友人でもない、見たこともない大人の男だ。ドーソン先輩とはまた違う、物憂げな雰囲気のブルネットのハンサムは、遠目からでもわかる彫りの深い目許とその奥の薄い青の瞳が印象的で、正直俺は二度と彼の見た目を忘れないと思う。
ミルズは彼の腕に手を回して、ぴとりとくっついている。会話する距離はあまりに近く、先日ドーソン先輩といたときと同じような満面の笑みで、ミルズは彼の肩に頭をすり寄せた。男は自然な仕草でミルズの髪の毛に口づけ、ずいぶんと優しい手つきであいつの頭を撫ぜている。
ちょっと待て。ちょっと待て? ミルズってドーソン先輩と付き合ってるんじゃないの? というか、付き合ってもらってるんじゃないの? その様子どう見たって付き合ってるよな? しかもずいぶん年上の男だよな? やばいんじゃないのか? あいつ、もしかしてだまされてるんじゃないのか? それとも逆にミルズがあの男をだましてるのか?
なぜか俺はパニクってしまったが、ミルズの髪を撫ぜていた男の肘のところに中身の入ったエコバッグがぶら下がっているのにようやく気づいた。よく見るとミルズの片手にも同じようなのがあって、二人が買い物帰りだということに思い至る。もしかしてこのあとどちらかの家に行って……食事をして……いや、待て待て、下世話! 俺下世話すぎるな!? きっとあの男とミルズは身内かなんかなんだ、見た目全然似てないけど。それであんなに距離も近いんだ、俺だったら家族とべたべたするなんて絶対厭だけど。
モヤモヤしている間に俺はすっかり二人の姿を見失っていた。歩道でぽかんと立ち尽くしている俺の名を呼ぶ声が聞こえて、振り返るとゾーイがにこにこ笑顔で走って来るのが見える。俺はゾーイに抱きつかれるまま彼女の頭を撫ぜてそのおでこにキスをして、これってなんだかさっき男がミルズにやってたやつみたいだな、と思ってしまって渋面になった。どうしたの、と訊かれて、どうもしないよ、と答えたけど、正直どうかしてしまいそうだ。
翌日学校で会ったミルズは相変わらずの無表情だったけど、俺はどうしてもどうしてもこないだのことを訊きたくて、やつが一人自分のロッカーの前でモバイルをいじっているところに割り込んで声をかけた。
「なあ、こないだ街中でお前のこと見かけたんだけど」
「……へ?」
きょろりと見上げてくるミルズの目が青い色なのだということを俺はこのとき初めて知ったし、やつの声が意外と高くてやわらかめなのだということも初めてわかったし、やつと俺の身長差が結構あることにも初めて気づいた。
「えっと……それがどうかしたの?」
ミルズのほうもこれまで会話したことのなかった俺が急に話しかけてきたから戸惑っているんだろう、少し不安げな様子な上目遣いをするものだから、俺は一つ咳払いをする。
「二回。ドーソン先輩と歩いてるとこと、全然知らない大人と歩いてるとこ」
「うん?」
「お前、どっちともいちゃついてたよな。二股かけてんの?」
ミルズは口をぱくりと開けて、それから真っ赤になって大きく首を振った。
「まさか、二股なんて!」
「じゃああれって何?」
「あれって……」
やつが言いかけたとき、廊下の向こうから仲間が俺を呼んだ。ミルズがぱっとそちらを見て、呼ばれてるよ、と言う。知ってるよ、でも俺はお前の話が聞きたいんだけど。そんな俺の内心も知らずに仲間は俺の傍まで来て、ミルズをちらりと一瞥して俺の腕を引く。ミルズはすっと一歩下がって俺から離れた。
「あいつと何喋ってたの?」
「……別に、なんでもないよ」
俺は後ろを振り返る。ミルズはもう俺のほうを見ていなくて、ロッカーからノートを出しているところだった。
結局その日はミルズと喋る機会はなくて、俺は翌日の休み時間にやつと再戦した。今度は誰にも邪魔されないように校舎の端っこの人気のない階段前まで引っ張っていくと、ミルズはやっぱり困ったように眉を下げて、君に関係ないことなのに、とぼやいた。
「お前がもし二股かけてんなら最低なやつだし、そうじゃないなら、あんなふうに街中でべたべたしてるのを俺みたいに見かけたやつが勘違いするだろ」
「だから、二股じゃないって……それに、勘違いしたのは君の勝手じゃないか」
こいつ、意外とはっきり口答えするな。普段のおとなしい様子からは想像ができなくて俺はむっとする。ミルズは俺を見上げてきて、もう街中で二人とべたべたしたりしないよ、と口を尖らせた。俺は慌てて、そうじゃない、と口にする。そこの自由はどうだっていいんだ、俺だってゾーイと街中でいちゃつくし、キスもする。でも俺はゾーイとだけだ。お前はそうじゃなかった。そういうことを言ってるんだ。
ぺちゃくちゃと言い訳みたいなことを並べ立ててから、俺はミルズがずいぶんと興味なさそうな様子なのに気がついた。一方的にしゃべり過ぎてしまったようだ。
「だ、だから、気になるだけなんだって。だまされてるわけじゃないんだよな? お前とあの二人ってどういう関係なの」
「だますって、どういうこと? 付き合ってるんだよ。君とゾーイ・シャノンみたいに……あ、厳密には、君の言う大人のほうの人とはまだなんだけど……彼は僕が十八になるまで待っててくれてる。でも、お願いしたらキスはしてくれるんだけど……」
「…………」
言っていることがよくわからなくて俺はミルズを見つめたまま黙り込んでしまった。ミルズは首をかしげて、どうかしたの、と訊いてくる。
「君の知りたいことに答えたよ」
「……うーん……訊きたいこと増えたかも」
「えーっ、困るよ……」
心底厭そうな表情をしたミルズはちらちらと廊下の向こうを見ていて、クラスに帰りたそうな雰囲気を醸し出している。俺はやつの腕を取って、もうちょっと待って、と言った。
「二人と同時に付き合ってるってこと?」
「ちょっと違うかも……三人で付き合ってる」
「ん? ドーソン先輩とあの男も付き合ってるってこと?」
「あれ? そう言われるとちょっと違うのかな。でも、二人もお互いのことちゃんと大事に考えてるよ」
「んん……? えっと、じゃあ、あの男が待ってるっていうのは」
「僕が成人するまで」
「ああ、そういう……」
「ねえ、もういいだろ」
ミルズはやつの腕を握っている俺の手を目線で見下ろし、眉根を寄せてこちらを見上げた。ごめん、と言って手を離すとやつは、ありがとう、と言ってさっさと足を踏み出す。廊下を行くその後ろ姿にためらいは何もなくて、俺はやつの後ろを歩きながら俺よりも小さな背中を見つめた。
やつから少し遅れてクラスに戻るとミルズはクラスの奥のテーブルに着くアボットの隣にいて、何かノートを見せ合って会話している。その向かいではマクダネルがコミックを読んでいた。
あの二人は知ってるのかな、ミルズのこと。
そんなことを考えながら俺も手前のテーブルを囲むいつもの仲間のところに行く。ゾーイが席を移動してきて俺の隣に坐り、ここの問題がわかんないんだけど、と言いながらノートを見せてきた。俺もわかんない、と言いながら顔を寄せると、ペンを握るゾーイの指先の色が昨日までとは変わっていることに気づいた。
「……あれ、ネイルの色変えた? 昨日までグリーンだっただろ」
「あ、うん。きれいでしょ」
「きれいだけど、あんまりこういうピンク好きなイメージなかった」
「そっかな? 最近ピンクも好きだよ」
「そうなんだ」
俺はゾーイの部屋のアイボリーの壁やベージュのタンス、白いベッドカバーやカーテンの脇に揺れる落ち着いた色の観葉植物を思う。あの部屋のカーペットが今のゾーイのネイルのような濃いピンクになることが想像できなくて首をかしげると、素知らぬ彼女は隣で、あっわかった、と嬉々とした声をあげてノートに向かった。
離れたところに坐っているミルズに目を向ける。俺の位置からはやつがテーブルに向かっている横顔しか見えない。俺と同じ制服を着ているやつの鼻先や尖った上唇のシルエット、ときどき見えるペンを動かす丸い手は、俺ともアボットともマクダネルとも、クラスの誰とも同じじゃない。ゾーイがいつも選ぶネイルの色も、クラスの誰とも同じになったことはない。
ミルズのあの鼻先が、あの唇が、あの手が、あのまったくタイプの違う二人に分け隔てなく触れるのか。
……いや、待て待て、俺やっぱり下世話すぎるな!? 渋面になる俺に気づいたゾーイの濃いピンクの指先が、俺の頬をつねって楽しそうに笑った。