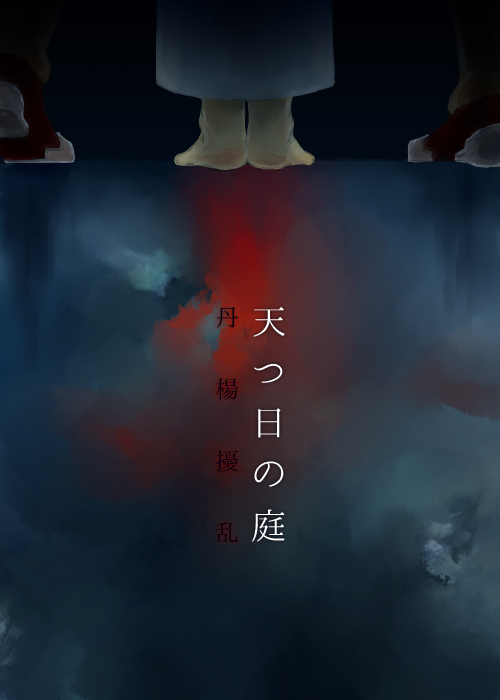孫翊の体をそっと地面に横たえた徐元は、辺鴻を睨みつけたまま立ち上がる。彼が戸惑ったような表情を浮かべるのを見据え、腰に提げていた剣をゆっくり鞘から引き抜き構えると、殺してやる、と口にした。
「殺してやる!」
「元、私は――」
徐元が飛びかかり振り下ろした剣を、辺鴻は寸でのところで受け止める。彼の構える剣についた血を見て、徐元は更に腕に力を込めた。
「なぜそいつを庇うんだ、元!」
辺鴻は力の限り剣を薙ぎ払い、徐元の体を突き飛ばした。地面に倒れ込みながらもすぐさま立ち上がった徐元は、踏み込んでなおも辺鴻に斬りかかる。ギン、と鈍い音を立てて剣同士がぶつかった。やめてくれ元、と辺鴻が絞り出したような声で言うのに、徐元の表情が怒りに燃えた。
「文寛どの、軽蔑します! 俺は罪びとにかける情けなど持ち合わせてはおりません!」
辺鴻の体を剣ごとはじき返した徐元は、勢いのまま刃を振り下ろした。得物を構え損ねた辺鴻の体が、左肩から腹にかけてえぐれるように切り裂かれる。膝から崩れ落ちた辺鴻に背を向け、徐元は地面に横たえた孫翊の下へと走り出す。
「叔弼様、叔弼様あっ……誰か!!」
抱え上げた孫翊の体は十二月の夜気のためだけでなく冷たくなっている。見開かれたままの瞳の黒い色が闇を湛えて凝っている。徐元の目からこぼれた涙がその頬にひたひたと滴を打ちつけて流れていった。
徐元は、政堂の玄関に立っていた二人の男を思い出した。振り返れば、彼らは微動だにした様子もなく騒動をじっと見つめているだけだ。徐元は叫んだ。
「嬀都督、戴郡丞! お医者様を呼んでください!」
必死の彼の声にも、二人は反応を示さない。政堂の中から人の出てくる気配もなく、その空気の異様さに徐元は息を飲んだ。
「辺文寛」
そればかりか、男の片割れは謀叛人の名を呼ぶ。
「孫翊は死んだぜ」
「た、戴郡丞……!?」
――じゃり、と地面を踏みしめる音がして、徐元が振り返るよりも早く、生ぬるい腕が彼に後ろから抱きついた。
「元」
耳元で息を切らしながら謀叛人がささやく。心臓から冷えた心地がして、徐元は、ひ、と喉から引きつった声を発した。
「い――いやだ! いやだ……!! 叔弼様!」
腕をめちゃくちゃに振り回してまとわりつく腕を振り払おうとする徐元の手に、謀叛人の流した血がべとりとつく。ああ、と叫んだ徐元の肩を、跳ね飛ばされた辺鴻が引き倒した。
「ぐ、うっ」
「あいつの名を呼ぶな!!」
地面に転がった徐元の体に辺鴻が馬乗りになり、その頸に手をかける。目を見開いた徐元がその手を引き離そうともがくが、深傷を負った体のどこから力が出ているのか、辺鴻の体はびくともしない。
彼は目を血走らせて徐元を見据えている。
「私の方が、お前のことが好きだ……好きだ!! 元!!」
「い、やだ――しゅ、く、う……ぁあ……!」
「その名を呼ぶな、私を呼べ!!」
辺鴻の両手に力がこもる。
頭が真っ白になっていく。その頸を扼する己の手に重ねられた徐元の手の甘美な感触。彼の薄桃色の爪に引っ掻かれてできた傷。真っ赤に染まっていくその喉元――
…………
どれほどそうしていただろう。動かなくなった徐元の上に乗ったままの辺鴻の肩に、骨張った手がそっと置かれた。
「おい、そいつまで殺してどうするんだよ」
「…………」
戴員の声が聞こえているのかいないのか、辺鴻は静かに彼の上から退く。そしてそうっと彼の遺体を横抱きにして抱え上げると、ふらふらと覚束ない足取りで血の跡だけをその場に残し、厩舎の方へと姿を消した。
「子周、あれはどうするんだ?」
「さあなあ……放っといていいんじゃないかね。どのみちあの傷で動き回ったんじゃ助からんよ」
ふ、と鼻で笑った彼は、ちらりと孫翊の死体を見下ろして口の端を上げる。
「ちょっとからかってやるくらいのつもりだったんだがね。まあ、結果的にこいつを殺してくれたのは助かったが」
「それはその通り。手間が省けてよかったよ」
嬀覧はため息をつき、それじゃあ奥方のところに報告にでも行きますか、と肩を竦めて言った。
◇
夫である孫翊が死に、弟の徐元も扼殺され、さらにその遺骸を凶漢に持ち去られた、と侍女を通して報告を受けた徐氏は、呆然と言葉を失った。戸板に横たわり瞼を閉ざした夫の傍に膝をつき、彼女はようやくぽつりと、旦那様、と呟く。
「下手人の行方は現在捜索しているとのことです。しかし厩舎に向かったとの報告もあるので、よもや邑の外に出たやもと……」
「構いません。必ず探し出して裁いてください。わたくしから報奨も出します。どうかお願いいたします」
徐氏は早口にそう言うと、孫翊の遺体を奥に運ばせた。丁寧に遺体を洗い、着物を召し替えさせると、その傍に足をたたんで腰を下ろす。
「旦那様」
人払いをさせ、亡夫と二人きりの室の中。呼びかけても返事はなく、孫翊は無表情に目を伏せている。徐氏は、孫翊の少し掠れたような低い声が好きだった。その声が己と弟の名を呼び、その声が描く輝かしい未来が好きだった。
彼女は遺骸の傍らに添えられた、赤い房飾りのついた形見の剣を睨みつける。
「すぐに後を追えない不肖の妻を、どうか、どうかお許しくださいませ」
そっとその胸に顔を伏せると、常ならば穏やかに波打っているはずの鼓動が聞こえないことに彼女は不意に涙をこぼした。
夫と弟の仇を討ち、これから生まれてくる夫の形見を立派に育て上げなければ、己は彼の傍には往けないのだ。
翌朝早く、宛陵南部の丘陵地帯で、辺鴻、そして徐元の遺体が発見された。その遺体を見つけ、宛陵まで運んできたのは誰あろう、その近辺に集落を構える阜屯の十四、五歳ほどの三人の少年たちであった。早朝の警邏の途中、烏の大群が上空を旋回していたのを不思議に思い向かってみると、大木の根元に二人の遺体があったのだという。食われてはないみたいですよ、と一人が言い、別の少年に頭を叩かれていた。
自ら阜屯の少年たちを引見した徐氏は、謝意と共に報奨の旨を問うた。彼らは互いに顔を見合わせ、でしたら、とひとつの願いを口にした。
「僕らのことも孫討虜様の軍勢にお加えいただけませんか? 本当は僕らよりももう少し年が上じゃないと行かせてもらえないんですけど、あの……こっそりでいいので」
三人は徐氏の表情を伺うように上目遣いになる。それを受けて、徐氏は微笑した。
「わかりました。わたくしから主公に取り計らいましょう」
「本当ですか!」
わあ、と手を挙げて喜び合う彼らに徐氏は、ただし、とひとつ言葉を添えた。首をかしげる彼らの前に彼女はぴっと人差し指を立ててみせる。
「主公はただいま西で戦をしております。その軍勢が呉にお戻りになるまで、この宛陵の兵舎で他の者たちの振る舞いを見て学んでください。できますか?」
神妙な顔で頷く少年たちに、徐氏も笑みを深める。兵務を終えた後は必ず政堂の奥にある自分の室に戻ってくるように言いつけ、彼らの身柄を遣いに預けると、彼女は後ろに控える侍女たちを振り返った。
「――弟も私のところへ帰ってきました。葬儀の支度を始めましょう」
沈痛な面持ちで侍女たちが返事をしたとき、室の外から衛士の声がかかった。
「孫伯海様より面会のご要請です」
「伯海様……!」
すぐに徐氏が正庁へ向かうと、使いの孫高、傅嬰を伴った孫河が厳しい表情で坐していた。現れた徐氏の顔を見た彼ははっとなって立ち上がり、何か言おうと口を開いたようだったが、すぐに閉じてしまった。
「伯海様、このたびはこのような形になってしまって、なんと申し上げたら良いのか……」
「……いや、言わずともよい。……残念だった」
口許に持っていった手が下ろせずに、孫河はそのまましばし黙る。徐氏は彼を促して改めて坐らせると、自身もその前に腰を下ろして三人を静かに眺めた。
「……下手人、辺鴻は、亡き討逆様から丹楊の邸宅を賜ったわたくし共の隣人でございました。彼はその……あまりわたくし共と話すことは多くありませんでしたが、元とはとても仲良くしてくださいました。元も、一番近しい殿方でしたからよく懐いていたのです。元が旦那様とも知り合ってからは旦那様にもよくお仕えくださいまして……」
遠い目をして徐氏は言う。
「冷静になってよく考えてみれば、このようなことをなさる方ではないはずなのです」
「ですが叔弼様と令功は凶刃に斃れました!」
傅嬰が叫ぶように言うのをチラリと孫河は振り返った。
「俺だって文寛どのがこのようなことをなさるなんて夢にも思わなかった。けれど実際彼はし果せてしまったじゃないですか!」
「それは……そうなのですが……」
困ったような表情で俯く徐氏は、頬に手を当てて、なぜ、とぽつりと呟いた。
「弟を連れて行ってしまったのでしょう……」
正庁に沈黙が降りる。遠く聞こえる人の声が煩わしく感じられるほどの静けさの後、孫河がふと顔を上げて口を開いた。
「……ともかく、俺は嬀都督と戴郡丞のところへ行く。この一件は間違いなく彼らの監督不行き届きだ、譴責で済むものではなかろう。公崇、仲進。殿への伝令を引き受けてくれるか」
こうなってはお前たち以外に信頼できる者がいない、と言い、立ち上がる孫河に、重々しく頷き返して孫高と傅嬰も続く。後を追って立ち上がった徐氏は、孫河を呼んだ。
「どうか……どうか、お気をつけくださいませ」
「無論だ。そなたの申すことが真実であるならば、彼はただ一人では事を成し得なかったはずだ」
そう言い残して辞去する孫河を、足音を立てそうなほど大股でいきり立って歩いて行く孫高と傅嬰を、徐氏は不安げな面持ちで見送っていた。
政堂の前で孫高、そして傅嬰と別れた孫河は一人足早に郡丞の政務室へ向かった。衛士の静止も聞かずに勢いよく扉を開けた向こうには、目を丸くして孫河を振り返る大都督の嬀覧、そして郡丞の戴員がいる。おや、と嬀覧が口を動かした。
「これは、孫盧江様。遥々皖城よりご苦労様でした」
「労いは結構。この事態は一体どうしたことか」
眉間にしわを寄せて厳しい表情を作る孫河に、戴員はいかにも申し訳なさそうに眉尻を下げた。
「残念です。孫将軍の信頼篤かった辺文寛がこのような凶行に及んでしまったことは」
その言葉に目を細める孫河は、未然に防ぐことは本当に叶わなかったか、と口にした。
「聞けば下手人は、宴会に訪れた客を見送りに出ていた叔弼を後ろから斬りつけたと言うではないか。状況を見れば恐らく下手人に対応したのが徐令功のみであり、それゆえ彼も巻き込まれたのだろうとは容易に想像がつく。そのとき他の者らは何を――いや、お前たちは何をしていた?」
「…………」
一歩踏み出す孫河を見据えたのは嬀覧である。彼の様子を見た孫河は顎をついと上げて言い募った。
「太守を補佐すべき丞がそのとき太守の傍におらぬはずはなく、加えて配下たる辺鴻の凶行は兵を預かる大都督の統率が不足していた証左に他ならぬ。貴様らは二人を見殺しにしたのではないか?」
「まるで見ていたように仰る」
「容易に想像がつく、と申した。貴様らが職務を全うせぬからこうした変事が起きたのだ」
はっきりとそう口にした彼を、嬀覧は首をかしげて半眼で見た。
「随分な物言いですね。孫将軍ご自身に非があったとはお考えにならぬのですか?」
「それは辺鴻の悪事を看過したと認める発言か? 将に非があればそれを諌め正道へ導くのが貴様らの務めであろう!」
上衣の裾を翻して反転する孫河に、嬀覧は飛びかかった。何をする、と声を上げた孫河の体に抱き付くと、懐から勢いよく取り出した小剣をその心臓に、ぐ、と突き刺し、押し込むように体重をかける。倒れ込んだ彼から小剣を引き抜くと、もう一度胸にそれを突き立てた。
「は……」
「やっぱり、孫家の人間は孫家を庇うんですね」
更にもう一度小剣を突き刺し、孫河が事切れたのを見た嬀覧は文机に頬杖を突いてその様を見ていた戴員を振り返った。
「合肥の劉元頴どのに使者を送ろう。彼の軍に江北の歴陽まで来てもらえれば、決起するにはあとはこの丹楊にいる兵だけで十分のはずだ」
「その辺はお前に任せるぜ。可愛そうだ、丹楊の連中も。周大明はともかく袁術に呉景に孫翊……こんなに振り回されてなあ」
「よく言うよ。呉会の民には手を出さないと言い出したのはお前だろうに」
戴員がため息をつきながら言うのに肩を竦めて笑った嬀覧は、外の衛士を呼び寄せて合肥に州庁を構える揚州刺史・劉馥への書簡を持たせると、重々内密にね、と口元に人差し指を持っていって、彼に一緒に小銭を握らせた。
血を流して横たわる孫河の死体を見て驚いた衛士は、恐る恐る頷くと急いで駆け出す。扉から顔を出してそれを見送った嬀覧は、戴員に声をかけられて改めて室内に目を遣った。
「それはどうすんだ?」
「放っといていいだろう。それより、俺は行きたいところがあるんだ」
どこだ? と不思議そうに問いかける戴員に、嬀覧はニヤリと口の端を上げて笑った。
「もちろん、美しい未亡人と女たちのところに」
◇
城門まで来た孫高と傅嬰だったが、ふと孫高が立ち竦んだ。焦燥して振り返る傅嬰に、情けなく眉を寄せた孫高が問いかける。
「……本当にこのまま俺たちが討虜様のところへ向かっていいのか?」
「討虜様の弟君が殺されたんだぞ!?」
「そうだけど、そうじゃなくて!」
孫高は考えるように口元に拳を持っていく。
「だって、叔弼様がお見送りに出たなら、少なくとも戴郡丞も一緒に出たはずだろう? それなのに辺文寛どのはまんまと叔弼様と令功を殺して、そのまま――深傷を負った体で、一人分の男の遺体を担いで、邑の外まで逃げ果せてるんだ。戴郡丞や、そうだ、嬀都督がすぐに兵を派遣していたらそんなことできなかったはずじゃないのか?」
「お前、それって、まさか」
孫高は傅嬰の腕を掴んだ。
「戻ろう、伯海様のところに!」
来た道を引き返した二人は、役所まであと一里というところで見覚えのある顔が前方からやって来るのを見た。一方通行の城邑内の道路で、である。訝しんだ二人を彼も見止めたのか、ああ、と叫んだ。
「あれ? 貞成!」
「よかった、よかった! 公崇、仲進!」
二人に駆け寄ってきた李純、字を貞成は、思わず抱きつかんばかりの勢いで二人の腕を掴んだ。
「伯海様が、嬀都督に殺されてしまったんだ!」
「……!」
絶句する二人に、李純は続ける。
「嬀都督はそのまま政堂の奥に押し入って……ど、どうなったのかはわからないんだけど……い、一緒に来てくれ!」
あらん限りの力で引っ張られ、もたつきながら二人は李純の後に続く。連れて行かれたのは役所の脇門から入ってすぐのところにある、下級兵士のうち呉・会稽郡出身者の集まる宿舎の一室だった。
中に入れば狭い室内に、十名ほどの若い兵士が坐っている。その内の三名が見慣れぬ少年であることに孫高は首をかしげたが、ともかくも先の李純の言葉の真偽を確かめることが火急の問題であった。
「嬀都督が奥に入ったってどういうことだよ!」
「わかんないんだよ、も、もしかしたらずっと奥方を狙っていたのかも知れないし……」
しどろもどろになりながら李純はひとつの書簡を差し出した。嬀覧に駄賃と共に預けられたのだと言う。届けるわけないだろう、と李純は室の隅に向かって小銭を投げ捨てた。
「これ……劉刺史に宛てた密書か」
「うん、劉刺史の軍勢に歴陽まで出てきてもらって討虜様を釘付けにして、自分たちは丹楊で叛乱を起こそうって腹だ」
「まさか……討虜様に朝廷へ刃向かう意図があるわけない!」
若い兵士の中の一人、楊斯が、だからこうして劉刺史に書簡を送るんだ、と言う。
「曹司空から任命された劉刺史の後ろ盾を得た“義の叛乱”を鎮圧すれば、討虜様はそれだけで逆臣のそしりを受ける」
それを聞いた李純はぽつりと、俺に預けてくれてよかった、と呟いた。
「公崇、仲進……叔弼様と、令功と……伯海様のこと……本当にごめん」
「……俺たちに言うなよ……いや、俺は、三人の仇を取る。間違いなく嬀都督と戴郡丞が仕組んだことだ。討虜様の江東をあいつらの好き勝手にはさせない」
立ち上がる傅嬰、彼に迷いなく続こうとする孫高の二人を引き留めたのは、別の一人、賈聘だった。
「俺たちだっておんなじなんだ。さっさと先に行かないでくれよ」
「けど……こうしてる間に今度は奥方様に何かあったら」
戸惑う孫高に賈聘は、あの見知らぬ少年たちを示した。
「こいつら阜屯から来た奴らなんだけど、実は今朝方、令功と辺文寛どのの遺体を見つけて運んできてくれた連中なんだよ」
ぺこり、と頭を下げる三人の少年を、孫高と傅嬰はまじまじと見つめる。
聞けば彼らは直接徐氏と引見し、報奨にと“孫討虜将軍麾下への参入”を求めたらしい。現在西の地で戦争している彼の帰還を待つために、しばらくの間この丹楊で兵務に励み――その監督を任されたのが楊斯や賈聘であった――一日の終わりには必ず徐氏の下へ戻って来るように言い付かっているのだという。
「こいつらは、奥方様に会えるんだ。それは彼女が直々に許したことなんだから、誰にも阻むことはできないだろう?」
そう言って肩を叩かれた少年の一人が、そうですよ、と少し大きな声で言った。
「俺たちのこと使ってやってください。大丈夫、阜屯の虎の民はそう簡単にくたばりませんから」
頼もしい仕草で胸を叩く彼の着物の衿に見覚えのある紋様を見て、ああ、と孫高と傅嬰は納得した。数年前まで、今の孫討虜――かつての孫孝廉の側仕えが着ていた一張羅によく似ていた。
「そんなら、お前らに用間を頼まないとな。嬀都督には十分に気を付けて……奥方様のこと気遣ってやってくれ」
そうして三人の阜屯の少年たちに自分たちの思いを言付けると、孫高たちは彼らを徐氏が控えているはずの政堂の奥の室へ向かわせた。他方で彼らのうちで最も馬術の上手い項謙に西にいる孫権への伝令を依頼すると、彼らは改めて策謀を成すための会議を始めた。
少年の一人、孔援が奥の室に続く回廊の前に立つ衛士に挨拶をすると、彼は神妙に頷いて三人を奥院の正庁へと導いた。奥方様に決して無礼のないように、と噛みしめるように言う彼は、そのまま足早に戻っていく。
「奥方様、孔援、澤季、申彪、ただいま戻りました」
「はい、どうぞお入りなさい」
緊張した面持ちで入室する三人を、席に坐った徐氏が迎える。脇には一名の年若い侍女が控えているのみで、他には誰の姿も見えない。
「……あの、他に、誰か、いらっしゃいます?」
「いいえ、おりませんよ」
徐氏は手招きして三人を傍近くまで寄せると、兵務は大変でしたか、と微笑を浮かべて問うた。
「は、はい。大変でした。でもあの、楊さんと賈さんがお優しかったので」
「それはよかったですね」
何度も頷いた徐氏に、澤季がぐっと眉をひそめて小声で言った。
「――僕たちも大変な役目を承りました。あなた様をお救い申し上げ、逆賊を誅滅するための、大変な役です」
まあ、と徐氏は目を見開き、脇に控えている侍女も驚いたように三人を見た。すぐに彼女は立って扉の傍まで近づくと、外の様子を窺うようにそっと扉を開ける。振り返り頷いたのを見て、徐氏もさらに三人の傍へとにじり寄った。
「嬀都督がこちらまでいらしたのは存じ上げておりますね」
「はい、僕たちそれで」
「よろしいのです」
徐氏は手のひらを向けて彼らが話し出すのを制すと、努めて小さな声でこう言った。
「伯海様が彼の手にかかって亡くなられたことも聞いております。わたくしの側仕えだった女たちも皆、彼のために人身御供となりました。無体はせぬよう言い含めておりますが、どうなってしまったかはもはやわかりません」
彼らがいるはずのかつての孫翊の居住区域の様子は奥からは全く見えない。徐氏の憂悶の表情に、三人も、ただ一人残された侍女も胸を痛める。
「彼はわたくしをも手籠めにしようとしましたが……もう晦日も近いので、月末に法事を執り行いまして喪明けするまではとお待ちいただいたのです。存外、聞き分けの良い方で助かりました」
ふと彼女が口元に浮かべた笑みに、少年たちは背中が粟立つのを感じた。
それは、奸計を成す人間の、どこか軽薄な笑みである。
「そちらに孫公崇、傅仲進はおりますか? もう外へ出てしまったでしょうか」
「お、おります! 嬀都督と戴郡丞の悪だくみに気づいて、引き返して来てくださったのです。孫討虜様への伝令は項さんが向かいました」
「そうですか、それは何より」
徐氏はぴっと人差し指を立てた。
「わたくしは嬀都督と戴郡丞を殺す策略を立てました。それには皆様のご協力が必要不可欠です」
「は、はい」
「明日、皆様方にお会いしましたら、お伝えください。晦日の夜、亥の初刻に政堂の裏手までお越しくださいと。そこで皆様方を中へ引き入れ、わたくしは嬀都督を奥へ招き入れます。他方、戴郡丞のことも討っていただきますが……これは皆様方の策略にお任せしたく存じます」
お願いできますね、と尋ねられ、少年たちはこくこくと何度も首肯した。それを見て安堵したように微笑んだ徐氏は、正庁の隅に用意させた布団を示す。
「こんなことになるとは思わなくて、皆様方にはこちらでお休みいただかなくてはなりません。今、わたくしに許された領域はここしかないのです」
しおらしい態度の徐氏だが、三人にはもはやこの正庁が虎穴のように思えてならない。わかりました、と頷いた彼らは、明日のことを思って眠れぬ夜を過ごした。
◇
――建安八年、晦日。一年の闇をとっぷりと湛えた丹楊の街を、若い兵士たちは政堂へ向かって駆けてゆく。孫高と傅嬰は奥院の徐氏の下へ、残りの兵士たちは嬀覧と戴員の居坐る役所の小門へとそれぞれに分かれた。
政堂の裏手に来た二人を引き入れたのは、奥院の回廊を守衛している衛士の一人である。どうかよろしくお願いします、と彼に懇願され、二人は強く頷く。
まっすぐに奥の室に入ると、徐氏はいなかったが代わりに年若い侍女が坐して二人を待っていた。
「奥方様はただいま正庁で法事を営んでおります。お二方にはこちらをお召しいただくよう言いつかっております」
「こちら……って……」
侍女に差し出された着物は、どう見ても今彼女が来ている女物の着物と同じものである。
「こ、これを俺たちが……?」
「計略のため、どうかお聞き入れくださいますよう」
「うわあ……お女中さん、気味悪がらないでくださいよ」
傅嬰が言うのに、侍女は表情を動かさずただ頷く。無反応なのも寂しい、などと思ってしまう二人は、そそくさと言われた通りに召し替えた。最後に彼女に差し出された布を頭から被れば、遠目には正体がわからなくなる。
「見えないかな、大丈夫?」
「はい。お二人には私どもの中に紛れていただきますので」
侍女の言葉に二人は首肯した。
孫翊と孫河、そして徐元がその命を落としてから七日が立ち、ついに徐氏が喪を明けさせる日が来る。練りに練った――とは言いにくい計略だが、成さねばならない。しかし、徐氏がたったひとつだけ彼らに課した制約のことが気にかかる。
程なく、徐氏と彼女の側仕えである侍女たちの足音が聞こえてきた。法事の間くらいは、と嬀覧は侍女たちを解放してやったのである。奥の室へ入って来た彼女は、沐浴を済ませてきたのかほのかに甘い香りをその身にまとっていた。室の中に孫高と傅嬰の姿を確認した彼女は、あら、とおかしそうに口許に手を当てて笑う。
「お二方とも、お可愛らしいですわ」
「うぐ…………」
唸る孫高と頭を抱える傅嬰である。
徐氏は侍女たちをすっかり奥の室に入れてしまい、几帳を立て巡らせた。布で仕切られた室内で、彼女は侍女たちに努めて楽しい会話をさせるよう仕向ける。そうは言われても咄嗟には話が出てこない侍女たちは、孫高と傅嬰の女装姿に目を向けながらおかしそうに話をしだした。
「ずっと嬀都督の目がありました」
居た堪れない気持ちの彼らに、空虚な賑々しさの中に小さな声で徐氏は語りかける。
「戴郡丞の方は首尾よくいきますでしょうか」
「皆、叔弼様と共に鍛錬を重ねた仲間たちです。……あなた様のお言いつけもなんとか守りますよ」
それだけが枷なのだ。しかし、徐氏は少しも悪びれない風に笑う。
しばらく歓談していた彼女たちだったが、もう良いでしょう、との徐氏の言葉に、一人が立ち上がり扉の外に控える衛士に入室を許可する伝言を預ける。
彼が去って半刻もせぬうちに、嬀覧の来訪が告げられた。几帳から表へ身を翻して出て行く徐氏の背中を見つめながら孫高と傅嬰はほとんど同時に唾を飲み込み、息を殺す。身を低く沈める彼らとは対照的に、その周囲を固める侍女たちは背筋を伸ばして胸を張った。
「失礼いたします」
嬀覧の鋭い声がした。扉が開かれ、こつん、こつん、と足音を立てて彼は歩いてくる。徐氏は膝をつき、指を床について深々と頭を下げた。
「このたびはわたくしのわがままをお聞き入れくださいまして、本当にありがとうございます。お待ちしておりました」
「いいえ、そういった貞淑なところも気持ちがよろしい方ですね。孫家に嫁がなきゃあもっと良い定めもあったやもしれないのに」
笑いながら彼が言うのに、そうでしょうか、と徐氏は返す。嬀覧は彼女の前に同じように膝をついて礼を返した。
「あなたからどう見えていようと、わたくしは幸せでございますわ」
顔を上げて徐氏は微笑む。
「そうですか。では俺がそれ以上幸せにして差し上げますよ」
それに続いて顔を上げた嬀覧は、彼女がにっこりと微笑む向こうで、几帳の布がひらめくのを見た。
「では、よろしくお願いします」
徐氏の言葉が放たれ、几帳の陰から二つの人影が躍り上がった。目を見開き、は、と息を飲む嬀覧が立ち上がる間もなく、その手に握られた刃が彼の体を深く斬りつける。噴き上がった血飛沫がその身に降りかかるのをまるで気にも留めず、徐氏は口許に笑みを浮かべたままじっと坐していた。
ダン、と激しい音を立てて床に倒れ込んだ嬀覧の、放り出されたその腕に、歯を食いしばった孫高が刃を突き立てる。アア、と叫んだ彼のもう一方の腕には傅嬰が同じように剣を突き刺した。
「――奥方様」
床にはりつけにされた嬀覧が、細い糸で繋がれた意識をどうにか辿って目線を動かす。着物を真っ赤に染めた女が、ゆらり、ゆらり、と己の方に歩み寄ってくるのが見える。その手に握られているのは、赤い房飾りのついた一振りの剣だった。
「孫君、傅君、足を抑えていてくれますか」
「…………、わかりました」
孫高と傅嬰は体重をかけて嬀覧の足を抑え込む。傍らに膝をついた徐氏が、剣を鞘から引き抜いて嬀覧の首筋に宛てがった。
「殿方には遠く及ばぬほど、非力な女の腕ですから、不調法でもお許しくださいませ」
「や、めろ……クソ……! ……孝章様……!」
ぐ、と力が込められていく刃に閃く光から、孫高は思わず目を逸らした。部屋の奥ですすり泣く侍女たちの立てる小さな音に気を向けていなければ、
嬀覧の悲鳴に気を失ってしまいそうになる。
◇
政務室の扉を勢いよく開けた孫高と傅嬰とを振り返った仲間たちは、ああ、としかめていた表情をほんの少しだけ和らげた。
「今、お呼びしようと思っていたところだったんだ」
二人の背後から姿を現した徐氏が、真っ赤に染まる腕に嬀覧の首を大事そうに抱えているのを見て、兵士たちの傍にいた阜屯の少年たちは渋面になる。
「戴郡丞ももう虫の息です。……お言いつけは守りましたよ」
徐氏が兵士たちに課したたったひとつの制約。二人を生かしたままにしておくこと。必ず己が手を下すのだと、虫を殺したこともないような面をした女がかつてそう告げた。
ありがとうございます、と彼らに謝意を述べて徐氏はその横をすり抜け、書簡を散らかして床に横たわる戴員の横に膝をつく。その傍らにそっと置かれた嬀覧の首を見て、畜生が、と戴員は息も絶え絶えに言った。
「孫権も、お前らも、全員、苦しみながら死ね」
「承知いたしました。ではまずあなた様に、その手本となっていただきましょう」
徐氏は今度、緑色の房飾りをつけた剣を振りかざした。
兵士たちには見覚えがあった――それは、徐元の愛用していた剣である。叔弼様とお揃いの房飾りを姉に作ってもらったのだ、とかつて嬉しそうに自慢していた彼の表情は、きらきらと輝いていた。
“同じように”徐氏は戴員をも殺し果せた。そうして嬀覧と戴員、二人の首を抱えて彼女は歩き出す。兵士たちもその後ろに続いた。
孫翊の墓前に首級を捧げ、徐氏と兵士たちは床に額をつけて深く深く礼をした。
顔を上げたとき、徐氏の目から涙があふれ出した。血のついた手で彼女は顔をすっかり覆い、泣き崩れてしまう。
「…………ああ、あ……」
その痛哭は静かな墓前に響き渡り、兵士たちもまた、二度と帰って来ない友を思って涙を流した。
◇
十日後、急報を受けて西から帰還した孫権の率いる軍勢が宛陵に到着した。
仇討ちを成した兵士たちが礼をもって彼らを迎え入れる。賊に与したものをすべて捕らえて牢へ幽閉している旨を孫高から聞いた孫権は、そうか、と短く答え、続けて言った。
全員の首を刎ねろ、と。
程なく、呉郡から孫瑜の軍勢も宛陵に着いた。事件の経緯と状況を説明された彼は、丹楊郡の太守後任に誰を選ぶか――或いは丹楊郡から手を引くか否か――に悩む孫権に、己を後任にしてくれないか、と直談判した。
「……ですが……」
「大丈夫だから。ね、お願いだ、仲謀」
孫翊、孫河と立て続けに親族を亡くしているこの地にこれ以上孫家の縁者を置いていてよいものか、と孫権は不安を抱いたが、孫瑜は屈託なく笑って彼の手を取る。
「これ以上、きっと誰も死なせやしないから」
孫瑜の笑みに、孫権は小さく頷き返す。
「よろしく……お願いします。仲異どの」
その言葉に、任せてくれ、と孫瑜は頼もしく胸を叩いた。
孫高、傅嬰を始めとする徐氏の仇討ちに与し逆賊討伐の功を上げた若い兵士たちは、孫権に目通りして彼の本陣を守る牙門将として取り立てられることとなった。その中には阜屯の三人の少年たちも含まれており、お前の後輩だな、と楽しそうに笑う孫権と朱桓に、谷利はなんとも言えず複雑な表情になってしまう。
徐氏と彼女の母は孫権がその身柄を引き取り、呉郡に邸宅を与えて住まわせることとなった。遠からず孫翊の子が生まれてくるのだ、と聞いた彼は至極嬉しそうに、そうか、と笑ったが、徐氏の心には、もし孫翊が、徐元がこのことを聞いていたなら、という思いがよぎる。
そして辺鴻の母は徐氏とその母の嘆願もあり、罪人の身内であるとする咎を受けさせぬよう丹楊から呉郡へと居を移させ、こちらもまた孫権がその身柄を保証することとなった。
「我が君、太守になるにはどうしたらいいんですか?」
呉郡に帰る途上、唐突な朱桓の問い掛けに首をかしげつつも孫権が答える。
「孝廉や茂才に推挙されて中央に出仕し、その才が統治に相応しいと認められたり、或いはそれまでの任地や役職で治績が上がればそういった能吏はどんどん出世していきますね。たまに郡や朝廷の官吏と気脈を通じたり賄賂を渡したりして任命してもらう者なんかもあるみたいですが」
「はあ……それって、きっと大変ですよねえ」
頭を掻きながら言う朱桓に、そうですね、と頷く孫権はやはり彼の質問の意図が見えないようだ。それは谷利も同じことで、どうかされましたか、と思わず問いかける。
朱桓は唸りながら、言った。
「ままならないなあ、って、ちょっと」
歯切れの悪い言葉だったが、その答えには二人ともどこか思うところがあって、口には出さずとも同意する。
建安九年は重苦しい空気をその身に纏わせ、彼らの足を絡め取って動けなくしたまま、自身は素知らぬふりで過ぎてゆくのである。