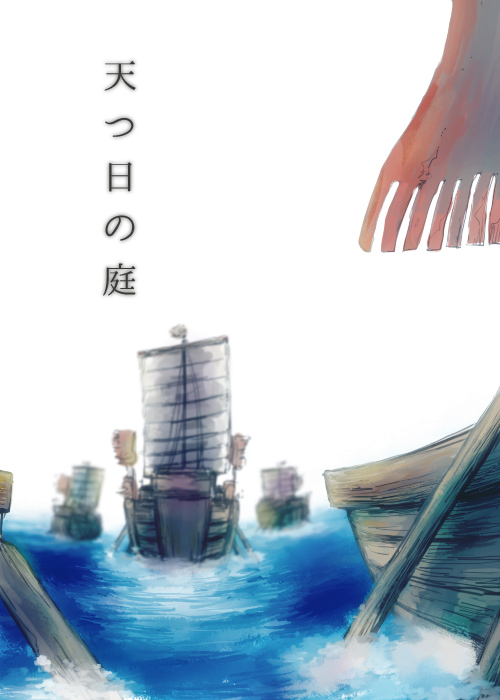お会いいただけないかと思いましたよ、と翌日持たれた会見の席で、開口一番に諸葛亮は言った。評定の間に同席する群臣たちがその不遜な態度に眉を顰める中、孫権が苦笑しながらなぜと問うと、
「何やら立て込んでいらっしゃるご様子でしたので。私がここへ来ることができたのも、ほとんど魯子敬どのの独断専行でしょ?」
「はは……否定はしませんが。諸葛どの、こたび我が軍は曹孟徳の軍勢に対して徹底抗戦の構えを取ります。劉軍とは互いに不可侵の協定を結びたいと思います」
それは重畳、と手を拱いて礼をする諸葛亮に、脇に控えている周瑜が不愉快そうに唇を結ぶ。使者を自軍に連れてきた手前、事態の推移を見ておかなければならない魯粛は周瑜の不機嫌な佇まいには冷や冷やするばかりである。
孫権は彼の発する冷気を肩に感じながら、気を取り直して諸葛亮に問いかけた。
「諸葛どの、劉玄徳どのと劉江夏どのの軍勢は今どちらに?」
「夏口から樊口に退いております、曹孟徳に江陵を取られてしまいましたので。向こうに陸戦を挑まれたら壊滅は必至ですからね」
然り、孫権は首肯した。そして少し前のめりになって、改めて口を開く。
「曹公の軍勢の状況はわかりますか?」
大仰に諸葛亮は頷き、こほん、とひとつ咳払いをした。
曹操軍の先鋒は曹純、文聘である。曹純は騎兵の内でも精鋭を率いる勇将、そして文聘はもともと劉表に仕えていたこともあって荊州の地勢に詳しく、また劉琮の陣営から降伏した将兵のほとんどは彼の存在のために曹操に臣従していると言ってよく、必ずしも曹操に心服しているというわけではなかった。その証左として元劉表麾下の将兵のほとんどは当初は劉備に付き従って南進したのであり、曹操の下にいるのはただ軽騎兵による苛烈な攻勢に屈することを甘受してしまったからに過ぎないのである。
また、先達てまで荊州の情勢に備えるために荊州方面の諸都市に駐屯させていた彼の麾下の将の多くを前進させたという。頴川郡長社県の張遼、字を文遠、同郡頴陰県の于禁、字を文則、そして同郡陽翟県の楽進、字を文謙の他、張郃、字を儁乂、朱霊、字を文博、李典、字を曼成、路招、字を文嘉、そして馮楷、字を伯正の七軍が、章陵太守であり都督護軍を務める趙儼、字を伯然――彼は元々曹操が司空であった頃その掾属の主簿を務めており、特別愛された士人であるという――の指揮の下で動いており、うち楽進は襄陽に入り、また別軍として徐晃、字を公明、そして満寵、字を伯寧の二軍が樊城に留まっているという。さらに先刻伝令があって、曹操は攻め落とした江陵に曹仁を駐屯させたとの連絡が入ったということであった。
「よほど其の方のご主君を殺したいと見える」
腕を組んだままの程普がそう言うと諸葛亮は肩を竦め、全くその通りです、と呆れたような声で答えた。
「曹孟徳の起こした大軍勢は地の利に守られて堅守を誇る劉表征討のためであり、彼の風下に立つことを良しとしない我が主公を誅滅するためのものでありました。しかし劉表が死に、その後継はさっさと恭順してしまった。恐らく彼は、皆様方江東の将兵たちも何ら抵抗なく帰順してくるものとたかを括っていたことでしょう」
ですが、と諸葛亮は悠然と群臣たちを見回し、最後に孫権をまっすぐ見てさっと手のひらを差し伸べた。
「孫会稽様、あなた様はこのように皆様のお心をすっかりひとつにしてしまわれた。これは曹孟徳にとって大誤算であり、青天の霹靂です。世の趨勢は決してけだものの味方はしないのです」
彼の浮かべる自信に満ちた表情に、孫権はむずがゆそうに両方の口の端を上げ、努々安堵めされますな、と固い声で言った。
「我々の側もあまり兵数を割くことができるわけではございません。土着の不服従民たちの動きに備えるため、呉会、そして丹楊の軍勢を動かすことは叶いませぬ。こたびは程徳謀公、そして周公瑾どのに左右の督を任せ、豫章、鄱陽、それから先の黄祖征伐の際に呉郡より動かした軍勢を率いていただくことになっております」
「……ちなみに、いかほどの」
「今のところは三万を」
三万、と諸葛亮は呟く。あまりにも少なすぎる手勢である。それに劉備・劉琦の率いる一万余、関羽の率いていた水軍を合わせたとしても四万程度の兵数であり、曹操の率いる十数万の兵に対抗するには心許ない。加えて諸葛亮は、この戦いに於いてひとつの企みを持っていた。
ふと彼が黙った隙に、周瑜が口を開く。
「おや、頼りないな、とでも思ったか?」
「…………いいえ、まさか」
顔を上げた彼に、周瑜は無表情に言う。
「安心したまえ。こたびの戦、孫軍の指揮を取るのは私とこちらにいらっしゃる程公だ。彼は大殿の時代より軍勢を支えてきたいずれ劣らぬ猛将である。君のような若輩者には、用兵に於いても実戦経験に於いても及びもつかぬ」
「……それはそれは、大層なことで」
それのどこが、安心したまえ、に繋がるのか諸葛亮にはわからない。彼の目には、周瑜が彼自身の主張を必死に包み隠して余所行きの――或いは孫権に向けての――言葉を発しているようにしか見えなかった。
そのことを知ってか知らずか、周瑜の言を聞いた孫権はまたしても苦笑する。
「ふふ、諸葛どのが若輩者なら、私などどれほどのものでしょうね」
「殿、以前も申し上げましたが、あなた様のそのような謙遜はしばしば的を得ておりませんよ」
うぐ、と言葉に詰まる孫権の斜め後ろで谷利が小さく笑う。孫権に睨まれ、彼は慌ててすまし顔を作って姿勢を正した。
孫権もまた背筋を伸ばすと諸葛亮に向き直る。
「支度が整い次第、軍を出陣させます。劉玄徳、劉江夏ご両名にそのようにお伝えください」
「あなた様も出られるのですか?」
諸葛亮の問い掛けに孫権はゆっくり首を振る。
「私はこちらの戦況が落ち着くのを確認したら、張公と共に一旦呉に戻ります。――山越のみならず、揚州北部の動向からも目を離すことはできません」
揚州北部の曲阿、丹徒の二県には孫河の甥である孫韶、字を公礼の率いる軍勢が駐屯しており、北方の動静を常に注視している。また丹楊郡には孫瑜の軍勢があったが、その後背、前線に対する助勢となるべき呉郡、会稽郡の軍勢は山岳地帯の山越との衝突に常に備えなければならないため、有事の際の恃みとするには些か不安があった。
荊州を行軍する巨大な軍勢のその裏で、曹操が手薄になる東部方面に対して何の備えもしていないとは想定し難く、或いは連動して攻勢をかけてくる恐れすらある。荊州戦線に於ける勝利が確実なものとなり次第、孫権と彼の麾下数千の兵士たちは取って返して合肥城を攻撃する積もりだった。最初、合肥攻撃について相談を持ち掛けられた周瑜は難色を示したが、孫権がどうも意固地な様子なのに折れ、丹楊の孫瑜と協同して行軍することを条件に転進を了承した。
諸葛亮は目を細める。
「勝てる、と、お思いなのですね」
「勝つと確信しているだけのこと。我々の軍勢は精強ですから」
覚えず面に笑みを浮かべる己に対し、そうですか、とどこか気の抜けたように応える彼に孫権は首をかしげる。
「ご主君が曹孟徳に負けると?」
「まさか。我が主公が曹孟徳に降るとき、もはや彼の首はないのです。どうして彼を愛する私や臣下の皆がその敗北を看過しましょうか」
「……それは羨ましい話だ」
ぽつり、俯き加減になった孫権はささやくような声でこぼす。彼はすぐに顔を上げ、二の句を継いだ。
「劉玄徳どのは、なぜどうしても曹孟徳には屈しないのでしょうか」
そう尋ねられた諸葛亮は、きょとんと目を丸くする。
「…………それって」
しばらく黙って考え込んでいたようであったが、やがて彼はおもむろに口を開いた。
「あなた様が私に問うて、そうして私があなた様に応えるような、そういう質問ではないですよね」
へ、と間の抜けたような声を上げる孫権に、諸葛亮は小首をかしげる。
「私の如き分際で、我が主公のご深慮を量り、あまつさえ口にすることなどできませぬ。今は忙しないなかですからそうもいかないでしょうが、戦後成り行きが落ち着きましたらば、ぜひ我が主公に直接お尋ねになってください」
それは恐らく、そういう領域の話です。諸葛亮はそう言った。孫権は彼の顔を見て頬を赤らめ、わかりました、と頷いて口の端を指で掻く。いかにも恥ずかしそうな所作である。
その様子を見た諸葛亮はおかしそうに笑った。
「さあ、でも、田横ですら高祖に屈するを良しとしなかったのに、ましてや劉豫州がどうして曹孟徳に屈するものかと、私としてはそう思います。或いは両雄倶に立たずとは、正にこういうことなのかも知れませぬ。先ほどは曹孟徳の悪行を看過せぬと申しましたが、それでもなお我が主公が曹孟徳に敗れるというのであれば、それはもはや天命なのでありましょう。私もまたそれに殉ずることを厭いませぬ」
私は実に良い主君に巡り会いました、と胸を張って諸葛亮は言う。
その表情、どこか朴訥とした彼の佇まいにも晴れやかなものを感じて、孫権は息が詰まりそうな心地がした。
◇
三万の軍勢は確かに心許なかった。前夜、人目を憚って内密に孫権に目通りした周瑜はそれとなく己の要望する兵数を伝えたが、それに対する孫権の返答は芳しいものではなかった。無理からぬことではあったが、一瞬曇った周瑜の表情を孫権は見逃さなかったのだろう、彼はそっと周瑜の傍に寄ると、本当に申し訳ありません、と眉根を寄せて言った。
『すぐに動かせるのはどうしてもこれだけです。私も戦況が決するまではここに残り動員を続け、物資や兵糧の輸送に当たりますゆえ、どうかご辛抱ください』
ただ、もし。
『何か問題があって、曹公とこれ以上戦を続けられないような状況になったら、そのときは必ずすぐに帰還してください。私が彼と決着をつけます』
――彼はなんと恐ろしいことを言うものだろう。周瑜はその言葉を聞いたとき、全身の血が凍えたような心地がした。
彼の亡兄、孫策のお墨付きである“戦下手”の彼が、ただ己の立場、矜持だけを持って、軍才豊かな曹操、そしてその麾下にいる歴戦の猛将たちと決着をつけようなどと言う。それは周瑜が先んじて述べたこの戦いにおけるあらゆる優位性をすべて否定し兼ねない事態に発展する恐れがあった。彼の責任感の強さには恐れ入るが、周瑜には決して採りえない選択肢である。まさかそれを彼が見越していたわけでもあるまいが――孫権は結局のところ軽率だったし、彼の後ろに控えている谷利は信じられないような表情で主君を見つめていた――孫権に丸投げしてしまうことの恐怖を考えれば、その他の“問題”はすべて取るに足らぬことにさえ思えた。
周公瑾を左都督とし、程徳謀を右都督とする。この采配に眉を顰めたのは両名ばかりでなく、今回の戦線に集まったほとんどの将もまた同様であった。
兼ねてから程普と周瑜との関係は思わしくなく、少なくとも孫権もその事実については承知していた。多くの将兵は二人の関係の原因が程普の傲慢にあるものだと認識していたが、それに異を唱えることもなく周瑜はひたすら彼に対し真摯に振る舞うように努めていた。数年前は一瞥すらくれなかった彼があるとき、話しかける己を振り返り目を細めて、そうか、とぽつりと返した一言に、たまらなく嬉しくなるほどには周瑜だって思うところがないわけではなかったのだ。
『江東は、孫破虜様が生まれ、孫討逆様が拓いた故国。そして皆様は父と兄とに愛され慕われた素晴らしき勇将にございます。私は皆様方の勇武、気魄を間近で拝見することができて、本当に幸せ者です』
誇らしげな表情、よく通る澄んだ声は、きっと誰の心にも染み渡ったのだろう。
出陣の直前、程普は周瑜の傍へ歩み寄り、その肩を拳で軽く小突いた。
『信じている』
『――ええ、骨身に刻みます』
そのまま振り返らずに自身の乗る船へと向かう彼の背中をじっと見つめる己の後ろで、様子を窺っていた諸将が安堵したような空気を醸し出すのを周瑜は感じ取り、覚えず口許に笑みを浮かべた。
全く孫権は、その手法が良かれ悪しかれ、人を本気にさせるのがとにかく上手い。
「周将軍! 劉豫州様からの使者がいらっしゃっております」
船団が樊口を過ぎた頃、川の風に吹かれながら周瑜がふと嘆息したとき、背後の兵から声がかかった。周瑜が振り返ると、一人の兵士が拱手して己の言葉をじっと待っている。
「劉豫州の使者と言ったか?」
「はい、会見を持ちたいと」
「それなら程公に……いや、そうだな」
すぐに周瑜は思い直し、兵の呼ぶ方へと歩み寄る。劉軍からの使者が周瑜の顔色を伺うような素振りで佇んでいるのに微笑み返し、周瑜はまず一言、ご足労ありがとう、と慇懃に言った。
「しかし、私にはただいま軍の任務があるから持ち場を離れるわけにはゆかぬ。これは我が軍の諸将も同様だ。もしどうしても会見を持ちたいと劉豫州どのが仰られるのであれば、そちらの方から出向いていただけないだろうか。ああ、もし来るのであれば必ず私のところにしてくれ。戦の前に諸将を煩わせたくはないのでね」
まくし立てる己にぽかんとする、彼を呼んだ兵士をチラとも見ないで、周瑜は言うべきことは言ったとばかりに使者の前を辞去する。
様子を見ていた副将が、よろしいのですか、と問うが、周瑜は肩を竦めるだけに留めてさっさとその場を後にしてしまった。
数刻後、劉備は存外素直に周瑜の下へと足を運んできた。にこにこと笑って、いやすまない、と頭を掻く彼に周瑜は面食らう。
「孟徳がいつ来るかいつ来るかとそわそわしてしまってなあ。お前さんがたの船影が見えて嬉しくなって。無礼なことをした」
許してくれ、と人好きのする笑みを浮かべる劉備に己も笑みを返して会釈しながらも、しかし周瑜は内心では笑っていない。
「劉豫州どのにはご苦労なことです。わざわざおいでくださいましてありがとうございます」
「構わないさ。しかし立派な船団だねえ。雲長が率いていたのとは比べものにならない」
「ああ、先の衝突で別働隊だった」
そう、と劉備は嬉しそうに頷く。
「孫軍は、この陣容は、大体どのくらいの人数がいるんだい?」
「三万です」
即答した周瑜の顔を、急に真顔になって黙り込んだ劉備がじっと見つめる。その様子を訝るように半眼になる周瑜に、劉備は恐る恐る問うた。
「俺は、その……水戦には明るくないんだが、三万というのは十全な数字なのか?」
「ええ、我々はこれで十分」
はあ、と呆けたように嘆息し仰け反った彼は、すごいな、と気の抜けた声で言う。
「俺にはどうにも……少なすぎるように思えて。頭が固すぎるな」
「それならばそれで結構。劉豫州どのは我々が曹孟徳を追い散らすのを黙ってご覧になっていてください」
劉備はいよいよ目を見開いて周瑜を見た。泰然とした彼の様子にどぎまぎする劉備は、ええと、と取り繕うような声を発する。
「ああ、そうだ、魯子敬。あいつは? あいつはどこにいるかな。よければ彼とも話がしたいんだが」
「魯子敬どのは賛軍校尉として別の船に乗られておりますが、彼もまた軍務の最中ですので、諸将同様勝手に持ち場を離れさせるわけにはまいりません。どうしてもというなら別の機会にお願いいたします」
ついに劉備は閉口してしまった。その様子を目を細めて見つめながら、やがて周瑜は、ああそうだ、とまるで今思い出したようにわざとらしく声を上げた。
「諸葛孔明どのも一緒に出発しておりますので、二、三日のうちにそちらに戻りましょう」
「そうかい、そりゃあよかった……」
まさに取り付く島もない、といったふうである。結局劉備はそのまま、お互い奮励努力しよう、と言い置いてさっさと周瑜の船を後にしてしまった。
下船して去って行くその後姿に冷ややかな目線を向けながら、周瑜は口の中で、お互いか、と呟く。
「……よく言ったものだな」
その声は低く、初冬の河畔に似合いの乾いた響きを湛えていた。
◇
建安十三年、冬十月、癸未の朔日、人々は空を見上げていた。昏くのっぺりとしたその中に太陽はなく、ただ黒い円だけが浮かんでいる。
日食である。
谷利は柴桑の宮殿からその有り様を見つめ、覚えず武者震いした。
「あまり日を見過ぎるな、目が潰れるぞ」
さっさと屋内に引き返し、その場に集まった張昭らの文官や天文官らと何事か議論を交わしていた孫権が谷利を呼ぶ。慌てて主の傍に戻った谷利だが、彼らがやけに焦燥している様子なのに首をかしげた。
「この食が前線に出ている皆の気を煩わせなければよいのだが」
「殿。これは以前からある程度予測できておったではありませぬか。諸将にもその旨はお伝えしております」
「うむ……だが、董仲舒やこの京房の言うように、変事が起こらないとも限らないだろう」
孫権の不安げな物言いに、谷利は彼らにとって食が“不吉なもの”と認識されていることを知る。谷利の面食らったような表情に苦笑した孫権は彼に向き直ると、その手にしていた書物の一文を示した。
「不御、生叛、不明、不安、亡、誣君、不知、不承、乱、逆、背、因――すべて、食を引き起こすものだ。その後に大地が震動することすらある。今、天下はもはや漢王室を食い散らかす曹孟徳の掌中に収められようとしている。一体これは、書物の上ではなんと呼び表されるのだろう?」
群臣を散会させた後、張昭や秦松らだけが残る政堂で、孫権は居ても立っても居られない様子で頬杖を突いては胡坐を掻く足を組み直してみたり、伸びをしてみたりしている。谷利はしばらくそれを黙って見つめていたが、やがて誰一人言葉を発する様子ではないのを感じ取ると、我が君、とささやくような声で孫権に声をかけた。
「少しよろしいでしょうか」
「うむ、どうした?」
孫権の素早い返答に、彼もまた会話の糸口を探していたのだろうと察せられて谷利はおかしくなった。笑い交じりの谷利の声に、孫権は不思議そうに首をかしげる。
「我々の屯では、日が隠れることは吉兆です」
「ほう? それはどういったことだろうか」
「我々の父祖が、全身の体毛が真黒の虎を見たそうです。かつて飢餓で大変だったときに食糧を求めて南へ遠出した際のことだそうですので、丹楊の周辺ではないのですが」
体ごと谷利に向き直った孫権が、期待に満ちた表情で続きを促す。谷利はひとつ頷いた。
「高い崖の上に凛として立つその雄々しい姿の上にちょうど日がかかったとき、その黒虎は大きく口を開いて日を一飲みしました」
「なんと」
「ええ、そうして周囲が暗闇に包まれ、ただ黒虎の両眼だけが爛々と輝き、父祖がいよいよ絶望したとき――黒虎は大きく吠え、宙に飛び上がると丸くなって空に昇り、次第にその体毛を真っ白に変えて、ついに新しい日になりました」
ほう、と孫権が感心したような声を上げる。それで先祖はどうなったのだ、と問いかける彼に、谷利は続ける。
「そうして明るくなった視界に父祖が見たものは、辺り一面の草原とその中に遊ぶ多種多様の動物たち、その向こうに広がる大きな川、そして川べりに実のなる木が林立する様だったそうです。父祖はそこで皆の分の食糧を得て屯に戻り、屯は飢餓から救われたということです」
谷利が話し終えると、はあ、と感慨深げにため息をついた孫権は右手に作った拳で己の口許をそっと隠すようにした。
「……なるほど、そういうこともあるのか」
そう言うとやおら孫権は立ち上がり、政堂の窓の方へと歩いていく。谷利もその後に続けば、先ほどまで黒い影に隠されていた太陽が少しずつ明けだし、柴桑邑に日が差し始めるのが見えた。
「いいな、それは」
谷利を振り返る孫権の精悍な頬をも、きらきらと日の光が照らし始める。
「今日、今このとき、新たな日が生まれるのだ」
穏やかな笑みを浮かべるその面を見つめ返しながら、谷利もまた頷いた。
そのとき、政堂の扉の向こうから声がかかり、前線からの書簡が到着した旨を告げる。孫権が入室を許可すると、一人の兵士が素早い動作で評定の間に入って来、その手に持っていた書簡をさっと差し出した。
そこには孫軍の船団が陸口への布陣を完了した旨がしたためられている。一読した孫権はその書簡を張昭に回すと、伝令の兵士に対し労いの言葉をかけて退室させた。
「開戦、ですな」
「うむ」
遠くを見つめるようなまなざしの孫権は、口許をほんのわずかほころばせて、開戦だ、と言った。
◇
辺り一帯に充満する冬の空気が、常にない暖かさを帯びている。しかし南西から吹く風は鋭く、ともすれば耳がちぎれてしまいそうなほどだ。
曹操の船団は江陵から江水に乗り、一旦洞庭湖まで南下してから夏口まで北上してくる航路を取るようだ、と用間の兵が言う。周瑜は厳しい表情でひとつ頷き、彼を下がらせた。
柴桑と江陵とは互いに陸口からの距離は同程度であり、孫軍がこの地点に先んじて到達できたのは幸運である。しかし孫軍の船団が陸口に布陣したことで、曹軍が陸上から柴桑、そして江東に侵攻する方策は採り得なくなった。
二年前の保屯、麻屯の戦役でこの地一帯の不服従民たちをひとまず慰撫していたことも幸いし、周辺各地の屯から少なからぬ人数が兵士として参加することを望んで馳せ参じ、また軍需品を提供してくれる屯もあれば、柴桑からの兵站に加わってくれる者たちも現れた。このことは少なからず孫軍全体の士気向上につながった。協力者がいることの心強さは、すなわち勇気になり得る。
「俺たちも川の民ですから、操船なら任せてくださいよ」
得意げになって周瑜に言うのは、かつて麻屯で谷利と共に行動していた盧遠である。北からの侵略者たちに苦しめられた彼らは、再び北方の兵士たちが南下してくるという報を聞いて矢も楯もたまらず兵を募り、また周辺の屯に率先して協力を呼び掛けていたという。
「こたびの戦には、谷どのや孫将軍はいらっしゃらないんですね」
「ああ。谷利は柴桑で殿のお傍についているし、仲異どのは丹楊で北東部からの脅威に備えている。皆、己のすべきことをしているよ」
そうですか、と盧遠の声は嬉しそうに弾む。周瑜もまた微笑み、再び目を凝らして川の向こうを睨んだ。
聴覚を研ぎ澄ませば、南西から風に乗って船が川面に波を蹴立てている音が聞こえてくるようだ。
誰もが口を噤み、じっとして微動だにしない。
やがて、江水のふちに黒い線が浮かび上がった。
「曹軍!!!」
一人が叫んだ。
鼓吹が一斉に太鼓を打ち鳴らし、孫軍の船がにわかに動き出した。
「左右に展開しろ! 曹軍に江水を抜けさせるな!」
「右翼、既に程将軍、周将軍の船団が封鎖しております!」
「程公、幼平……!」
周瑜は覚えず口許に笑みを浮かべ、ぐっと力強く拳を握った。孫軍の将兵、すべての息が揃い、この苦難に立ち向かっている。
曹軍の船団の先鋒は、孫軍の形成する囲み込むような陣容に突出して飛び込む形になった。ぎこちない動きで攻撃を避けようとする蒙衝を、数隻ごとを一団として組んだ孫軍の闘艦が包囲し、三方から矢を射掛けていく。後方から来る援軍が間に合わぬうちに、一隻が沈んだ。オオ、と鬨の声を上げた闘艦の兵士たちはしかし、すぐさま次の蒙衝へと襲い掛かる。
「右翼は心配しないでください、すぐに麻屯から出た舸船が来ますから!」
「頼もしい限りだ!」
盧遠の言に返事しながら、周瑜は右手に携えていた剣を掲げさせる。その刃に閃く光を合図に、周瑜の乗る蒙衝の後方から三隻の闘艦が勢いよく漕ぎ出た。甘寧、韓当、そして黄蓋の操る船である。ほとんど同時に、陣の中央を固める呂範の部隊からは呂蒙と凌統の船が動き出した。
周瑜の剣が、堂々前方を指し示した。
「さあ、行こう!!!」
◇
――陸口での緒戦に敗れた曹軍は、その対岸、赤壁へと船団を寄せて孫軍と対峙した。曹軍先鋒の闘艦の多くを撃破したとはいえ、未だその数は孫軍のそれを上回っている。
しかし捕虜にした曹軍の兵士の様子を見ると、曹軍の兵士の中には既に疫病に罹患してしまっている者も少なからずあった。曹軍は操船の拙さに加え、この上動かせる兵数もそう多くはないらしい。
だが、その隙を突いて攻勢をかけるには、赤壁に陣を敷く敵の大船団はひとところに固まり過ぎていた。緒戦の勝利は各個撃破に拠るところが大きく、既に陣形を整えられてしまった今では釣り出して叩く作戦も採り得ない。突撃をかけることもできるだろうが、それでは味方の損害も増えるばかりだ。周瑜は、無暗に兵の命を失わせるわけにはいかなかった。
対岸を睨みつける眼差し、南西風が揺らすその髪を、盧遠が不安そうに見つめる。
周瑜の理想の最上とはここで曹操を討ち取ることであったが、そうでなくとも彼の率いてきた船団を完膚なきまでに叩きのめすことにあった。疫病による軍の弱体化を押してまで強行した南征があえなく失敗に終われば、以降の荊州、そして江東は容易く曹操が手出しできるような土地ではなくなる。
北の道理が、南に通じることはあり得ないのである。
対岸に集まる船影を黒く染めながら、その向こうに日が傾きかける。
「おうい、公瑾。こーきーん」
不意に周瑜を呼ばわる者があって、弾かれたように振り返ると、忙しなく働く兵士たちの隙間を縫って誰あろう黄蓋が大股で駆け寄ってくるのが見えた。
「黄将軍!? いかがされましたか?」
「いやなに、ちょっとね、相談があるんだよ」
相談、と首をかしげる周瑜に、黄蓋はその凛々しい佇まいに似つかわしくなく、大きな口に人懐っこい笑みを乗せて、いたずらっぽく彼の人差し指を口許に持っていく。
「俺はね、南の田舎ではあるけど荊州の出身なもんでね、この辺りにはちょっと詳しいんだ。大殿の下に馳せ参じてからはしばらく離れていたが、故郷に吹く風は今も変わってなかった」
「はあ……」
「大殿、討逆様、そして討虜様に仕えて、もう二十数年になるが……まだやったことのないことを、やってみたくて」
目を細める彼は、周瑜の肩の向こう、敵船団の影をじっと見つめる。周瑜もまたその視線を追って己の後背を振り返った。
「降伏、してみようかと思うんだが」
「え?」
後頭部にぶつかった声に、周瑜は思わず彼らしくなく素っ頓狂な声を上げて身を翻した。黄蓋は相変わらずにこにこと笑って、懐に忍ばせていた書簡をすい、と周瑜に差し出す。
「俺じゃ判断がつかんから、一度これを読んで添削してくれないか」
“お前さんならわかるだろう?”
黄蓋はそう言って、戸惑う周瑜の両手に書簡を握らせ、それを己の両手で包み込むようにした。
人知れず、川に吹く風の向きが変わった。
それはまるで彼らの背を優しく強く押すように、東南の方角から渡ってきた風であった。