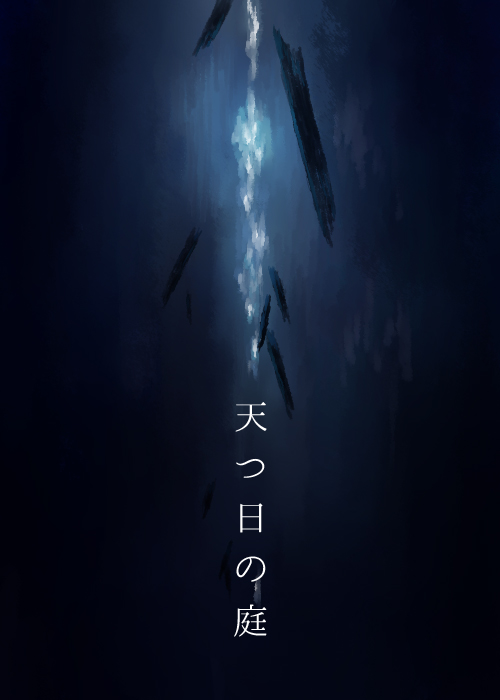――暴風は明け方には収まり、昨晩の惨劇のことなど素知らぬ顔で冴えた冬の太陽が昇った。
孫権は傅嬰に近衛兵七百人を率いさせて被害の状況と行方不明者の捜索に当たらせ、また下流の京城に駐屯する孫韶に伝令を出して河口に流れ着いた兵士や船の残骸の回収を任せると、自身は孫瑜を伴い軍陣の各所を回り将兵たちの慰撫に努めた。
昨年暮れの凶兆から戦争、そして今回の災害に、皆浮き足立ち、あるいは竦然としている。
「……董将軍のお姿はまだ見えぬか」
こそりと耳許で尋ねる孫瑜に、孫権は重く頷く。そうか、と残念そうに孫瑜が息をついたとき、西方の陣から鼓吹が軍楽を鳴らすのが聞こえた。
顔を見合わせ孫権と孫瑜の一行がそちらへ走って向かうと、晴天の下、江を悠然と渡ってくる船団がある。昨晩、風波に攫われて西部に流され暗闇に溶けていった船たちだった。
船体の側面には矢が刺さっており、流されていった先で戦闘が発生したのであろうことは想像できた。
船の上部にはためく“徐”の旗を見上げながら孫権は、文嚮どの、と呟く。
聞こえもしないはずなのに、ちょうどそのとき船の縁から身を乗り出した徐盛が遠く川岸に立つ孫権と孫瑜の姿を見とめ、遠目にもわかる満面の笑みで大きく手を振った。
「我が君いーっ、奮威将軍んーっ」
その大声に名を呼ばれた二人はぽかんと口を開ける。彼らの後ろで衛奕がかすかに笑い出してから、ようやく二人は表情を緩めた。
夜半、流された徐盛の船団は運悪く曹軍の陣営のただなかに漂着したが、悪天候は曹軍にも猛威を奮い敵も混乱のなかにあったという。そこで徐盛は手勢を率い岸に上陸すると、敵に攻撃を仕掛けて多数を屠った。次第に天候が回復してきたため撤退しこうして戻ってきた次第だという。
その報告を聞いた孫権は開いた口がふさがらず、孫瑜は頬を引きつらせるばかりであった。
「ご覧の通り、多少の矢傷は負いましたがあなた様の船も将兵も皆無事です! 不手際で船を流されてしまった咎はどうぞ俺一人に負わせていただけませぬか」
「いや、そんなことがどうして罪になりましょう。私はあなたを称賛すれど、罪を問うつもりは毛頭ありませんよ。それに……」
言い淀む孫権に首をかしげた徐盛が先を促すような目線を向ける。嘆息した孫権は、元代どのが行方不明なのです、と小さな声で言った。
「董将軍が……!」
「彼の軍勢を捜索させておりますが未だ報告はありません。……文嚮どの、兵たち共々よくぞご無事で戻ってくださいました」
沈痛な面持ちでそっと手を取られ、思わず徐盛は、うう、と唸る。
――どうして己が彼といるときはいつもこんななのだ。孫策も、周瑜も、董襲も、いつも誰かを喪い悲嘆にくれる顔ばかり孫権は己に見せる。
徐盛は孫権の手を握り返し、我が君、と大きな声で叫んだ。
「俺は! ずっとあなた様の下におりますから! 悲しまないでください、今にあなた様の安息の国を勝ち取ってみせます!」
「えっ?」
そうして膝を伸ばして立ち上がった徐盛は相変わらずぽかんとしている孫権を一度だけ顧みると、では失礼、と威勢良く自陣に走り去ってしまった。
「……彼は、嵐みたいな男だなあ。前に蕪湖でまみえたときはもうちょっと大人しかったと思うんだが」
呆れたような声音の孫瑜の言葉に孫権は微笑みながら、そうでしょうか、と相槌を打つ。
「もともと武勇で知られた人でしたから。私が彼を招聘しようと思ったのもそれが理由ですし……」
「ああ、そうだったね。頼もしい限りだ」
そうして孫瑜は、兵の慰撫に当たるために河岸の陣へ戻った。彼の背を見届けた後、ふと考え込むような面持ちになった孫権を見、谷利は内心で首をかしげる。しばらく後、孫権はぱっと顔を上げると親近監らを見回した。
「思いついたことがある」
「それは、奮威様のご機嫌を損ねるようなことでしょうか」
間髪を入れず谷利が問うと孫権はニヤリと笑って、さすが察しがいいな、と口にした。そうして彼は三人を手招き、こそこそと密談を始める。次第に渋面になる彼らを、孫権自身は表情をほころばせて見つめているだけだ。それだけで三人は孫権が、彼らがどれほど口答えをしても聞き入れるつもりが毛頭ないであろうと理解することができた。
「……そんなの危ないですよ。嫌ですって言えたらいいのに」
「…………」
衛奕の言葉に孫権は哄笑すると彼の肩を抱き、頼まれてくれるか、とささやく。口を尖らせた衛奕は、しかし小さく頷いた。
「谷利どの、我が君のことよろしくお願いします」
神妙な顔をして言う左異に谷利が頷けば、その横でようやく孫権が、そんなに私は覚束ないか、と眉根を寄せた。
◇
天候が安定した正月下旬、曹操は長江南岸に孫権の敷いた陣を具に眺め、そのなかでも比較的防備が手薄と思われる西岸の右翼を攻撃し都督・公孫陽の軍勢を打ち破り彼を捕虜とした。次いで夜陰に紛れ濡須の中州に張遼、臧覇の軍勢を渡らせたが、孫軍の水軍がこれを取り囲み、撤退の報を受けて引き返す軍を追撃し、三千もの兵を捕らえた。この痛手を受けて曹操はいよいよ守戦に切り替えたが、そこへ孫権は自ら船に乗ると濡須水に漕ぎ出で曹軍の軍中へ突入した。
「なんだ、あの船は」
愚昧とも取れる行動、単騎濡須水を走る孫軍の一艘の船を河岸の陣から見ながら、ぽつりと楽進、字を文謙が呟いた。その横で忌々しそうに眉根を寄せた李典、字を曼成が、我々をばかにしているのか、と舌打ちをする。そこへ異状の報告を受けて本陣から出てきた曹操が、彼の近衛である許褚、字を仲康、そして中領軍の薛悌、字を孝威を伴って彼らの傍に並んだ。彼は一目船を見るとたちまち哄笑した。
「おかしなことをするものだ。あれは孫仲謀本人かな、ご丁寧に牙門旗まで携えて。我が軍が攻撃を仕掛けないのにしびれを切らして出てきたに違いない。でなくば我が陣営の遊覧といったところか」
そう言って李典の肩を軽く叩き、お前と同じくらいの歳の青年だよ、と曹操が微笑みかけると、李典は至極迷惑そうな表情をした。
「あんな猪武者にはなりたくないものです。ましてや本当にあれが孫仲謀の乗る船なら、彼は私の記憶が定かなら一軍を統べる大将のはず。あのような軽挙妄動、諌められるまでもなく自重するのが当たり前でしょう」
「そうだな。昔一度会ったときは、あんなばかげたことをするような男には見えなかったが……」
曹操は全軍に弓と弩を用意させ、船を攻撃するよう指示を出した。
「孫討虜が死んでも、周公瑾が死んでもまだ江東には“朝敵”がいる。さて、あの男を殺したらどうなるものか、見てみよう」
矢が一斉に船へ向けて放たれる。無数の矢が曹軍の陣を向いている左舷に突き刺さり、船の均衡が崩れ僅かに傾いだ。おや、と面白そうに目を瞬かせた曹操の視界で、船は傾きながら方向を変え、右舷を曹軍側に向ける。曹軍の放つ矢は船の右舷にも次々突き立てられ、こともあろうに均衡が取れた船は体中から矢を生やしながら悠然と濡須水を下っていった。
「…………しまった」
曹操は気の抜けたような声を発し、大笑いして隣の李典の肩を何度も叩いた。
「仲謀めに我が軍の矢を与えてしまった!」
「……勘弁してくださいよ、丞相……」
かの船が帰陣するや、ほとんど間を置かず孫軍内で太鼓や鉦鼓、そして楽が打ち鳴らされた。ほう、と嘆息する曹操は何度も頷き、いい男になったな、と口にする。
「浅慮は否めないが反骨心は兄譲りか。付け入る隙があるとするならばそこだが、……今ではなかろうな」
「……撤退なさるので?」
薛悌の問いに、曹操は頷く。
「将は一人捕縛した。三千の兵の代わりは到底務まらんが、これ以上犠牲も増やせまい。またぞろ増水もするのだろうし……ああ、お前、私の幕舎に文遠を呼んでくれ」
曹操は自身の幕舎に足を向けながら、通りがかりの兵の一人に声をかける。そうして己の後背にいる楽進と李典を振り返った。
「文謙、曼成、お前たちも来なさい。薛中領軍、そなたには駐留軍の護軍として共に合肥に入ってほしい。劉元頴どのが遺した軍備があるから、防衛には事欠くまい」
「は、承知いたしました」
「……あいつも一緒か」
李典が呟いたのを耳ざとく聞きつけた楽進が、陣中で殺し合うのだけはやめてくれよ、と鼻を鳴らして茶化すように言う。李典はその言葉には答えず、彼を横目で睨みつけるに留めた。
彼らのやり取りを後背に伺いながら、薛悌は小さな声で曹操に言った。
「……彼らで大丈夫なのでしょうか」
せめて臧揚威将軍が、と口ごもる薛悌に、曹操は微笑んでその肩を撫ぜてやる。
「彼らが信じられなくても、私を信じてくれ。大丈夫、私の見込んだ素晴らしい将たちは、国事に於いて私情を優先するような愚か者ではないから」
「いえ、そのような……ええ、わかっております。愚盲をどうかお許しください」
「いいや、気持ちはわかるよ。だが、彼らはそなたの目の前で最も優れた将になる。それだけは確かなことだ」
曹操の自信に満ちた言を受け、薛悌はようやく口許に笑みを浮かべて頷く。その様子に曹操も満足げに笑い返して、大股で自身の幕舎に戻って行った。
◇
建安十八年夏六月、中原に魏国が建てられ、曹操は当地を治める魏公となった。献帝の詔勅を当初は断ったものの、文武百官らの上表を受けての就任であった。国土として曹操に与えられた諸郡は十もあり、中原に於ける彼の権勢はますます盛んとなった。
荊州地方では、かねてからの魯粛の予測通り劉備が動いた。
益州の北に位置する漢中――この頃は漢寧と呼ばれた――に独立勢力を保っている宗教集団の長・張魯は、益州の主である劉璋との間に深い遺恨があった。のみならず張魯は漢寧に於いて宗民を愛し善政を敷いたため、彼に従う民衆は意気軒昂、張魯征伐のためにたびたび侵攻してくる劉璋の軍勢をよく防いだ。このことを利用し、劉璋を廃するを企む別駕従事・張松、字を子喬を始めとする劉璋臣下の一部が益州への劉備招聘を彼らの主人に提案したのである。“張魯征伐のための援軍”の名目であった。
劉備を益州に迎えることについては他の家臣たちによる少なからぬ反対があったが、劉璋は結局真意を疑わず張松らの意見を容れ、荊州は公安に拠点を構える劉備の下へ張松、そして法正、字を孝直の二名を派遣した。果然法正もまた張松の一味であった――そして法正が中でも遥かに秀でていることは、後に劉備も知るところとなる。
建安十六年の暮れ、劉備の下に来た二名は、劉璋に替わり益州の主として当地を統べるよう劉備に乞うた。劉備の側も彼らを歓待し、二名は手ずから携えた地図を用い益州の地理や劉璋の軍勢の陣容、軍備、各将らの性質に至るまで劉備に詳細に伝えた。そこには、劉備の下に参じ諸葛亮と共に軍師中郎将に任じられた龐統の姿もあった。
だが、劉備は初め渋った。劉璋が彼と同姓であり、彼から国を奪うことは道義にもとるというのがその理由である。
何をばかなことを、と龐統は劉備を断じた。
「民心は劉璋から乖離し、臣下らは斯様にてんでばらばら己自身の思惑で動いております。もはや益州に国はありません。統治者もありません。いるのは愚かな一人の男」
龐統の声は柔らかな響きで、冷たいことを言う。
「同じ劉ならいっそ好都合、民衆には彼らの領主よりも己の明日の生業こそが肝要なのです。あなた様の言う道義など彼らが如何ほど気に掛けましょう。それよりも新たな領主にもたらされる安寧のほうが、彼らにはよほど心配事なのですよ」
身を乗り出して訴える龐統に劉備が思わず上体を引くと、その様子を傍らで見ていた諸葛亮がおかしそうに笑った。
「ふふふっ、さすがは士元どの。あなたを推挙しておいてよかった」
「孔明、同じ考えでいるなら早く君の主公に便宜を図っておくれ。この人はいつもこんなに弱気なのかい?」
「まあ、そんなところです」
肩を竦めて一歩前に出る諸葛亮に、龐統は横目で劉備を睨みながら立ち位置を譲る。士元お前、と劉備が情けない声を上げた。
「そんな性格だったか? 初めて会ったときは」
「お互い様でしたよ、劉荊州様。まさかこんなにか弱い人とは思いませんでした。でもいいんです、私はあなた様を一国の主にすると決めたんですから」
つんと拗ねたように顔を背ける龐統に、くそう、と唸りながら、劉備は己の隣に立った諸葛亮を見た。
「孔明、同じことをもう一度繰り返すつもりかい? さすがの俺でももうわかっているぞ」
「そうですか、なら、どうすべきかももうわかっているんでしょう?」
ぐ、と歯を食いしばって言葉に詰まる劉備に、横から張飛が茶々を入れる。
「おいおい義兄、ひと回り以上も年下の連中に言わせっぱなしでいいのかい?」
「口先で勝てる相手なら軍師にゃあしてないだろ!」
「さもありなん!」
呵々大笑する張飛に、彼は当てにならぬと踏んだ劉備は隅っこの床几にだらりと腰掛けている簡雍をすがるように見つめたが、彼もまた目を細めて小首をかしげるばかりである。
口を開いたのはその隣に坐る伊籍だった。
「劉季玉の配下たちのことならお気に掛けますな。張子喬どのたちの言を信ずれば、彼らにも彼らなりの矜持があり、そして必ずものの道理も弁えておりましょう。我が君がその威徳でもって光輝を益州に広く行き渡らせ、善政でもって民を安んじたならば、彼らとてそれが本望に違いないのです」
パシンと自身の膝を叩き得意げな表情をする伊籍に、その通りです、と龐統が同調する。
「多少の無茶を通す自覚があるなら、あなた様の敷く善道を益州の臣と民とに正しく指し示すことがそれに報い得る唯一の方策です。そうして国が安定したところで彼らに新たな故郷を与えてやれば、誰も“信義”に背くことはいたしません」
「信義……」
龐統の言葉を受けてぽつりと劉備は呟く。龐統は、少なからず自覚的にその言葉を用いた。
「信義、信義ね」
ストンと劉備は自身の座席に腰を下ろし、困ったように頭を掻いた。
「そうだ。いくら荊州が居心地がよくても、公安はともかくいつまでも江陵にはいられん。ここは肩身が狭いな、だろう、孔明」
名を呼ばれた諸葛亮は、目を伏せてひとつ首肯する。
「ええ。ですが江陵にも人材は残しておくべきです。それも……この鼎の地に立つに相応しい人材を」
「それってお前のことかい?」
己の言葉に沈黙を返す彼にふと小さく笑んだ劉備は、そこでようやく政堂の隅で成り行きをじっと見守っていた益州の二人の使者に視線を寄越した。
「子喬、孝直、待たせてすまないね。こっちへ来てくれ……劉玄徳とその一派は、お前さんたちの要請を受けることにした」
手招きされるがまま劉備の座前に膝をついて礼をする二人に、そう堅苦しくならんでくれ、と彼は笑う。
「劉益州どののため、北の宗賊共を討つ手助けをしよう。すぐに支度を整えて出立するから、お前さんたちは先に戻って劉益州どのに劉荊州の来訪を伝えてくれ」
「は、かしこまりました」
「劉荊州様、よくぞご決断くださいました」
顔を上げた二人のうち、法正がまっすぐに劉備を見て、お待ちしております、と低い声で続けた。それに応えて劉備は頷き返す。
程なく、江陵の地に関羽、そして諸葛亮の二人の将を自身の名代として残し、劉備の軍勢は西の隘路を抜けて益州へと入った。
紆余曲折、劉備が益州を獲るのはそれから二年と少しの後、建安十九年夏五月のこととなる。折しも孫権がその本拠地を秣陵に移し、いよいよ北の曹操と相対し始めた矢先であった。
◇
建安十八年末には陸口に駐屯する魯粛の下に劉備による雒城包囲の報が届いていた。両軍の趨勢を見ても劉璋の敗北、また劉備による益州獲得は時間の問題であろう、と彼は見当をつけた。建安十六年に孫軍の一団が荊州を退いてから二年が経ち、魯粛としては漸う事が成ったかという思いでいる。関羽、そして諸葛亮という股肱を荊州に残し、手回しに時を要したとはいえ――その諸葛亮も軍師欠員の報を受けて益州に向かわざるを得なくなったのであるが――劉備の類まれな軍事手腕を持ってしてもやはり侵攻戦には多大な労力と時間を払う。ましてや孫軍がこれを成そうなどとは到底敵わぬことだったやもしれぬ、と彼は独りごちた。
他方で、同時に聞いたあるひとつの報に魯粛は深く悲嘆した。諸葛亮が益州入りせざるを得なくなった軍師欠員、つまり龐統の横死である。
知り合った当初には――魯粛にはさっぱり理由が判然としないのであるが、二人の間に軋轢があり、それを魯粛が取りなす形で龐統は劉備の麾下に入った。その際に諸葛亮と同位の軍師中郎将に任ぜられ、劉備の軍事の一翼を担うことになったのだとは魯粛も聞いていた。確かに大きなことをさせよと取りなしはしたが、まさか人物評が大好きな内政屋が“あの”劉備の軍事に携わることになるとはね、と笑い、しかし自身も孫権の下で似たような羽目になっているのだと思い出しておかしくなったものである。
とはいえ、軍師中郎将とは大将である劉備の傍らにあってその補佐を担うのが主で、まず前線に出ることはないだろうと魯粛は踏んでいた。何より彼に再会するためには互いの生存が最低条件なのだから当然である。しかし、敵の攻撃が劉備の間近まで迫ればそれすら危ういだろう。
魯粛は、数年前には己の名ひとつと少ない手勢だけ持って命からがら逃げていた男と、内政屋上がりの人を愛する小柄な軍師を夢想した。
「感傷はいかんね。気が鈍る」
誰に言うでもなくぽつりと呟き、魯粛は立ち上がる。魯粛の個人的な劉備に対する好意と、孫権陣営、劉備陣営の間で発生する外交上の摩擦は別の問題だ。
かつては我が軍の益州攻略を手助けせぬと拒否しておきながら、己はしっかりと情勢の隙をついて益州を略取せしめるものか――劉備の益州入りを知った孫権の言葉である。なるほど、周公瑾どのは斯様に先見の明があったのだと、先達ての濡須口での衝突を受けて任地より一時帰還した魯粛との会談の席で、孫権は忌々しそうに吐き捨てた。
元より劉備は孫権よりも遥かに軍事経験が豊富で、北は幽州より出でて荊州まで戦いに戦いを重ねながら渡り歩いてきたような男である。当人の老獪さに加え、彼の麾下にある将兵たちの武勇、諸葛亮ら軍師たちの智謀が、例えば“劉備に安定した地盤を与える”ことに収斂し先鋭化するならば――恐らく、“孫権を盟主として江東の地盤を守り固める”ことに重きを置く孫軍に太刀打ちできるとは、魯粛にはどうしても思えなかった。
孫軍には飢餓感がない。魯粛は、彼自身ですらそうであると知っている。なぜなら今己が率いているのは、亡き周瑜の遺した将兵たちなのだから。周瑜はまた、彼自身の肉体が滅びても決して失われることのないものを孫権や魯粛の中に遺していった。孫権に限って言うならば、彼は亡兄から託されたものをずっと携えて事業を展開させている。
江東に住まうのは、多くがこの地方に由来する豪族たちである。そして孫権は、その江東を武力平定し当地に地盤を築いた孫策の後を継いだに過ぎない。恐らく、今孫軍に与する者たちの多くが未だにこう考えているに違いない――己の安寧が確かに約束されるなら、なにも、彼よってでなくてもいい。
――それじゃあ困るんだよ。
誰に向けるでもなく不敵な笑みを浮かべて、ばたりと勢いよく扉を開いた魯粛の耳に、すぐ近くから上がった悲鳴が飛び込んでくる。見れば、孫権の親近監の一人である山越の青年が目をぱちくりさせて魯粛を見ていた。
「び、びっくりしたあ。今お呼びしようと思ったのに」
「えーと、衛君? だったかな? 謹慎は解けたのかい」
親近監の青年――衛奕の登場に内心驚きながら尋ねる魯粛に、彼は照れくさそうに笑って頷いた。
過日の濡須口での衝突で孫権とその親近監らは“共謀”し、孫権による敵陣営への単騎突入という変事を起こした。左異、そして衛奕が孫瑜の気を引き、孫権と谷利が密かに保屯、麻屯出身の水夫を忍ばせておいた船に乗り込む。西岸で公孫陽の軍勢が破られ、兼ねてから続いていた災害のこともあり諸将がそれぞれの陣営で兵の慰撫と安寧に努めている間だからできたことだった。
「ひどいですよねえ、奮威様も。あんな力任せにふん縛らなくても」
「いや、話を聞くだに君ら大概のことをしでかしたよ。俺がその場にいても止めてたね」
「ほんとですか。でも我が君は無事だったんだし」
「無事じゃなかったら君の首は繋がってないぜ……」
そりゃ大変、と他人事のように笑う衛奕にため息を吐きながら、我が君がお呼びかな、と問うと、彼は大きく頷いて先導するように歩き出した。
魯粛が秣陵に滞在している間、孫権は、軍議の場を設けるときもあれば単に雑談がしたくてなどと言い訳することもあったが、常に魯粛を傍近くに呼びたがった。
結局、濡須口での衝突で行方知れずとなった董襲、そしてその麾下の兵たちは一部を除いて今も遺体が見つからないままだという。下流域で捜索に当たっていた孫韶からも船の残骸がいくつか回収された報告は寄せられたが、将兵の遺体の発見までは至らなかったらしい。現在は董襲の後任の偏将軍に陳武を任じ、濡須の砦には平虜将軍となった周泰をその督として配置し、朱然、徐盛らの若い将たちを補佐につけて守備に当てている。曹軍は一時撤退したとはいえ、兵糧を蓄え機が満ちれば再び侵攻してくるだろう。孫軍は次の手を考えねばならなかった。それも、曹軍の意気を挫くような効果的な一手である。
政堂に入った魯粛の目に、お待ちしておりました、と嬉しげに眦をすぼめる孫権の笑みが映る。昨日も、一昨日もそんなような表情をしていた。それは少なからず孫権の不安を表しているようにも思えて、魯粛は胸が締め付けられるような心地がした。
孫権の斜め後ろには、どうやらこちらも謹慎が解けたらしい谷利と左異とが控えている。谷利などは事の次第を孫瑜より報告された張昭の憤怒を真正面から食らい、その苛烈さは孫瑜ですら見兼ねて仲裁を入れるほどであった。それでもなお張昭の怒りは収まらず、谷利は投獄に加え棒叩きの刑まで受けるところであったが、これは孫権の、利が罰を受けるのであれば己も受けねば道理が通らぬ、という一言で棒叩きだけは何とか沙汰止みになったという。秣陵に帰還し経緯を孫権に聞かされた魯粛が気遣って獄中の谷利を訪ねると、投獄は二度目ですので、と存外平然として坐している彼がいて呆れ返るばかりであった。
――ともかく、谷利にしろ左異にしろ、孫権の隣にあるほうが見慣れていて心安いものだ。魯粛に笑みを向けられて、彼ら二人も会釈を返す。そこに、ごほん、と大きな咳払いが聞こえて、魯粛は慌てて音の発生源である張昭へ丁重に礼をした。
程なく、厳畯や諸葛瑾ら孫権の傍近くで政務に当たる文官たちや、秣陵に駐屯している韓当、甘寧、凌統、陳武らの武官たちが政堂に集まってきた。彼らがことごとく席に着いたのを眺め、孫権はひとつの書簡を彼の前の机に置いた。
「尋陽の呂子明どのより、皖城攻略の上陳がありました」
「ほう」
思いがけない言葉に嘆息した魯粛を孫権はちらりと見、またにこりと微笑んで一堂に視線を戻す。
「曹孟徳が皖城に朱光なる人物を新たに盧江太守として送り込み、この周辺で屯田を始めているとのことです。先達ての盧江人の某が同様のことをしていたときには子明どのの攻撃と敵方の自壊で事なきを得ましたが、こたびは数万規模の人員が動いているという報告です」
荊州戦役の前後、それまで盧江太守を務めていた雷緒が数万の兵を引き連れて劉備に帰順したことで太守不在となった当地に目をつけた曹操が、同じく盧江人である謝奇を盧江郡の西、蘄春郡の典農官として抜擢し、皖城周辺に於いて屯田を始めさせた事件があった。やがてその屯田兵らが周辺、とりわけ孫権の統治が及ぶ地域で略奪を繰り返すようになり、尋陽県令を務める呂蒙が彼らに帰順を働きかけるも受け容れられなかったためこれを攻撃したところ、屯田兵たちの略奪は止み、謝奇の麾下にあった数名の部将が呂蒙に投降を申し入れてきたのである。
「数万ね……ここに敵方の根城を造られると厄介です。揚州から西へ出ることが格段に難しくなる」
魯粛の言に孫権は頷き、谷利に促して呂蒙からの書簡を彼に回させた。それを受け取り目を通しながら、魯粛は何度も首肯する。
「“皖城周辺は肥沃な土地であり、作物が十分に収穫できればすぐに軍備が整い、数年もせぬうちに揚州と荊州の間に曹軍の橋頭堡を築かれてしまうだろう”……然りですね」
「ええ。加えて彭沢の呂子衡どのより、鄱陽の不服従民を内応させる使命を持った間者を捕捉したとの報告も入っております」
孫権の続けた言葉に政堂がにわかにざわめいた。それまで黙っていた諸葛瑾が、殿、と僅かに声を震わせて膝を孫権に向ける。
「呂将軍の進言を容れ、すぐさま皖城攻略の軍勢を出すべきかと思われます。曹軍に時を与えてはなりませぬ」
「ええ」
我が意を得たり、というように孫権は応じ、おもむろに立ち上がって群臣の前に歩み出た。魯粛は目を細めて諸葛瑾を見、すぐに孫権に視線を戻し声を上げる。
「わたくしも呂子明将軍に賛同します。既に部将たちが西は江夏郡まで進出している今、盧江に楔を打ち込まれることは看過できませぬ」
「無論、その通りです。他に意見のある方は」
魯粛の言を受けた孫権は群臣を見回し、誰にも意見する気配がないのを感じ取ると、脇に控えている書部の胡綜と徐詳に呼びかけた。
「尋陽の呂子明将軍にすぐに伝令を。拙速にて皖口まで軍勢を率いて来られますようにと」
「かしこまりました」
「皖口まで?」
訝るような厳畯の声に、孫権は然りと頷いてみせる。
「この丹楊からも兵を出します。西に展開している軍をこれ以上動かして、荊州に残る劉玄徳どのの軍勢の動向に対応できなくなっても困りますから」
その言葉にいくらか険が混ざり、まだ根に持っているなと魯粛は苦笑しつつ、ぱしんと膝を叩いて皆の目線を己に向けさせた。
「では、わたくしが軍を動かしましょう。西と同様にこの秣陵からもそう多くの軍勢は動かせますまい。わたくしと、そうですね、もう一人二人くらい……」
そうして政堂に居並ぶ、皆一様に気概を見せる武官たちを見渡した魯粛の耳に、ええ、と孫権の同意の言葉が聞こえた。
「私も出ます」
「そう、我が君……へえっ?」
「殿!?」
張昭が身を乗り出すのを、孫権が彼の前に歩み出ることで制する。
「韓将軍、陳将軍には秣陵の守衛に当たっていただき、張公には将軍府の留守を預かっていただきます。甘将軍、凌校尉は魯子敬どの、私と共に西へ。子瑜どの、曼才どの、参軍として同道をよろしくお願いいたします。呂子明将軍と落ち合い次第、皖城を攻撃して落としましょう」
「か、簡単に言いますね……」
魯粛が苦笑交じりに言うのに、振り返った孫権は小首をかしげて笑った。
「皆様がいてできないことがありますか?」
その言に、魯粛は言葉に詰まる。主君による絶対の信頼。人に仕える人ならば、これほど欲するところのものはない。
「…………、……ありませんね」
魯粛は孫権の前にさっと進み出ると片膝をついて拱手し、深くこうべを垂れた。
「謹んで拝命いたします。すぐに出立の支度を整えますゆえ、御前を辞去することをお許しください」
「……えっと……はい、わかりました、が……」
急に歯切れの悪い返答になる孫権を不思議を思い、僅かに首をかしげた魯粛が顔を上げると、彼は困ったような表情で己を見下ろしている。
なんとなくその理由が察せられるような気がして魯粛はにんまりと口許に弧を描き、彼が何か口にしてしまう前に、では、と勢いよく立ち上がって政堂を後にした。
◇
建安十九年、夏五月の初め。折しも劉備が西の益州で統治の国都である成都を陥落させた頃、東の丹楊、そして西の尋陽の二方面から出立し皖口で落ち合った孫軍は、皖城邑の東八里のところに陣を構えた。
本陣の幕舎に入ってきた呂蒙は入り口の脇に腕を組んで佇む甘寧の姿を見、よかった、と一言口にした。
「子明どの、よかったとは?」
孫権が尋ねると呂蒙はニヤリと得意げな笑みを浮かべ、大股で演習台へ歩み寄る。
「殿、こたびの攻城戦は拙速なれど果断の攻撃が要。であれば、甘将軍ほどその任にふさわしい将はおりませぬ」
ほう、とまたしても魯粛は呂蒙の言に嘆息した。
孫権もまた目を輝かせて一歩呂蒙たちのほうへ踏み出すと、その心は、と上ずった声で問うた。
「皖城の城壁は幸いさほど高くありません。以前したように攻囲ではなく、雲梯を架け城壁を登り速攻を狙います。そこで甘将軍を升城督として先陣を切っていただき、内部から城門を開け、そこへ我々が一息に攻勢をかけるのです」
「なんと……」
孫権は感心したように口許に手を当てぽつりと零したが、すぐに心配そうに眉根を寄せて甘寧を見た。
「だが、城壁から矢が降り注ぎます。将自らが乗り込むのは些か……」
「我が部隊は夷陵でも似たようなことをしていますからご心配なく。我が君、俺をあなた様の眼前で活躍させてくださいよ」
然り、呂蒙は大きく二度頷いた。
「甘将軍はかつての荊州戦役でもたった数百の手勢で夷陵城を速攻し降伏させております。その手腕があればこそ、こたびの戦でも優れた武勇をお見せいただけるでしょう」
そうして演習台に向き直り、呂蒙は皖城に見立てた駒を指差した。
「何より現在当地に入っている数万の人員のうち、その多くは専ら屯田に携わる庶民であり、老人、女子供も少なくありません。そして中でも皖城本陣に詰めている兵士はどれだけ多く見積もっても一万には足らないでしょう。我が君、無礼を承知で申し上げます。あなた様の牙門兵たちを僅かばかりで構いませんので借り受けることはできますでしょうか。彼らに凌校尉と共に皖城周辺の邑を速やかに制圧していただきたいのです」
手を拱いて己を見る呂蒙に孫権はぱっと晴れやかな笑みを浮かべて、無論です、と答えた。
「僅かと言わず五百でも千でも預かってください。利、公崇と仲進を呼んできてくれないか」
「わかりました」
「えっ! い、いや、それほどは……」
孫権の命を受けて幕舎を辞去する谷利の腕を取りかけて、呂蒙は慌てて手を引っ込める。振り返らずに彼が出て行ってしまって呂蒙は焦った。彼の当惑を見て取ったのか、おかしそうに笑ったのは魯粛である。
「大盤振る舞いですねえ、我が君」
「もちろんですとも。子明どのがこんなに頼もしいのですから、出し惜しみしてはいられないでしょう」
二人の会話を聞いてようやく顔を青くした呂蒙の脇腹を甘寧が小突いた。
「なんでそこで急にへたれるんだよ。俺のところに来た伝令にすら気丈に行けなんて言ってたくせに」
「そっそれは……!」
言葉に詰まって今度は顔を赤くした呂蒙の前に孫権は歩み出ると、彼は両手でそっと呂蒙の左手を取った。
「ありがとうございます、子明どの。あなたの知勇に私はとても勇気づけられます」
「殿……」
赤い顔を一層赤らめて照れくさそうに口許をもごもごとさせる呂蒙をさらにからかおうと魯粛が口を開いたとき、幕舎の外から孫高、傅嬰の到着を告げる声がした。彼らは牙門将として本陣の幕舎の程近くに控えていたのである。
中へ、と孫権に言われ幕舎に入ってくる二人はそれぞれどこか気概に満ちた表情をしている。
「利から話は聞いているか?」
「はい。凌校尉と共に皖城邑の迅速な制圧を」
孫高が答えて呂蒙を見ると、彼は先程までの当惑ぶりから一転、きりっと引き締まった顔立ちになって大きく頷いた。
「先程の話の続きですが、魯将軍の軍勢には皖城の南面を除く三方の包囲をお願いできますか。ただし無理な攻勢はかけず、しかしそれと気取られぬよう矢による牽制を主としてください」
「ああ、わかった」
「凌校尉の軍勢は周辺邑の制圧が済み次第、魯将軍に合流してくれ。孫、傅両将の率いる牙門隊はそのまま邑の慰撫に務め、わかっていると思うが……」
呂蒙が言う前に、もちろんですとも、と傅嬰が頼もしく首肯する。
「捕虜にした民や兵は傷つけない。大前提です」
「うむ。余計だったな」
喉を鳴らして笑った呂蒙は、そうして甘寧を見た。口の端を上げて笑む彼は、任せておけ、とはっきりと声を発する。
「ただ、援護は頼むぜ。乗り込んだら俺たちはすぐに中へ突っ込むからな」
「無論です。では、攻撃開始は明朝、卯の初刻に」
それを聞いた孫権が、ああ、と感嘆の声を上げる。皆がそちらへ顔を向けると、にっこりと笑った彼が、いいことを思いつきました、と口にした。
「朝のうちに片をつけてしまって、皆で天柱山を眺めながら食事を取ることにいたしましょう」
「はは……妙案ですな」
魯粛の同意を得て孫権はひとつ頷くと、演習台を腕を組んで睨みつけ黙っている凌統に目線を向けた。
「公績、少しその辺を見て回らないか?」
「えっ?」
不意に声をかけられ驚きに肩を震わせながら凌統は、なぜ私が、と言わんばかりの表情をしている。彼を気にするふうでもなく孫権は彼の手を取ると、入り口脇に控えていた谷利を始めとする親近監たちと連れ立って幕舎を出た。
申の正刻を過ぎてもまだ空は明るく、夕暮れの気配もない。盧江郡の郡治皖県は大別山をその背景にするが、その南を流れる長江の周囲百里ほどは平地が広がっており、初夏の光に草木はきらめいている。
陣営を当て所なく彷徨いながら、孫権は軍務をこなす将兵たちに声をかけて回っている。その後ろをついて歩く凌統は未だになぜ己が呼ばれたのかわからないふうで、訝るように僅かに眉根を寄せたままその背中を見ていた。
やがて陣営の端まで来ると、孫権はくるりと凌統を振り返った。
「ここへ来るのも久しぶりだな」
その言葉にはっとなった凌統は、孫権に大きく歩み寄って頷いた。
「はい。あのときは……ここ皖城で李術があなた様に叛旗を翻したのでした」
「ふふ、覚えているか。公績はまだ字をもらったばかりだったな」
こくんと頷く凌統に微笑みかけ、孫権は彼の後ろを顧みる。
「もう酒も飲めるようになったか」
「もちろんです。そりゃあ好き嫌いは……ありますけど」
「そんなこと大したことじゃないさ。お前は酒よりも書のほうが好きな男だしな」
おかしそうに言う孫権の顔は、後ろに控える凌統には見えないのにきっとその口許には笑みが浮かんでいるのだろうと察せられて、凌統も心なしか安堵する。
「あのときは、とても大きい城に思えた。藩垣は高く、長く……そして私はあまりに矮小で無力なのだと」
傍らで彼の言を聞く谷利も、あの夜のことを思い出していた。闇に溶けるような孫権の昏い顔を。
「だが、先ほど子明どのは皖城の城壁は然程高くないと事もなげに言った。そうして改めて城を眺めてみれば、確かにそうだったのだ……私はあのとき、これからは江東を平らげる戦をすると決めた。そして今もまた、新たな宿願のためにこうして皆に働いてもらっている」
振り返った孫権は谷利を見、凌統に目を遣る。そして凌統の前へ歩み出るとその手を取り、そっと撫でさすった。
「お前もまた、苦楽を共に過ごしてきた私の大切なともがらだ。立派になったな、公績……」
俯き加減になる孫権の赤い髪の流れを見て、凌統は気が付いた。己の身長が、孫権とそう変わらないくらいまで伸びていることに。
――あの日、父が死んだ日、孫権は己を抱きしめた。少し窮屈そうに。
凌統は不意に理解した。孫権がなぜわざわざ己のみを連れてこうして会話してくれるのかを。
そして同時に思い知ってしまった。己の体内について消えない悲傷、黒々としたその跡の存在を。
鼻の奥がつんとして凌統は思わず、孫権の体をあの日の己が彼にそうされたように抱き返したくなった。
申し訳なさと、どうしようもないやるせなさとを見透かされないようにするために。